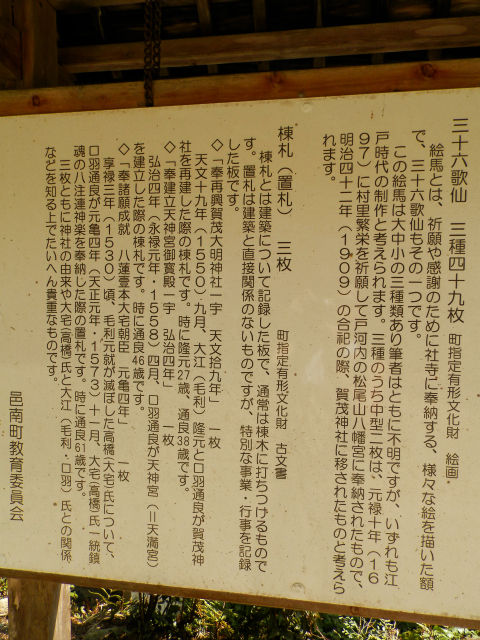「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(後編)澄元方の上洛戦敗退と将軍義稙の淡路出奔事件の顛末
以前の記事 『「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(中編)将軍義尹の甲賀出奔事件の背景』 では、永正10年(1513)に将軍がわずかな供だけを連れて突如京都から出奔した珍事件の背景や、細川高国が京兆家当主となってから内衆の再編が進んでいたことなどを紹介しつつ、「義稙」と改名した将軍がどのような政権構想を抱いていたのかを探りました。
そして、大内義興が帰国した経緯については独立した記事として 『大内義興が帰国に至った背景―在京中に起きた「安芸国人一揆」と「有田合戦」の関係、遣明船の永代管掌権を獲得した件について』 で考察しました。
今回は主にその後の話、阿波より機を窺っていた細川澄元とその与党による上洛戦を通じて起きた将軍義稙と細川高国の関係の変化、そして澄元と将軍義稙を仲介した赤松義村とその重臣・浦上村宗の対立を併せて見つつ、なぜ高国と対立して出奔した将軍義稙の復帰が叶わず、高国に擁立された義晴が新たな将軍として受け入れられたのか、そしてその後の義稙の動向が「阿波公方」にどう繋がったのかを考察します。
同シリーズ記事
最後となる今回はデータ量にして前編や中編の3倍以上と、かなりの長文になっていますので、覚悟の上でどうぞ……。
写真は阿波平島にある阿波公方足利家の菩提寺、西光寺の義稙、義冬、義栄三代廟所。
忙しい人のための、義稙の行動について検討すべき疑問点まとめ
全部読むのはしんどい方のために、対象を義稙の行動に絞って、この記事で検討の必要性を訴えているいくつかの疑問点について、まとめておきます。
澄元方の上洛戦の際に京都に残った義稙は高国を見捨てたのか?
高国が義稙を残して近江へと逃れた直後には、澄元から義稙に恭順を申し出る書状が送られており、また、三好之長が入京するまでの間には、義稙の方からも澄元派の赤松義村より「京都無事」を祝って太刀や馬が贈られたことへの返礼を送っている。これらのことから、京都に残留した義稙が澄元を受け入れる姿勢を見せていたのは間違いない。
しかし義稙は同時に、澄元に与する畠山義英の攻撃を受け河内高屋城に籠城していた畠山稙長を激励しており、近江に同行しなかったことをもって高国を見捨て澄元を支持したと断ずるのは妥当ではない。
また、高国はその後近江で両佐々木氏など近国からの援軍を得て帰還するわけだが、そもそも高国の敗退以前に両佐々木氏に支援を要請したのは義稙自身であり、そのような展開は想定できたはず。
そして、澄元死去の噂が流れていたことも合わせて考えると、京都に残留した義稙は高国が戻るまで時間を稼いでいたか、あるいは澄元と高国を両天秤にかけつつ状況を静観していたと見るのが妥当ではないか。
義稙は高国の専横を嫌って出奔したのか?
義稙は出奔に際して思い通りに執政できないことの不満を書き残しているが、高国の専横と評すべき行動や対立要因を具体的に挙げるのは難しい。
ただ、出奔直後から讃州家を頼り、約二ヶ月後には明確に高国の討伐を謳っていることから、義稙の側には高国への不満があったようだ。
出奔に際しての公卿の反応からは、両者が対立関係にあったと見られていることと、義稙側近の畠山式部少輔が反感を集めていたことが窺えるが、実際のところはよく分からない。
義稙は自身の後継者をどのように考えていたのか?
現在の通説では義稙が義維を養子としたために将軍家の分裂が継続したと捉えられて、義澄系(義澄→義晴→義輝→義昭)と義稙系(義稙→義維→義栄)に分類されている。
しかし、義稙と義維の親子関係を伝えるのは史料としては良質とは言えない軍記や伝承のみで、当時の一次史料によるとむしろ義稙は出奔以前から義晴を後継者に迎えようとした形跡がある。
また、出奔の翌月には義晴擁立が進められ、そのまま抵抗なく受け入れられたことを考えると、義晴を次期将軍候補とすることは以前からの既定路線であった可能性が高いのではないか。
義稙は将軍復帰の意志を義維に託したのか?
義稙は大永元年10月から11月にかけての堺上陸時の和睦交渉失敗により淡路へ退去して以後、大永3年4月に死去するまでの間、帰洛に向けて活動した形跡はなく、将軍復帰はもとより帰洛を望んでいたかどうかも分からない。
そもそも、今のところ信頼できる史料で義維の存在が確認できるのは義稙死後の大永7年3月以降であり、義稙の死が京都に伝わったのもその後であった。
義稙の遺臣が讃州家を頼り、義維を義稙の「猶子」として擁立したのは確かだが、実際には義稙が義維と対面したかどうかすら分からない。
目次
今回の記事はとても長いので目次を用意しました。
- 同シリーズ記事
- 忙しい人のための、義稙の行動について検討すべき疑問点まとめ
- 目次
- 将軍・足利義稙が有力守護による連合体制からの脱却を図り、側近の畠山式部少輔順光を引き立てたこと
- 各地の反幕府勢力と呼応して再び上洛戦を展開した、細川澄元と三好之長
- 細川澄元と結んだ赤松義村の事情……浦上村宗との対立の始まり
- 細川高国が近江へと逃れた一方で、京都に残留した将軍・足利義稙の真意とは?
- 細川澄元と三好之長の主従が死去し、細川高国が京都に復帰したこと
- 浦上村宗と戦い続けた赤松義村を支えたものは何だったのか
- 将軍・足利義稙が旧澄元派を頼って細川高国を討つために京都を脱出したこと
- 亀王丸が次期将軍「義晴」として擁立されてなお諦めなかった赤松義村の最期(妄想注意)
- 細川高国による新将軍の擁立が人々の支持を得た一方、高国打倒を諦めた義稙が畠山卜山とともに淡路に退去したこと
- 義稙の遺臣たちが「堺公方」義維を擁立し、義稙の系譜が「阿波公方」家に伝承されたこと
- 義稙終焉の地・撫養にある撫養城跡を巡ってみた
- 参考書籍、史料、論文、Webサイト等
- 浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』(思文閣出版)
- 山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』(戎光祥出版)
- 今谷明『戦国 三好一族』(洋泉社)
- 清水克行・榎原雅治(編)『室町幕府将軍列伝』(戎光祥出版)
- 渡邊大門『備前 浦上氏』(戎光祥出版)
- 播磨学研究所・編『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)
- 大石泰史編『全国国衆ガイド 戦国の "地元の殿様" たち』(講談社)
- 若松和三郎『戦国三好氏と篠原長房』(戎光祥出版)
- 那賀川町史編さん室『平島公方史料集』
- 京都府教育委員会『京都府中世城館跡調査報告書 第3冊(山城編1)』『第4冊(山城編2)』
- 兵庫県史編集専門委員会『兵庫県史 通史編 第三巻』
- 西宮市史編集委員会『西宮市史 第一巻』『第四巻 資料編1』
- 国書刊行会編『続々群書類従 第三 史伝部2』(続群書類従完成会)
- 塙保己一編『続群書類従 第二十三輯下 武家部』(続群書類従完成会)
- 塙保己一編『群書類従 第二十一輯 合戦部』(続群書類従完成会)
- 高橋遼「戦国期大和国における松永久秀の正当性─ 興福寺との関係を中心に─」
- 西原正洋「永正の錯乱以降における細川氏の本庶関係―典厩家を軸として―」
- 馬部隆弘『細川晴元の取次と内衆の対立構造』ヒストリア 258号 (2016.10)
- 落ち穂ひろい
- やまんなか: 亀王丸と義村
- 二周年です(…のおまけ): Muromachi通り
- 室町幕府奉行人一覧
- 東京大学史料編纂所データベース
- その他
- 同シリーズ記事
将軍・足利義稙が有力守護による連合体制からの脱却を図り、側近の畠山式部少輔順光を引き立てたこと
将軍義稙は永正10(1513)年に出奔事件を起こし、これによって細川高国、大内義興、畠山義元、畠山尚順の四人に対して「諸事不可背御成敗之由申入云々」と、自身の裁定に従うことを約束させたのですが(中編『都を仰天させた将軍義尹の甲賀出奔と、帰洛の様子に見る幕閣の構成』)、永正15年(1518)8月に大内義興が帰国した時点で、すでに京都に残留しているのは細川高国ただ一人となっていました。
実は大内義興の帰国以前にも、能登守護の畠山義元は領国の錯乱を受けて永正10(1513)年10月に帰国した後、永正12年(1515)9月には死去していて、後継者の義総も引き続き能登への在国を余儀なくされていたのです。
また、畠山尾州家の当主・畠山尚順(すでに出家して「卜山」と号していました)も、永正12年頃には嫡子の次郎稙長の元服に伴って自身は京都を去り、領国紀伊の広城を拠点としてその統治に力を注いでいました。
永正15年(1518)の段階で、将軍義稙のもとで幕政に参加していた有力守護の多くがすでに京都を去り、領国統治のために在国せざるを得なくなっていたわけです。
そして、義稙もこの状況に何も手を打たなかったわけではなく、彼ら有力大名に頼らない独自の権力基盤を形成しようと考えたようで、そのために重用されたのが「明応の政変」以来、父と共に義稙(義材・義尹)に近侍していたという、畠山式部少輔順光でした。
この畠山順光の経歴はとても興味深いもので、明応2年(1493)5月、細川政元が義稙(義材)の身柄を龍安寺から側近の上原元秀邸へと移した際、身の回りの世話をする役目を受けたのが同朋衆の木阿弥で、順光はその息子でした。つまり、彼は元々奉公衆のような名のある武家の出身ではなかったのです。
この時、義稙(義材)が越中に脱走したために木阿弥父子は逮捕されて拷問を受けたのですが、彼らはその後も義稙(義材)からの信頼に応え、明応8年(1499)に河内で挙兵した畠山尚順と連携して上洛戦を展開した時には連絡役を務めました。
永正5年(1508)6月についに義稙(義尹)が京都帰還となり、父の木阿弥と共にその忠義を愛された順光は、この時に「畠山」の名字を賜ったとのことです。畠山家の惣領である尚順に無断で与えられたとは思えませんし、両者は共に義稙(義材・義尹)と強固な信頼関係を築いていたことを考えると、「順光」という名も尚順から偏諱を授かったものでしょうか。
そのような経歴を持つ畠山順光は永正14年(1517)4月、義稙の命を受けて将軍上使として大内義興の兵と共に大和へ侵攻、大和国内の武士たちの抗争を鎮圧しました。順光はこの時、興福寺の「官府衆徒」の地位をも獲得しようとしたそうです。
中世の「南都」大和国は守護を設置せず興福寺が支配権を持っていた特別な土地であり、衆徒というのは興福寺領の在地領主など半僧半俗の有力武士のことで、その代表者で構成されるのが「官府衆徒」あるいは「衆中」と呼ばれる機関でした。奈良市中の警固や犯罪人の検断を担っていたこの機関に将軍直臣の畠山順光が名を連ねるということはすなわち、将軍による大和支配への介入を意味していたと思われます。
余談: 興福寺の官府衆徒としては筒井氏や古市氏が有名ですが、彼らは応仁・文明の乱を通じて東軍方と西軍方に分かれて対立し、畠山政長(尾州家)と畠山義就(総州家)の争いにも積極的に加わった末に、管領・細川政元の頃にはその武力介入を招き、大和は幾度となく赤沢宗益(赤沢朝経、澤蔵軒宗益)の猛攻にさらされて甚大な被害を受けました。
その後も古市氏や越智氏は畠山総州家(義英)と共に澄元方に与しており、義稙が畠山順光に大和侵攻を命じたのも、旧義澄派である澄元与党の鎮圧が目的であったとも考えられます。
なお、後年の三好政権における大和支配の責任者となった松永久秀は、永禄5年から6年頃には正式に官府衆徒の棟梁である「官務」の地位を獲得しており、大和においては戦国時代も末期に至ってなお、興福寺を中心とした在地支配の枠組が必要とされていたことが窺えます。
畠山順光の官府衆徒への就任は義稙の目論見通りにはいかなかったようですが、その翌年の永正15年(1518)3月17日、畠山順光の邸宅にて異例の将軍御成が行われました。
明応2年の政変以後、これまで将軍御成の対象とされたのは管領を務めた当時の細川政元と細川高国、代々政所頭人を務めた伊勢守家当主の伊勢貞宗と伊勢貞陸の他には、永正5年(1508)8月の畠山尚順、永正7年(1510)10月の大内義興、永正9年(1512)4月の畠山義元といった有力守護に対して恩賞として一度だけ行われたものでした。
そのような先例の中で、元々武家の出身ではない畠山順光の邸宅への御成は、鷲尾隆康の日記『二水記』に「不慮の果報、不思議」と記されたように、特異な事件として受け止められたようです。
どうも義稙は良く言えば親愛の情が厚い、悪く言えば贔屓が過ぎるところがあったようで、かつては側近として重用した廷臣の葉室光忠が多くの大名たちから恨みを買ったことが「明応の政変」を招いた要因になりました。
詳しくは後述しますが、畠山順光も後に義稙が京都を出奔した理由として『二水記』に名指しでその振る舞いが非難され、今度の御成が行われた順光の邸宅も荒らされることになります。順光もまた葉室光忠と同様にしがらみの無さから義稙の代行者として重用され、そのために恨みを買う立場になってしまったものでしょうか。
『塵塚物語』の義稙評として「御こころ正直にして、やさしき御むまれつきなり」というのがありますが、実際、幼少期を父の義視とともに美濃で過ごした義稙は、生粋の京都育ちの将軍とは異なる価値観を持っていたように感じます。それは義稙が「下剋上」の時代に相応しい将軍のあり方を模索する中で得たものだと考えますが、少なからぬ京都の人々にとっては忌避すべきものでもあったのでしょう。
大内義興、畠山義元、畠山尚順らの相次ぐ帰国により、有力守護による連合体制から脱却せざるを得なくなった将軍義稙は、このように「明応の政変」以来の忠臣である畠山順光を特別に引き立てることで、言わば側近政治による体制強化を図ったものと考えられています。(山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』)
しかし、西国一の大大名である大内義興の帰国は、永正8年(1511)の船岡山での手痛い敗戦以来、阿波から動いていなかった細川澄元とその与党を再び活気づかせ、将軍義稙と管領細川高国はその対応に追われることとなるのです。
余談: なお、畠山順光邸への御成には、永正8年に澄元方として葦屋河原合戦にも参戦した淡路守護・細川淡路守尚春の子息と思われる「細川淡路」が出席しています。
細川尚春はこの前年の永正14年9月、三好之長によって淡路を追われて堺へと逃亡しており、『細川両家記』によると更にこの翌年の永正16年5月11日、之長によって殺害されるという最期を遂げました。これにより、之長は淡路水軍を傘下に収めたと言われています。
細川家一門の尚春に対して、澄元の部下である三好之長が独断でそこまで横暴に振る舞ったとはちょっと信じがたいところですが、之長の行動は因果応報として、等持院合戦に敗れて高国に投降した彼の身に降り掛かることになります。
各地の反幕府勢力と呼応して再び上洛戦を展開した、細川澄元と三好之長
永正16年(1519)10月のこと、細川澄元を大将とする四国勢の進軍に先駆けて、かつて細川高国が将軍義澄を見捨てて義稙(義尹)方に身を投じた際に標的とされた池田筑後守貞正の遺児・三郎五郎(後の池田信正)が、有馬郡の田中城に拠って挙兵しました。
これに対して、越水城主・河原林対馬守正頼ら高国方の摂津国人たちが協力して攻め寄せたものの、寄手の中には城方と同じ池田一族の池田民部丞の軍勢があり、その中に旧主である三郎五郎に「返り忠」を起こす者が現れたことから軍は混乱し、城方の逆襲を受けて敗退してしまいました。
そして11月には、三好之長をはじめとする四国勢の本隊も兵庫津から上陸し、澄元は神呪寺に陣を構えた後、今度は逆に一万余騎の軍勢でもって、河原林正頼が守る越水城を包囲させました。
(なお、河原林対馬守正頼は一般的には「瓦林正頼」あるいは「瓦林政頼」と表記されることが多いようですが、彼の名字は当時の史料では一貫して「河原林」と記されているため、当ブログではこれに習った表記とします。)
この越水城は、船岡山に敗れて失敗に終わった永正8年(1511)の澄元方上洛戦の後、四国勢の上陸拠点の一つ兵庫津と京都を結ぶ交通の要衝である西宮の防衛拠点として、細川高国が西摂随一の有力国人・河原林正頼に命じて築かせたもので、攻める澄元、守る高国どちらの陣営にとっても極めて重要な城でした。
高国は越水城を救援するため、守護代・内藤備前守ら丹波勢を主力とする4、5千の軍勢を編成して12月に池田城に入った後、後詰めのために武庫川沿いに布陣し、越水城の東側に展開した澄元方と対峙する形となりました。そして、越水城を巡る攻防はこの後も翌年の2月3日に開城するまで続けられることになります。
一方『御内書案』によると、永正16年(1519)10月の摂津における池田三郎五郎の挙兵に先んじて、同年8月に大和にて牢人たちが蜂起したため、義稙側近の畠山順光が鎮圧に向かったらしく、細川高国に宛てて順光への協力を依頼する御内書が残されています。これもおそらく、澄元率いる本隊を支援するための陽動だったのでしょう。
そして、翌永正17年(1520)2月には、阿波に退去していた畠山総州家の義英が大和国人の越智氏などと連携し、尾州家の稙長が守る河内高屋城に攻め寄せました。
義英は永正8年(1511)7月にも澄元方の上洛戦に呼応して挙兵しており、義就流の総州家と政長流の尾州家に分裂した畠山家において、「明応の政変」の経緯から義澄方となっていた総州家の義英は、今度もいわば同じ負け組として澄元と共闘関係にあったようです。畠山尚順が自ら下向して領国紀伊の支配を強化しようとしたのも、彼らに対する備えを固めるためだったのかもしれません。
このように、幕府は永正16年(1519)から17年(1520)にかけて細川澄元とその与党による波状攻撃を受けて動揺し、将軍義稙は12月8日に摂津で陣中にあった細川高国に宛てて「其後者時宜如何候哉。無心元候。早速勝利被待思食候。」と戦況を案じつつ、12月28日には佐々木四郎(六角定頼)に宛てて「連々不可存疎略之由。被聞召訖。彌致忠節者可為神妙候也。」と、支援を命じる御内書を送っています。
(後述しますが、六角氏への援軍要請がすでにこの段階で将軍義稙の意志によって行われていたことは、義稙と高国の関係を考えるに当たって重要なポイントだと思います。)
余談: 幕府の苦境は京都から遠く離れた駿河の今川家にも伝わっていたようで、永正17年(1520)正月13日には今川修理大夫(=氏親。大河ドラマ『おんな城主 直虎』で浅丘ルリ子が熱演した寿桂尼の夫。)に宛てた「就澄元摂州出張之儀。飛脚到来。尤神妙候也。」という内容の御内書案が残されています。
澄元は義稙(当時は義尹)の将軍再任以来、幕府に敵対する形となっていましたが、それは彼が細川政元の後を継いだ成り行きによるもので、義澄亡き今となっては(澄元は義澄の将軍在任中にも義稙との和睦を進言したことがあったほどです)、彼個人には将軍義稙への逆意など無かったでしょう。
しかし、「船岡山合戦」など義稙方との戦いで犠牲となった者たちの無念を背負う立場には違いなく、麾下の国人たちの中には一族が高国派と澄元派に分裂して争った結果、讃州家を頼って阿波への退去を余儀なくされた者もおりました。(「船岡山合戦」に敗死した細川政賢の子で典厩家当主の座を尹賢に奪われていた細川澄賢、前述した摂津瓦林氏の一族なども同様で、阿波に逼塞していました。)
そんな現状を打開するためにも、力ずくで高国を排除して再び京兆家の当主の座につき、将軍義稙の許しを得た上で幕府に復帰する……今度の澄元の上洛戦は、そのような戦いであったわけです。
細川澄元と結んだ赤松義村の事情……浦上村宗との対立の始まり
ここで、今度の澄元の上洛戦とその後の展開に大きな影響を与えることになる、赤松義村と浦上村宗の対立を中心に、赤松家の動向を確認しておきます。
赤松家では、永正3年(1506)頃から前当主・赤松政則の未亡人である洞松院が当主の義村に代わり、守護の意を奉じて黒印状を発給する体制が継続していました。
義村の生年は確実な史料からは不明(系図や軍記類には文明4年、延徳2年、明応3年の記述あり)ですが、『御内書案』によると、永正3年(1506)3月14日付で将軍義澄から赤松伊豆守宛で出された御内書にはまだ「道祖」と幼名で記されているものの、永正5年(1508)2月23日付で将軍義澄が赤松重臣たちに宛てた御内書には、浦上村宗が「浦上幸松」と幼名で記されている一方で義村は「次郎」と記されており、この頃には成人していたものと思われます。
そして、永正9年(1512)に浦上村宗がまだ10代前半の若さで名代として上洛している(中編『将軍義尹が赤松氏を赦免して義澄の遺児亀王丸と和睦したことの意味、その陰で軋轢を深めていた大内義興』)のに対して、守護であるはずの義村はまだ洞松院から権限を委譲されていない状況だったことが窺えます。
かつて、明応5年(1496)に赤松政則が死去した際、5人の重臣たち(浦上則宗、別所則治、赤松則貞、小寺則職、薬師寺貴能)が道祖松丸(後の次郎義村)の守護就任を幕府に要請したのですが、義村を擁立しつつ政局を主導する浦上則宗に反発した一部の重臣たちが赤松播磨守勝範を担ぎ出し、更に別所則治が洞松院を支持したことで赤松家中は分裂し、「東西取合合戦」と呼ばれる播磨の内戦へと発展した経緯がありました。
(なお、永正9年(1512)に浦上村宗と共に上洛した別所則治は翌永正10年に死去しており、その子か孫と見られる後継者の村治は義村からの偏諱を授かっています。別所氏は次第に赤松氏から独立していったとされますが、この頃の動向は定かではないようです。)
洞松院による執政期、義村はたびたび置塩館に歌人冷泉為広を招いて親交を深めるなど、和歌三昧の生活を送っていたと言われていますが、永正12年(1515)頃には側近として三人の奉行を編成して式目を定めるなど、ようやく守護として活動するようになります。
やがて義村は浦上村宗を遠ざけ、村宗と同じ宿老格の小寺則職を重用するようになるのですが、永正15年(1518)7月には村宗の出仕を停止したばかりか、翌永正16年(1519)11月9日、義村は自ら軍を率いて置塩城から出陣し、村宗の本拠地である備前三石城下まで押し寄せ、これを包囲したのです。
背景には赤松家中における高国派と澄元派の対立があり、義村がこの時機に兵を動かしたのは、澄元方の上洛戦を支援するためだったようです。
この三石城攻略戦は、義村側近の奉行・櫛橋則高の計らいによって村宗が降参する形で和睦が結ばれ、義村は12月末に帰陣したのですが、翌永正17年(1520)の2月2日(越水城開城の前日になります)には播磨太山寺に澄元戦勝の祈祷を依頼しており、義村が引き続き澄元と提携していたことは間違いありません。
(なお、『実隆公記』には「浦上勝利」と記されているそうで、三石城の戦いは和睦に終わったとはいえ、義村が村宗の討伐という目的を果たせなかった点で赤松の敗北と見なされたのでしょう。そして、両者の対決は京都でも注目されていたことが窺えます。)
これまで将軍義稙は義村に対して、永正15年(1518)12月2日、永正16年(1519)5月23日、永正16年(1519)11月3日と三度に渡って御内書を送り、澄元に与する被官の成敗や高国との和睦を命じていたのですが、義村は将軍の意に逆らってまでも澄元に肩入れし続けたわけです。
義村がそこまで澄元を支持した理由は定かではありませんが、義村の姉は澄元の実兄に当たる讃州家当主・細川之持に嫁いでいたこともあり、家中にも讃州家との繋がりを持つ者が多かったのでしょうか。
あるいは義村としても、本来中継ぎであったはずの洞松院の執政が長期間に渡ったために、その影響力を家中から排除するには、京兆家の補佐を務めてきた野州家出身の高国よりも、讃州家出身の澄元が幕府中枢に復帰してくれた方が良いと考えたのかもしれません。
(洞松院は細川政元の姉妹、つまりあの細川勝元の娘であり、「船岡山合戦」で澄元方に与した赤松家が後に幕府から赦免されたのも、洞松院と高国のコネに依るところが大きかったようです。)
義村が浦上村宗を排除しようとした理由について、『赤松記』は「浦上掃部助村宗と上の御間、不思議の雑説出来」と、曖昧な記述に留めています。通説的には義村は守護として自立するために村宗からの「下剋上」に対抗したとされていますが、当時の状況を鑑みれば「下剋上」というよりも、澄元との提携を推進する義村にとって、村宗は放置できない存在であったためではないかと考えます。
この後、村宗は洞松院や義村の嫡子・才松丸(後の赤松晴政)だけでなく、前将軍義澄の遺児・亀王丸(後の将軍義晴)をも手中に収めて、高国派として最大の功績を上げることになりますが、前述の通りすでに上洛も経験していた村宗は、早くから高国と関係を持っていたのかもしれません。
細川高国が近江へと逃れた一方で、京都に残留した将軍・足利義稙の真意とは?
さて、永正16年(1519)11月から続いていた越水城の攻囲戦ですが、『細川両家記』によると、年が明けて間もない正月10日のこと、高国方は2万余騎で攻め寄せたものの戦況を覆すことはできず、やがて城方の気力が尽きたために開城する運びとなりました。
永正17年(1520)2月3日夜半、城主の河原林正頼は逃亡して落ち延び、老臣の若槻伊豆守長澄は一人城に残って堂々と十文字に切腹し、後世の語り草となりました。『重編応仁記』には伊豆守の辞世の歌として「花咲かぬ今の憂き身も古へも 身のなる果は変はらざりけり」が伝えられています。
(『細川両家記』が描く越水城の攻囲戦には、城方で剛弓を讃えられた一宮三郎の活躍など見どころが色々あります。細川両家記を読む が詳しいです。)
そして、引き続き『細川両家記』によると、後詰めの高国勢もやむなく池田・伊丹・久々知・長洲・尼崎へと陣を後退、これに応じて陣を進めた三好之長は2月16日に1万7千余で尼崎・長洲へと攻め寄せ、「大物北の横堤」にて香西与四郎と三好孫四郎が太刀打ちしてどちらも名を上げたが、日が暮れて雨も降ってきたので双方兵を引き、その後高国は各城に連絡して京都へ撤退したとあります。(高国の敗因は越水城の攻囲戦の際、正月10日の西宮戎神社の神事、忌籠りの日に戦闘を仕掛けた罰だと噂されたそうです。)
このような戦況の悪化に加えて、京都では正月12日に土一揆が蜂起、28日には将軍第の木屋に放火される事件も起きており、義稙は2月6日に佐々木中務少輔(京極高清)宛で「京都忩劇之條。不移時日令参洛。抽忠節者可為神妙候也。」との御内書を送り、江南の六角氏に続いて江北の京極氏に対しても、速やかに上洛して支援するよう依頼したようです。
また、義稙は高国に対しても2月8日に「越水城不慮之儀無心元候。雖然諸陣堅固之由可然候。勝利被待思食候。」と、越水城の開城後もまだ勝利を期待していると激励していたのですが、前述の通り高国は2月16日に摂津で敗れて陣を退いたばかりか、池田城や伊丹城などの重要拠点も放棄し、総退却する結果となってしまったのです。
京都に戻った高国は「誘引申室町殿可落行云々、雖然室町殿無御招引」(『元長卿記』2月17日条)と将軍に共に落ち延びるよう求めたものの拒否されたらしく、将軍を三条御所に残したまま近江へと落ちて行きました。
『祐維記抄』には「十六日、酉刻、津國細川方陣破、細川方散々打死了、則細川右京大夫高国近江ヘ落行給云々、公方様ハ無殊儀京都ニ御座候也、六郎殿同三好ハ未津國在之」とあり、摂津で散々に敗れた高国は近江へと逃れたが、将軍義稙は京都に健在であること、澄元と三好之長はまだ摂津にいることが伝えられています。
幕府軍の主力たる高国勢の敗退によって追い詰められたはずの将軍義稙は、なぜ京都に残留したのでしょうか。
実は、義稙の元には澄元からの書状が届いていたようで、2月17日付で畠山式部少輔に宛てた以下のような内容が記されています。(『後法成寺関白記』2月20日条)
奉対上意連々無疎略之通、以赤松兵部令申候処、被達上聞由候条、至摂州令入国、爰元大略雖属本意候、公儀憚存不罷上候、此砌一途被仰出候者、毎事任上意可相働候、此事之次第急度御入魂憑入候、猶委曲荻野左衛門大夫可申候、恐々謹言、
澄元は以前から将軍の命令を疎かにはしないと赤松兵部少輔(義村)を通じて上申していたらしく、今度摂津を平定しても上洛しなかったのは将軍を憚ったためで、何事も将軍の命令に従うと申し出ていたというのです。
後世に編纂された軍記とはいえ『細川両家記』にも「今度公方様澄元一味にて京に御座候也」と、この動きを裏付ける記述があり、後に高国が京都を奪還して義稙は京都を出奔するという展開を知っていると尚更、義稙はすでに澄元に通じていたために、高国を見捨てて京都に残ったのだと考えてしまいそうです。
しかし、これまでの経緯と義稙の立場を考えると、この時点ではまだそのように断定はできません。
そもそも前年の末頃には六角氏に、またこのわずか10日程前にも京極氏に対して支援を要請したのは他ならぬ義稙自身でした。近江へ逃れた高国も2月22日に尼子某に対して「誠今度儀、不慮之題目、口惜候、仍至当国令下著候、此時別而中書江被加異見、入魂頼入存候」(片岡文書)と、今度の都落ちの無念を訴えるとともに、再び「中書」(佐々木中務少輔=京極高清)に協力を依頼しています。
少なくとも高国の方は、義稙の京都残留をもって自分が見捨てられたとは考えておらず、永正8年(1511)の「船岡山合戦」に至った澄元方の上洛戦の時と同様に、周辺勢力の助力を得て態勢を立て直し、再び京都奪還の機会を狙っていたのでしょう。
しかし、今回の状況が永正8年(1511)と大きく違うのは、対抗勢力の求心力の源泉であった前将軍義澄がすでに存命ではないことです。義澄の二人の遺児が赤松家と細川讃州家に庇護されていたものの、今は義稙が唯一の将軍であり、後継者として相応しい縁者もいなかったため、高国と澄元の京兆家家督を巡る争いがどう展開しようとも、血筋において義稙の立場が脅かされることはなかったのです。
(むしろ、すでに齢五十を越えていた義稙が正室すら迎えることなく、将軍家としての重責を一身に負っているというのは異例の事態で、彼は将軍家の分裂を忌避して意図的にそのような状況を保っていたと見るべきかもしれません。)
そして、高国を退けた澄元の方でも大きな問題が起きていました。
『祐維記抄』には翌3月16日の風聞として「河内高屋城落畢、御曹司、同遊佐、越智請取落シ被申訖、当國一圓ニ越智進止也、武家一向ニ不及入部者也、六郎殿ハ、去二月十六日夜尼崎舟沈テ他界云々、未諸人六郎殿ヲ見ル者一人モ無之云々」と記しており、高屋城が落城して御曹司=畠山稙長および遊佐氏から越智氏の手に渡り、大和国一円に越智氏の支配が及ぶこととなったが、武家は一向に入部に及んでいないこと、また(その理由としてでしょうか?)、六郎殿=澄元は先月の尼崎の戦いで死んだという噂があったことが分かります。
『細川両家記』が伝える2月16日の「大物北の横堤」での戦いには「その日は暮。雨もふりければ。両方互に引たり。」ともあり、澄元は悪天候の中で大物浦からの上陸戦を敢行し高国勢を撤退に追い込んだものの、実際のところ死んでいてもおかしくない事態に陥ったのかもしれません。
また『細川両家記』には「然に同二月廿七日に難波より三好筑前守之長。京へ上り給ひ。都にて威勢申計なし。」ともあり、三好之長が2月27日にはすでに難波を発って京都に入ったかのように記していますが、実際には三好之長は2月20日に大山崎に入ったもののすぐには上洛せず、ここで約1ヶ月滞在したようです。
そして同じく『細川両家記』によると、澄元は3月16日に伊丹城へ入ったようなのですが、そこから一向に動かず、3月27日に三好之長が2万に及ぶ軍勢を率いて洛中を行進した時にも姿を見せなかったため、京都の人々からこのような噂が広まっていたのです。(なお『祐維記抄』からは、澄元死去の噂は実に5月に至っても続いていたことが分かります。)
以前より澄元方と交渉していた将軍義稙が、そのような噂を知らなかった、気に掛けなかったとは思えません。
また、高屋城が落城する以前の2月29日、将軍義稙は高屋城を守り続けていた畠山次郎(稙長)に宛てて「高屋城事。于今堅固之由。尤神妙候。彌被官人等励戦功之様。可被加懇詞候也。」と、その防戦ぶりを賞賛する御内書を送っています。
この時、稙長は澄元に与する総州家とその与党・越智氏によって高屋城を攻められており、『祐維記抄』に「尾州無合力」「筒井順興モ陣立無之」とあるように、父の尾州入道(卜山)や以前より義材派=尾州派であった筒井氏からの支援も期待できない状況だったことが窺えます。
そんな苦境にあった畠山稙長を励ましている義稙が、実はそれ以前より澄元を受け入れていたというのでしょうか。だとすると、このような対応はあまりにも場当たり的で不審に感じられます。
その一方で義稙は3月3日、赤松兵部少輔(義村)に宛てて「就今度京都無事之儀。太刀一腰。西長。馬一疋鹿毛。到来。悦喜候也。」と、「京都無事」を祝って太刀や馬が贈られたことへの返礼を送っています。
前述したように、将軍義稙は赤松義村が家中に澄元派を抱えていた事情を知りながら、再三に渡り、澄元と手を切って高国と和解するよう促していたのですが、義村は再び今度の澄元方の上洛戦を支援したばかりか、恭順の意志を示す澄元を受け入れるよう義稙に申し出たのでしょう。そんな赤松義村に対するこの義稙の態度も、すなわち澄元を受け入れたことの表明にも思えます。
義稙はこのわずか数日前に、高屋城で澄元方への抗戦を続ける畠山稙長を激励したばかりで、まだ落城もしていないはず。これは一体どういうことなのでしょうか。
これまで見た状況を義稙の立場で考えてみると、近江へと逃れた高国には同行しなかったものの、畠山尾州家など従来からの支持勢力との関係は維持しようと努め、その一方で生死定かならぬ澄元方との交渉も続けつつ、情勢の把握に努めていたというのが実際のところではないでしょうか。もちろん、高国が援軍を得て戻ってくる可能性も想定しつつ、です。
幕府の主導権は京兆家が掌握しており、将軍はその傀儡に過ぎなかった……そのように捉えるならば、義稙の態度は理解できないかもしれません。
しかし、京兆家家督を巡る高国と澄元の争いに左右されることなく、自らが築いた三条御所に泰然として留まり続けることこそが、将軍として示すべき天下静謐への道だと考えていたのだとすると、あながち一貫性のない姿勢とも言えないでしょう。
細川澄元と三好之長の主従が死去し、細川高国が京都に復帰したこと
永正17年(1520)2月17日に京都を脱出して以後、大津の園城寺に滞在していたという細川高国は、各所に軍勢催促を行った結果、両佐々木氏(六角、京極)の支援を取り付けます。
諸史料に3万、4万、あるいは7万とも伝えられる大軍(この数字には高国麾下の兵と両佐々木氏からの援軍のほか、近江の朽木氏、越前の朝倉氏、美濃の土岐氏など周辺他国の兵が含まれるようです)を坂本に集結させた高国方は、5月2日から3日にかけて如意ヶ嶽など東山方面に進出、京都を制圧していた三好之長ら澄元勢を威圧しました。
『祐維記抄』には5月1日の記録として「去十六日ニ細川高国江州守山ノ八日市迄出頭」とあり、おそらく4月16日には八日市まで赴いて近江勢と合流した後、越前や美濃の諸勢も加えて坂本で陣容を整え、内藤貞正ら丹波勢とも示し合わせて反撃を開始したのでしょう。
高国方の大軍勢の様子は京都にいた公卿の日記に記されていますが、とりわけ『後法成寺関白記』5月3日条の「東西南北燧無是非、即諸軍勢如意寺峯以下所々陣取、驚目者也、及晩有時声、」という記述がよく伝わってきます。
一方、入京時には足軽を含めて2万人と伝えられた三好勢は、大軍による篝火と鬨の声に圧倒されたのか多くの脱落者を出したようで、この時点で4千、あるいは5千程にまで減っていたと伝えられています。
三好之長は5月1日、主君の澄元が京兆家家督を認められたことへの御礼のため、将軍義稙の元に出仕して礼物を贈ったばかりでしたが、そのわずか2日後にはこのような窮地に立たされることとなったのです。
『拾芥記』には「三好衆三条等持院并膏薬道場陣取之、奉頼三条之御所」とあり、之長は将軍義稙の支援を期待して三条御所に近い等持院と膏薬道場に陣取ったようですが、義稙はなぜか加勢しようとはしませんでした。
そればかりか、澄元麾下で名のある武将たちの中にも高国方へと降参する者が続出したらしく、『応仁後記』には「同四日、希雲カ一味ニ頼切タル香川安富久米川村等九頭ノ者共、敵方ヘ降参シテ弥々無勢ニナリニケリ」とあり、香川氏・安富氏・久米氏・川村氏といった名前が挙げられています。
このような状況で始まった合戦は『後法成寺関白記』には「諸陣川原江寄陣於云々、時声無是非、今日者足軽計合戦云々」(5月4日条)、また「諸陣猶東川原口江寄陣於、時声驚耳目也、今日モ川原ニテ足軽相戦云々、酉剋許諸陣所ノクト云々」(5月5日条)とあり、東山から陣を寄せた高国勢の鬨の声が聞かれるとともに、川原で足軽同士が戦う様子が見られたようですが、5月5日の夕暮れ時にはいずれも陣を退き、『実隆公記』によると「高国陣取、及昏引退、入夜三吉逐電云々」と、その夜には三好之長が行方をくらましたようです。
『祐維記抄』5月6日条は「細川高国七万騎余有之云々、吉田ニ高国ハ被取陣、諸勢ハ京中ヘ入、爰三好ガシウト界敷ハ打死ニト云々、其外高国ヘ裏帰面々十人余有之云々」と、之長を見限って高国に付いた者が十人以上いたことを報じるとともに、「六郎殿ハ未被見之、去二月十六日ニ海沈給事一定々々」と、やはり澄元が2月16日の尼崎における戦いで溺死したという噂を記しています。
以前に細川成之が高国への書状で反省したように(前編『「明応の政変」による讃州家の立場の変化と、一門の長老・細川成之の憂い』)、政元の頃から三好之長の増長を快く思わない者が多かった上に、澄元死去の噂まで流れたことで、諸将の離反に拍車が掛かったのでしょう。
『応仁後記』に挙げられているうち香川氏、安富氏などは讃岐守護代かつ京兆家譜代内衆でもある一族なので、離反するのも分からなくはありませんが、久米氏などは阿波の有力な国人であり讃州家の被官と思われます。いずれにせよ、彼らの多くは三好之長の部下ではなく、まして澄元が死去したとあれば、窮地の之長に従う義理などないという道理でしょうか。
三好之長は2人の子息(芥川二郎、三好孫四郎)や甥(三好新五郎)とともに、三条東洞院にある通玄寺塔頭・曇華院(将軍家ゆかりの尼寺で、義稙の妹である祝渓聖寿が入寺していました)に匿われていましたが、5月8日にはその噂が知られ、9日には高国に露顕して包囲されました。
祝渓聖寿は三好父子の引き渡しを拒み続けたものの、之長もついに腹をくくったものか、10日に子息両人を投降させた後、11日には自ら寺を出て、百万遍の講堂(知恩寺)にて甥の介錯により切腹するという結末を迎えたのです。(『祐維記抄』5月12日条によると、三好新五郎は之長の首を落とした後「我こそ三好が内者よ、自害これ見よ」と大音声で呼ばわり、立ったまま切腹するという勇ましい最期を見せて語り草となったようです。)
『細川両家記』には、高国は詫びを入れて降参してきた三好之長父子に対して赦免を約束したものの、之長を父(淡路守護・細川淡路守尚春)の仇と恨む細川彦四郎の訴えにより、奇しくも前年に尚春が之長によって殺害されたのと同日の5月11日に甥の新四郎ともども切腹させられ、子息の次郎・孫四郎兄弟もまた細川彦四郎から高国へ申し入れたため、翌12日に国元への手紙を書き残してそれぞれ切腹したとあり、不思議な因果を感じさせられます。(『続応仁後記』では「于時五月十一日、父子三人同日ニ滅亡ス」と更に劇的な内容に変わっていますが……甥の新五郎はどこへ……?)
余談: 今谷明先生は『戦国 三好一族』の中で、奉公衆として側に仕えていた細川彦四郎からの訴えを受けて、将軍義稙が之長と子息らの処分を決めたかのように書かれていますが、元ネタと思われる『細川両家記』には「同子息次郎孫四郎事も彦四郎殿より高国へ色々申されける。降参人いかゞと思召けれ共。さあらば生害させられよと御返事有ければ。」とあるように、高国の判断で切腹させたように読めます。
もしかすると、写本による違いや一次史料の内容と整合させた結果なのかもしれませんが、これまでの経緯を踏まえると、之長の処刑を決めたのが義稙か高国かでは大きく印象が異なりますので、ここに指摘しておきます。
このように悲劇的な最期を迎えた三好之長に対して、半井保房は『聾盲記』で「合戦ニハ三好ト申大強ノ物ナレ共、天罰ニテ如此」と辛辣な評価を下すとともに、之長を項羽に、高国を劉邦に喩えつつ「今三好ハ大悪ノ大出ナル者也、皆人々無不悦喜也」などと記しており、都の人々から忌み嫌われた三好一族の悪評ぶりが窺えます。
京都における澄元方の敗退は河内や大和での戦況にも影響したようで、『祐維記抄』によると、三好之長が逐電した翌日の5月6日には畠山総州(義英)が河内から没落し、9日には越智氏の調法により吉野まで逃れ、10日には入れ替わるように畠山尾州御曹司(稙長)とその被官の遊佐氏が河内に復帰、大和では筒井氏の軍勢によって古市氏の「山ノ城」が攻め落とされました。
そして、摂津では澄元与党が悉く退散して高国方が復帰し、畿内の治安が回復して寺社本所領も相違ないことが報じられ、大和・河内においても遊佐氏の仲介によって筒井氏と越智氏の和睦が進められたのです。
伊丹城に留まっていたという細川澄元も之長の敗報を聞いて阿波へと撤退しましたが、2月に尼崎で溺死した噂されていた澄元は、実際に容態が悪かったのでしょう。之長の死からわずか1ヶ月後となる永正17年6月10日に、32歳の若さで死去しました。
さて、細川澄元の代理として上洛した三好之長を受け入れ、「上意之趣與三好無二之御同心也云々」(『二水記』5月3日条)などと噂されていたにもかかわらず、結果的にこれを見捨て、細川高国の帰京を迎えるに至った将軍義稙は、どうなったのでしょうか。
京都に復帰した高国は5月12日には早速、将軍に対面していましたが(『実隆公記』5月12日条)、特に咎め立てたりすることはなかったようです。
前述したように、高国が京都を捨てて近江に落ちたのは両佐々木氏への援軍要請という当初の予定通りの行動であって、将軍もそれを承知で京都に残ったのであれば、帰還した高国が何事もなかったかのように面会していることも、おかしな話ではないのかもしれません。
ただ、もしそうであったとしても、将軍が一旦は澄元の京兆家家督を認めたことは事実でした。
また、義稙が三好之長を受け入れた際、公卿の中に高国への同情の声があったことは確かで、祝渓聖寿が之長父子の引き渡しを拒んだのも、掌を返すかのような兄の態度には承服できなかったためとも考えられます。
背信行為とも見られた義稙の行動を高国がどのように捉えていたのかは定かではありませんが、『祐維記抄』5月8日条は「公方様并式部少輔無殊儀者也」と、将軍が側近の畠山式部少輔ともども無事であったことと合わせて、「勢州ヨリ公方様ヘ不可有御仰天旨被申云々」と、伊勢守(伊勢貞陸)が「不可有御仰天」つまり動揺しないよう将軍に言い含めたことを伝えています。
伊勢貞陸は前将軍義澄の頃から細川高国と親しかったらしく、永正5年に高国が義澄を見限って義尹方に身を投じた時には、貞陸の口添えがあったのではないかと推測されています。(山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』)
そのような経緯があったからこそ、貞陸は今度も自分が仲介して高国に釈明することで、将軍義稙の背信とも言える行為は不問のまま落ち着くだろうと判断したのかもしれません。
あるいは、摂津で敗北した高国が一旦京都に戻った際、伊勢貞陸と高国が相諮った上での窮余の一策として、御所に留まって一旦は澄元を受け入れるよう義稙に促した可能性も考えられなくはありません。
結果的には、義稙がこの後1年も経たず京都を出奔し、高国打倒のため旧澄元派に支援を要請した一方、伊勢貞陸は高国の元に残ることになるので、彼の意図は不明と言うほか無いのですが……。
なお、『祐維記抄』には「次六郎殿ハ、去二月十六日海ヘ沈給フ、主従共以終畢」と、この段階においてもまだ澄元がすでに尼崎の戦いで溺死していたと信じられており、之長の最期をもって主従がともに滅びたこと、そして「次三好跡ヲバ、今度ウラガヘリノ面々ニ被下ト云々」と、高国によって三好氏の領地(畿内における領地でしょうか?)が寝返った者たちに下されたことなどが伝えられています。
浦上村宗と戦い続けた赤松義村を支えたものは何だったのか
一時は京都制圧に至った澄元方も今や畿内から悉く撤退してしまい、まさに永正8年の船岡山合戦の際と同様の結果に終わったわけですが、今度もまた澄元に与した赤松義村はどうなったのでしょうか。
前述した通り、宿老の浦上村宗と対立した赤松義村は永正16年(1519)末にはいったん和睦した後、翌永正17年(1520)2月末頃には将軍義稙に対して京都の無事を祝して太刀や馬を贈ったのですが、同年3月に今度は赤松家被官であった美作守護代・中村則久が義村を裏切って浦上氏に味方したことから、赤松義村と浦上村宗の戦いが再燃することになりました。
永正17年(1520)4月、討伐軍を起こした赤松義村は白旗城まで出陣し、4月20日には小寺則職を大将とする軍勢を美作に差し向けましたが、対する中村則久は要害である岩屋城に篭もって頑強に抵抗しました。
義村方による岩屋城の攻囲は二百余日に及ぶ長期戦となりましたが、その間に畿内では三好之長の敗死によって細川澄元が阿波へ退去し間もなく死没、細川高国が再び京都に復帰するという大きな戦況の変化がありました。
(なお『二水記』8月4日条からは「又近日右京大夫可遣勢於播磨国云々」と、細川高国が播磨に軍勢を派遣する計画があったことが窺え、その後の展開も考えると、これは重要な情報だと感じます。この動きに将軍義稙の思惑が絡んでいるのかどうかは分かりませんが……。)
義村が肩入れしていた澄元の敗退という時勢も影響したのでしょうか、義村方は7月8日の飯岡原の合戦に敗北し、10月3日には村宗および松田元陸の援軍が岩屋城の攻囲軍を後巻したことで形勢は逆転し、6日に義村方は数百名が討死、大将の小寺則職が自刃する程の大敗を喫してしまいました。
そして、勢い付いた村宗方は室津まで攻め上ってこれを制圧し、追い詰められた義村は永正17年(1520)11月、義母の洞松院と正室の瑞松院(まつ)、嫡子・才松丸(後の赤松政村、晴政)を守護所である置塩館から室津に移すとともに、「性因」と号して出家することとなったのです。
『赤松記』には洞松院と瑞松院は以前から村宗と同心していたともあり、それが事実だとすれば、洞松院たちは義村の敗北によってやむなく村宗の人質となったのではなく、むしろ義村を見捨てて隠居に追い込んだ側であったことになります。
併せて注目したいのは、赤松義村と浦上村宗の対立では、浦上氏の一族も決して一枚岩ではなかったことです。
浦上村宗は当初、浦上氏でも有名な則宗(則宗は村宗の大伯父に当たると伝えられています)と同じく赤松家当主の側で宿老として活動していたため、守護所である置塩館に出仕していたようで、浦上氏が実効支配を及ぼし国人を被官化していたという備前国内の統治については、守護代として村宗の弟に当たる浦上宗久が担当していました。
赤松家において浦上氏は宿老としての立場と備前国守護代としての立場の両方を任されており、当初はこれを村宗・宗久兄弟が分担していたわけですが、前述した永正16年(1519)11月の三石城攻囲戦の際、香登城主であった弟の宗久は義村に味方したようで、『宇喜多能家画像賛』には、宗久の元にいた宇喜多能家が香登城を脱出し、村宗に味方する備前西部の国人・松田元陸の援軍を募って、三石城の救援に貢献したと伝えられています。(落ち穂ひろい より 浦上宗久)
また、浦上氏の庶流と見られる有力者、浦上村国も義村に味方した一人です。
浦上村国は大永元年9月に義村が村宗によって暗殺された後も、小寺則職の後継者・村職とともに淡路に逃れ、反村宗派として活動を続けていくことになりますが、村国はかつて幼少の二郎(義村)を擁立する浦上則宗に対抗して、赤松(大河内)播磨守勝範を奉じたと伝えられているので、赤松家への忠義というよりも、元々浦上惣領家に反抗的な立場であったのかもしれません。(「嘉吉の乱」における赤松満政しかり、赤松惣領家に対する大河内家はまさにそのような立場でした。)
いずれにせよ、浦上氏が起こした「下剋上」に義村が抵抗を試みて敗れたという見方は妥当ではなく、おそらくは、畿内における澄元方の一斉敗退と澄元の死去に続き、村宗と並ぶ宿老で義村にとっては強力な味方であった小寺則職の敗死によって、赤松家における澄元派と高国派の力関係が逆転したため、洞松院は澄元派の旗頭であった義村を隠居させ、才松丸への代替わりによって家中の抗争を終わらせようと図ったのではないでしょうか。
このような経緯があり、義村(改め性因)はもはや表舞台に立つことは困難に思われましたが、決して諦めることはありませんでした。『赤松記』によると隠居の翌月の12月26日、赤松家で庇護されていた前将軍義澄の遺児・亀王丸を連れて密かに置塩館を抜け出し、明石の端谷(櫨谷)にある衣笠五郎左衛門(赤松家の年寄衆の一人)の館に入って再起を図ったのです。
義村は翌18年(1521)1月末には御着城に着陣、龍野赤松氏の赤松下野守村秀と、その下で郡代を務めていた御一家衆の広岡村宣を先陣として、広岡氏の居城・太田城まで軍を進めました。
しかし、村宗も備前三石城から室津へと進軍し、いよいよ両軍が対決となったところで、広岡村宣の裏切りによって先陣が混乱に陥ったため、義村はまたしても村宗討伐を断念せざるを得ず、2月11日の夜には亀王丸を連れて御着を脱出し、東条の玉泉寺へと逃れる結果に終わってしまいました。
義村は今度の敗戦にもなお諦めなかったらしく、義村が残した書状や禁制を見ると、永正18年(1521)1月12日時点では隠居号の「性因」と署名していたものが、2月18日、3月19日時点では「兵部少輔」と署名しており、隠居を撤回して当主復帰の意志を示していることが窺えます。
─── ここからは、これまで以上に妄想全開で仮説を展開していきますので、鵜呑みにしないようご注意ください。 ───
さて、ここまで播磨における赤松義村と浦上村宗の対立を見てきましたが、三度の敗戦を経て、養母や妻に見捨てられて嫡子も人質に取られるという危機に陥りながらも、なぜ義村はここまで執拗に戦い続けたのでしょうか。
これについては、義村には前将軍義澄の遺児・亀王丸という最後の切り札があったからだと説明されることがありますが、よく考えるとその理屈には納得できないものがあります。
後世の我々は、将軍義稙の最後の出奔と帰洛計画の失敗によって亀王丸に将軍への道が開くことを知っていればこそ、特に疑問を抱くことなくそのような解釈を受け入れてしまいがちですが、義稙が生前に後継者を定めた確かな形跡はないようです。
そして、義村が亀王丸を連れて置塩館を脱出した永正17年末頃、将軍義稙はまだ細川高国と共に京都にいたわけですから、亀王丸の立場はこれまでと何ら変わらなかったはずです。
そこで考えたのは、この頃には将軍義稙と細川高国の信頼関係はすでに破綻しており、義稙は密かに旧澄元派との提携を進めていたのではないかということです。
前述したように、将軍義稙は義村に対して再三に渡り澄元と手を切って高国と和睦するよう命じましたが、義村はおそらく永正16年末頃には逆に義稙に対して澄元を受け入れるよう働きかけ、義稙の方も永正17年2月の高国敗退によって澄元を支持せざるを得なくなったという経緯がありました。
その前提によって赤松義村を「澄元派」とみなし、義村から討伐対象とされた浦上村宗および義村を見捨てた洞松院の両者を「高国派」と仮定して説明してきたのですが、もし将軍義稙と高国の関係が破綻していたとすれば、亀王丸は高国にとっても次期将軍候補として重要な存在になっていたはずです。
だからこそ、赤松義村は次期政権において再び守護として返り咲くために、隠居を撤回して「兵部少輔」に名乗りを戻すとともに、将軍義稙の後継者として亀王丸を擁立した、というわけです。
すなわち、将軍義稙が幕政から高国を排除するために再び旧澄元派との提携を選んだことによって、赤松家における対立は洞松院と浦上村宗の「高国派」に対して、赤松義村は旧澄元派も含めて反高国で連合する「義稙派」という構図に変化するとともに、次期将軍候補である亀王丸の争奪戦が始まったのです。
突拍子もない妄想と思われるかもしれませんが、この仮説を補強する材料は他にもいくつかありますので、次項では将軍義稙が出奔に至った経緯とその後の展開を見ていきます。
将軍・足利義稙が旧澄元派を頼って細川高国を討つために京都を脱出したこと
永正17年(1520)5月に畿内から敗退した澄元に代わって高国が再び京兆家家督への復帰を果たし、政所頭人・伊勢貞陸の説得もあってか、将軍義稙と高国の関係も元の鞘に収まったかに見えました。
実際、8月22日に高国の主催によって将軍御所にて催された猿楽興行では、義稙は大いに満足した様子であったと伝えられており、両者の関係が良好であったことが窺えます。
この頃には周防在国中の大内義興からも「当年之祝儀」として「太刀一腰(國吉)、鵞眼(銭)二千疋」が贈られてきたようで、8月30日付で返礼として太刀一振を贈ったとの御内書が残されており、かつて義稙の政権を支えた後に帰国した大名たちからも、幕府は元通りに治まったと受け止められていたようです。
また、9月14日には将軍御所において今度は伊勢貞陸の主催で猿楽興行が催されており、この際には細川高国のみならず嫡子の稙国や典厩家当主の尹賢も将軍に伺候し、その翌日にも再び貞陸邸で囃物が行われて、大勢の見物衆が集まって死者を出すほどの盛り上がりを見せたらしく、高国も「大飲」つまり大いに楽しんだ様子であったとのことです。
史料からは将軍義稙と高国が対立に至るような具体的な問題は見えてきませんが、10月に入ると、旧澄元派からの離反工作があったことを臭わせる事件が起きています。
10月14日、これまで高国の麾下で働きを重ねてきた西摂随一の国人で、越水城主を務めていた河原林対馬守正頼(入道宗芸)が、「与敵通達之儀依露顕也」すなわち旧澄元派への内通を理由として、高国の命によって切腹させられたのです。
高国と正頼の両者と親交があった三条西実隆はその死に際し、歌集『再昌草』に「十月十五日河原林対馬入道宗芸生涯の事きゝて」として「洛中にことしハ種々の大はやし 河原はやしそ興ハさめけり」との歌を詠んでいます。高国の判断を暗に批判したものでしょうか。
後の大永3年(1523)正月、正頼とも親交のあった旧芥川城主・能勢因幡守頼則の追善のために実隆が主催した千句連歌には、正頼の後継者らしき「河原林対馬守」が列席、その翌4年3月には高国とともに実隆と会飲しており、更に大永6年に波多野元清と柳本賢治の兄弟が晴元方に通じて謀叛した時には、河原林対馬守が八上城の討伐軍を率いていることから、事実この時の正頼への疑いは濡れ衣であり、高国も反省してその後継者を重用したのでしょう。
しかし、正頼の一族には以前から澄元派であった者もあり(この人物については後述します)、旧澄元派としても調略しやすい立場ではありました。2月の越水城開城の経緯も合わせて考えると、疑いの目を向けられるのもやむを得なかったかもしれません。
ただ澄元の嫡子・聡明丸(後の六郎晴元)は幼く、強力な戦力であった三好一族も多くが敗死して、まだ立ち直るには早いこの時期に動く必然性は無いようにも感じますが……もし、将軍義稙の側からのアプローチがあったとするならば、話は別です。
この頃の高国は疑心暗鬼に陥っていたとか、あるいはこの事件を高国の専横化の動きと評価されることもありますが、いずれにせよ、すでに将軍義稙との仲がこじれ始めていて、実際に義稙方からの働きかけを受けた旧澄元派による調略があったとすれば、高国が判断を誤ってしまうこともあり得るのではないでしょうか。
(なお『東寺過去帳』によると、この時には河原林正頼だけではなく、利倉民部丞、中尾、稲荷出羽守、石井美作入道、その子中将が高国によって処刑されたそうです。「利倉民部丞」は山城国上久世庄の国人、「稲荷出羽守」は稲荷社の祠官・羽倉出羽守でしょうか?彼ら全てが内通を疑われたのかは分かりませんが……。)
それから5ヶ月間、将軍義稙と高国の関係が悪化した過程は明確ではありませんが、義稙は翌永正18年(1521)3月7日の夜、畠山式部少輔順光をはじめとする側近と、一部の奉行人を連れて密かに京都を出奔しました。(『二条寺主家記抜粋』では畠山順光の他に、西郡杉原四郎、下津屋修理、畠山七郎の名が見えるほか、奉行人では斎藤基躬、斎藤基雄、斎藤時基、飯尾之秀らが義稙を追って京都を離れたようです。参考:室町幕府奉行人一覧)
将軍義稙は以前、永正10年(1513)にも同じように京都を出奔する事件を起こしていましたが(中編『都を仰天させた将軍義尹の甲賀出奔と、帰洛の様子に見る幕閣の構成』)、今回はもその時と同様に御内書を残して出奔しており、その中で「世上之儀、万不応成敗候之間、令退屈、ふと思たち候」と、何事も執政が思い通りに運ばれないので嫌気が差し、思い立って出奔したと述べています。
『二水記』3月8日条には「定当時不随御成敗事等多端、此儀御退屈之故歟、又式部少輔無遠慮之所為歟、言語道断之次第也」と、執政が思い通りにならない不満のほか、畠山順光の思慮の無い振る舞いが理由に挙げられています。
これについては『二水記』4月8日条に「此次下京式部少輔家見之、内作之様美麗驚目了、但戸障子大略破取跡有之」と、順光の邸宅跡の内装が驚くほど美麗であったが戸障子はほとんど破り取られていたともあり、畠山順光は成り上がり者の寵臣と蔑まれていたものか、あまり都の公卿たちからは快く思われていなかったことが察せられます。
なお、軍記『足利季世記』では、義稙が畠山順光を贔屓するあまりに管領を与えたいと考えたため、高国との仲がこじれたという筋書きになっています。管領云々はあり得ない作り話だとしても、順光への寵愛はそれだけ多くの者が不相応に感じ、疎ましく思われてもいたということでしょう。
また、『壬生于恒記』3月8日条には「将軍御所存併悪思食右京兆故云々」と、将軍の出奔は高国への不満によるものと見られていたらしく、どうも永正10年の出奔時と同じように受け止められていた節も感じられます。
しかし、出奔後の動向を見ると、時機的には突然のことであったにせよ、今回は義稙自身が書き残したような衝動的な理由によるものではなく、最初から帰洛を前提として外部の協力者を頼っていることから、以前から進めていた計画に沿った行動の可能性が高いと考えます。
『二条寺主家記抜粋』には3月7日の出来事として「淡路ニアタ木ト云海賊ヲ御頼アリテ御座云々」と、義稙は堺を経て淡路へと逃れるにあたり、安宅水軍を頼ったと記されています。安宅氏は淡路島の海上交通の要衝であった由良を本拠地とする海賊で、永正15年に三好之長が細川淡路守尚春を討って以来、三好一族の勢力下にありました。
そして義稙は3月25日に瓦林日向守在時(国時とも)に宛てて、「就御帰洛之儀、別而致忠節者、可為神妙候也」(末吉文書)と、早くも帰洛への協力を命じる御内書を送っているのです。
この瓦林日向守は前述の河原林対馬守正頼の同族に当たりますが、正頼とは異なり永正8年の上洛戦から一貫して澄元に従ってきた一派で、この頃には澄元の嫡子・聡明丸(後の細川晴元。以下、便宜上「晴元」とします)の側近で奉行人を務めていたようです。
つまり、義稙は澄元の敗退後も交渉経路を閉ざすことなく、意地悪な言い方をすれば、以前から澄元(晴元)と高国を両天秤にかけた状態を継続していたことになります。
(後の展開も考えると、先の澄元上洛戦から引き続き、側近の畠山順光が澄元派との交渉に携わっていたのではないでしょうか。だとすると、『足利季世記』が高国と義稙の対立要因として順光の名を挙げているのも、あながち的外れではないのかもしれません。)
そして、同じく晴元を補佐していた細川澄賢(船岡山合戦で討死した典厩家の細川政賢の嫡子)は、4月3日付で大和国人の藤林勘解由左衛門尉に宛てて、以下のような軍勢催促状を出しています。
公方様至淡州被移御座、既来十六日被挙御旗、聡明殿被召具、御入洛上者、此砌可被抽忠節事専一候、於望之儀者、可申達候、恐々謹言
(漆原徹『緒方家の中世文書』より)
すなわち、出奔の翌月には早くも淡路へ移っていた義稙が「御旗」を挙げ、「聡明殿」晴元を供に引き連れて上洛する計画が立てられていたことが分かります。御旗を掲げるとはすなわち敵対者たる細川高国を幕敵とすることであり、晴元上洛の目的も当然、高国に代わって京兆家の当主となり、将軍義稙を補佐することでしょう。
藤林氏は永正8年(1511)4月27日にも上洛戦に先駆けて澄元からの軍勢催促を受けているほか、天文年間にも晴元から藤林勘解由に宛てた「今度馳加味方之由註進到来、尤以神妙之至候」との書状を受けており、一貫して澄元・晴元党であったようです。今回も晴元上洛に際して、藤林氏をはじめとする畿内の旧澄元派に号令が掛けられたものでしょう。
そして、義稙の協力者は旧澄元派だけではなく、「明応の政変」以降長年に渡って義稙を支え続けてきた畠山卜山(尚順)も加わっていました。
卜山は前年8月に領国紀伊で内衆に謀叛を起こされ、この頃にはわずかな人数で堺へ落ち延びるという危機の最中にあったのですが、『祐維記抄』には「堺迄御出アリテ、尾州ト御同心アル歟之由風聞之、淡路嶋ヘ御出ト云々」とあり、淡路へと向かった義稙がまず堺へ赴いたのも、卜山を頼ったためと見られていたことが窺えます。
(なお『祐維記抄』は卜山が紀伊を追われた件について、「尾州近年当国ヲ林堂并熊野衆以下ニ被出之、及度度寺社領押領」と、卜山が側近に登用した大和出身の国人・林堂山樹と熊野衆による興福寺・春日社領の押領を許したことを理由に「大明神御罰」と記しており、興福寺としては卜山が領国統治に失敗したのも自業自得と捉えていたようです。)
また『二条寺主家記抜粋』3月7日条には「尾州総州被迎合可有御入洛御用意云々」ともあり、これまで仇敵の関係にあった畠山卜山と畠山義英が義稙の帰洛支援のために和睦したとの噂も伝えられていたようです。
そして、5月3日に義稙の奉行人から旧澄元派の甲賀武士・佐治氏に宛てた軍勢催促状では「就高国退治、至淡州被移御座、近日御帰洛上者」(佐治文書)と、明確に高国の討伐を謳っており、これには畠山卜山が添状を認めています。
『祐維記抄』によると、卜山は5月には梶原氏と共に紀伊に帰国して広城へ入ったものの、戦いに敗れて再び淡路へと逃れたようで、以後は義稙の帰洛支援のため行動を共にすることになりました。
(なお、河内には卜山の嫡子・稙長が健在でしたが、父が義稙帰洛のために畠山義英と和睦したのに対して、稙長はその半年後には高国からの要請を受けて畠山義英と戦っており、結果的に父子は袂を分かつこととなります。)
その一方で、永正17年5月の高国復帰以来、将軍義稙と高国の間を取り持っていたはずの政所頭人・伊勢貞陸は、嫡子の貞忠とともに京都に残留したことから、義稙は高国との対立によって幕臣を十分に掌握できない事態に陥っていたとして、「義稙は高国との幕政の主導権をめぐる権力闘争に敗れた結果、出奔せざるを得なくなった」とする指摘があります。(浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』)
高国が義稙を追い詰めたと断じるには証拠不足と感じますが、ともあれ、将軍義稙は再び上洛して高国を討つ計画のもと、晴元をはじめとする旧澄元派および畠山卜山ら外部勢力を頼みとして、いわば一時避難のために、信頼できる少数の側近だけを連れて京都を脱出したと見るのが妥当ではないでしょうか。
亀王丸が次期将軍「義晴」として擁立されてなお諦めなかった赤松義村の最期(妄想注意)
ここまで、将軍義稙の出奔後の動きを見てきた中で、旧澄元派を「義稙派」と捉えるべきことには納得していただけると思いますが、これに前項で説明した亀王丸と赤松義村の動向が関わっていたのかというと……残念ながら、具体的な証拠を挙げることは困難です。
しかし、赤松義村が永正16年頃から畠山順光を取次として将軍義稙と細川澄元を結びつける役割を果たしてきたこと、義稙出奔のわずか1ヶ月前に亀王丸を連れて玉泉寺に避難しつつ、その後「兵部少輔」と名乗りを戻していることを考えると、やはり仮説として前述した通り、この時期にはすでに「義稙派」として動いていたと見る方が辻褄が合うのではないでしょうか。
そして、出奔翌月の4月にはすでに将軍義稙が細川晴元の供奉によって帰洛する計画が動いており、5月には明確に高国討伐を謳って支援を募っていたわけですが……『赤松記』によると、なぜか赤松義村はこれまで戦い続けてきた浦上村宗の申し出を信用して和睦し、4月2日には亀王丸の御供として英賀の遊清院に出た後、片島の長福寺へと移ったのです。
『伊勢貞助記』によると4月18日には高国が「若公様於御入洛」の件について協議するために、若狭守護・武田伊豆守に上洛を促しており、おそらく村宗は高国からの依頼を受けて動いたのでしょう。(伊勢家庶流と思われる貞助が承知していることから、「伊勢守」貞陸父子が関わっていた可能性も高いと考えられます。)村宗との間にどのようなやり取りがあったのかは定かではありませんが、義村はあろうことか切り札であったはずの亀王丸を引き渡してしまったのです。
その結果、7月6日には村宗の手引によって亀王丸が播磨から上洛、将軍義稙から名指しで討伐対象とされるに至っていた高国は、義稙に代わって亀王丸を擁立しました。上洛にあたって、細川右馬頭尹賢や丹波守護代・内藤備前守貞正が京都から出迎えに行ったとも伝えられています。
亀王丸入洛の様子は当時の様々な日記に記されていますが、それらの内容からは、亀王丸が近江で死去した前将軍・義澄の子息であり10歳ないし11歳とまだ少年であること、幼少期から赤松兵部少輔(義村)が養育していたこと、仮御所として岩栖院(細川満元ゆかりの寺院であり、京兆家の管理下にあったのでしょう)に入ったことなどが、広く伝わっていたことが窺えます。(『二水記』『菅別記』『拾芥記』『経尋記』など)
その様子を見物した鷲尾隆康は『二水記』7月6日条に「御輿被上簾了、御容顔美麗成」そして「不慮之御運誠以奇特也」と感想を記しており、都の人々からは好意的に受け取られていたようですが、その一方で『祐維記抄』7月条には「次アワチの公方様モ御出陣アルヘキ由其聞在之」と、淡路へ出奔中の将軍義稙が出陣してくるとの噂もあり、このままでは済まないとの不安も広がっていたようです。
─── ここから再び、妄想全開で仮説を展開していきますので、鵜呑みにしないようご注意ください。 ───
そして、亀王丸の上洛から10日後、長年亀王丸に付き従っていた側近たち数名が切腹するという不審な事件が起きました。
『二水記』7月16日条には「今度奉附若公衆五六人、於相国寺中切腹云々、造意事依露顕如此云々」とあり、何らかの企てが明らかとなったためと公表されていたようですが、鷲尾隆康は「数年令奉公、此砌生涯之条、不便之次第也」と、彼らが数年来奉公してようやく念願の帰洛が叶ったこの時に命を奪われたことに対して、同情を寄せています。
義村がこの期に及んで我が身を惜しんで亀王丸を引き渡したとは考え辛いところですし、義村が逆転を狙った最後の一手が亀王丸の上洛だったとすると、彼ら側近たちに最後の希望を託したのではと、妄想せずにはいられません。
すなわち、義村は旧澄元派による将軍義稙と晴元の上洛計画に望みをかけて、現将軍義稙と次期将軍候補たる亀王丸の帰洛を同時に実現させることを目論んでいたのではないでしょうか。
そもそも、将軍義稙自身も赤松家に庇護されている亀王丸をいずれは後継者とする腹積もりであったと考えると、義稙が永正8年の船岡山合戦の際に敵方として働いた赤松家を罰することなく、むしろ将軍家の通字「義」と「兵部少輔」の官位を与えて厚遇したことや、義稙が嫡子のいないまま正室を迎えることもしなかったことも、納得できます。
義村は元々彼自身の(あるいは赤松家臣たちの)都合で澄元支持にこだわっていたために、将軍義稙から再三求められた高国との和睦要請を無視していたわけですが、義稙と高国が決裂に至ったことでこの頃には両者の利害が一致していたのだとすると、洞松院にも見捨てられて隠居へと追い込まれた義村が、次期将軍候補となり得る亀王丸を擁立したのも、道理だと考えます。(『菅別記』7月6日条には亀王丸のことを「先年嶋御所御養子也」と記されており、この推測を裏付ける情報の一つと考えます。)
また、『二水記』6月28日条には近日の風聞として、「淡路御所今日御上洛云々、雖然雑説也、但延引云々、終以可令物忩、恐怖此事也」とあり、雑説つまり根拠のない噂話に終わったものの、亀王丸の上洛直前にも将軍義稙が帰洛するという噂で都の人々が不安になっていたことが窺えます。
しかし、旧澄元派による将軍義稙の帰洛計画は実行に移されぬまま頓挫し、義稙も8月28日付で奉行人の斎藤基躬、斎藤時基から丹波の小畠一族に宛てて「御帰洛事、既近日条、被抽忠節者、可為神妙之由」(小畠文書)と軍勢催促を行うなど、帰洛に向けた働きかけを続けていたものの、この後10月23日に再び淡路から堺へと上陸するまでの間、具体的な動きは見いだせません。
一方、上洛した亀王丸は7月26日には読書始、7月28日には将軍就任の先例に従ってまずは従五位下に叙せられるとともに、武家伝奏・広橋守光の命を受けた東坊城和長の撰により名を「義晴」と改めました。公卿では冷泉為広、三条西公條、日野内光、阿野季時、烏丸光康ら、武家からは高国とその嫡子稙国が礼参に訪れ、高国は太刀を進上しました。
(なお、義晴の名字選定については東坊城和長の案に対して内々に高国が異論を申し立て、自身の案を和長の勘文に加えさせたようです。和長によると「晴」字を上に置くのは不適切であり、義晴から一字拝領した場合に迷惑になると懸念されたものの、どうも高国が強引に押し通した模様。)
義晴の正五位下・左馬頭への叙任は11月25日、義稙の解任を伴う正式な将軍への就任は12月25日とまだ先のことになるのですが、現役の将軍である義稙が不在のまま、この段階ですでに亀王丸「義晴」の次期将軍就任はほぼ確実となったのです。
なお、将軍義稙と高国の仲を取り持っていたはずの政所頭人・伊勢貞陸は、高国による義晴の擁立を見届けた翌8月7日に死去し、嫡子の貞忠はその後、義晴に仕えました。差出人は不明ながら、7月10日付で伊勢守に宛てて「若公様御上洛、千秋萬歳目出存候、仍以誉田三郎左衛門尉御礼申上候」と、亀王丸の上洛を祝福する書状が残されており(雑々書札)、やはりその経緯には伊勢貞陸も関わっていたと推察しますが、真相は分かりません。
こうして目論見が外れた義村は、村宗の支配下にある室津で浦上被官の実佐寺氏の館に囚人のような扱いで押し込められたまま、約5ヶ月の時を過ごしました。
その間、8月22日には細川高国が進上した太刀が義晴から村宗へと下賜され、翌8月23日には幕府からの奏上により永正から「大永」と改元されました。この改元には「此間之年號雖無殊難、依将軍御他國、為奉立他主君、所用新號之由、細川右京大夫源高國申沙汰相談」(『宣胤卿記抜書』8月23日条)とあり、義稙の留守中に義晴を擁立した高国の意向によって、着々と新体制が整えられていったことが窺えます。
そして大永元年(1521)9月17日の夜、義村は村宗が送り込んだ軍勢の手によって殺害されてしまったのです。『赤松記』は義村が刺客の一人・岩井弥六の左手首を撃ち落として最後まで抵抗したこと、「是程御働比類なく候へとも、大勢不叶御果被成候」と伝えています。
なお、『播陽智恵袋』(播陽万宝智恵袋)には義村の作と伝わる歌がいくつか収録されていますが、義村が室津へ押し込められた時に「立よりて影もうつさし流てハ浮世を出る谷川の水」(たちよりてかげもうつさじ ながれては うきよをいづるたにがはのみづ)との歌を詠んで自筆の短尺を英賀城へ送り、三木東水が今も所持していると記しており、これが義村の辞世の句とされています。(「三木東水」は英賀城主・三木氏の一族で、宝暦の頃に播磨の伝説を書物にまとめた三木通識という人物のようです。参考:県史収載縁起目録)
しかし、半ば囚われの身となった義村の心境が本当に「浮世を出る谷川の水」のようであったならば、村宗の刺客に対して激しい抵抗などせず、静かに自決したのではないでしょうか……義村は将軍義稙の帰洛という逆転の可能性に賭けて最後まで諦めなかったと、そのように感じられてなりません。
また『赤松記』は義村に味方した者たちは他国へ逃れたこと、その逃亡先として「淡路其ほかおもひおもひに居られ候」と、真っ先に淡路が挙げられています。これは旧澄元派との連携を示すとともに、義村が将軍義稙の帰洛を支援すべく動いていたことの証左とも考えられるのではないでしょうか。
赤松義村と将軍義稙を繋ぐ線はおぼろげではありますが、義稙出奔から亀王丸(義晴)上洛に至るまでとその前後の動向からは、義稙が高国に代わって旧澄元派を引き入れる形で幕府を再編しようとした構想が浮かび上がってきます。
すなわち、高国に代えて幼少の晴元を新たな京兆家当主に据えるとともに、赤松義村の支援によって養子とした亀王丸を次期将軍候補に迎えることです。更にその先を読めば、讃州家にて養育されていた亀王丸の弟(後の「堺公方」義維)とも和睦して上洛させるか、あるいは後顧の憂いを断つべく、出家させることになっていたのかもしれません。
高国がどれほど幕臣や公卿たちとの間に強固な関係を築き得たとしても、次期将軍候補である亀王丸の擁立なくして天下を預かる大義はないわけで、大義がないままでは畠山稙長も父の卜山に習って総州家と和睦せざるを得なかったでしょう。
将軍義稙が高国を孤立させるためには、亀王丸を預かる赤松家の動向が極めて重要でしたが、赤松義村が軍事的にも政治的にも浦上村宗に完敗したことで、亀王丸は高国の主導によって現役の将軍が不在のまま将軍候補として擁立され、更に「大永」改元によってその代替わりが広く公知されてしまいました。そして、すでに用済みとされた義村は非業の最期を遂げてしまったのです。
(なお、浦上村宗をはじめその後の赤松家については、こちらの過去記事でも紹介しています。現在では見解が変わった部分も多々ありますが、参考まで。大河ドラマ『軍師官兵衛』以前の播磨の戦国時代あらすじ(ほぼ赤松氏の話)・続)
細川高国による新将軍の擁立が人々の支持を得た一方、高国打倒を諦めた義稙が畠山卜山とともに淡路に退去したこと
これまで見てきたように、出奔した将軍義稙が細川高国の討伐を呼びかけて自身の帰洛に協力するよう依頼していたことは明らかですが、なぜこれに応じる動きがほとんど見られず、その一方で高国に擁立された亀王丸が次期将軍として抵抗なく受け入れられたのでしょうか。
高国には目立った戦功こそありませんでしたが、右京大夫に任じられた直後の永正5年(1508)8月より犬追物の興行を復活させたほか、その後も頻繁に猿楽や連歌会を開催し、文化の興隆に力を尽くすことで都の人々の支持を集めるとともに、幕臣や在京大名とその重臣あるいは公卿たちと親しく交流し、儀礼を通じて人脈を広げる中で政治的地位を高めてきました。
高国の義父・細川政元は管領でありながら儀礼を嫌い、修験道に執心して女性を寄せ付けない等、色々な意味で協調性に欠けるところが目立ちましたが、高国はそんな政元を反面教師としたものか、対照的な資質を備えていったようです。
半井保房は『聾盲記』で三好之長の死に際し、之長を項羽、高国を劉邦に喩え、「信ニ細川高国ハ一人ヲモ不殺而大敵ヲ滅ス事ハ神変也」そして「高祖ハ有徳ノ人ナル間、天下ヲ被有也」と、高国の勝利に賛意を示しました。また、この澄元の上洛戦で義稙が之長を受け入れた際、公卿たちから高国に対する同情の声が上がっていたことも見逃せません。
高国は政元のように世評を顧みず我意を通すようなところがなく、社交性にも長けていたために、京都の人々から高く評価されたのでしょう。
そんな高国は義稙の出奔から間もない3月22日、明応9年(1500)の践祚以来すでに20年、長らく延引されてきた後柏原天皇の即位式を挙行しました。
永正16年(1519)9月のこと、天皇は義満以来の先例に従って義稙を源氏長者に就任させ即位式の催行を促し、義稙もこれに応えようとしましたが、(澄元の上洛戦に伴う混乱もあったため無理もないとは思いますが)やはり費用の徴収には難儀したようで、永正17年(1520)8月に年内の延引を申し入れたものの結局叶わないまま、出奔の前月となる永正18年(1521)2月に一万疋を進上したところでした。
京都と各地を結ぶ流通拠点である兵庫・尼崎・堺を抑えていた京兆家は、幕府以上の資金力を持っていたという話かもしれませんが、高国は不在中の将軍に代わって秩序回復に尽力する姿勢を広く都の内外に示したわけで、出奔した義稙としては幾分と間の悪いことになってしまったのです。
先に述べたように、このような将軍交代期における最大のキーマンと言ってよい「伊勢守」伊勢貞陸が、亀王丸の擁立に協力した節があることも重要です。
そして、義稙が以前から亀王丸を後継者に据えることを望んでおり、貞陸や高国ら関係者もそれを承諾していたのであれば、義稙出奔のわずか1ヶ月後に亀王丸の上洛計画が進められたのも自然な成り行きであり、高国が個人的な野心から幼少の将軍を立てようと企んだわけではないことになります。
要するに、高国が以前からその政治力を高く評価されていたことに加えて、出奔した将軍義稙に代わって後柏原天皇の即位式を挙行して世論を味方に付けたこと、更には、義稙出奔以前から、亀王丸を将軍の後継者に迎えることが幕府の既定路線であったために、結果として、高国による事実上の将軍のすげ替えが抵抗なく受け入れられたものと考えます。
三条西実隆は大永元年(1521)10月23日に義稙が帰洛を目指して再び堺に上陸した事件を報じ、『実隆公記』に「抑前将軍御出境南庄云々、大變事也」と記していますが、義晴がまだ左馬頭にも任じられていない時期であったにもかかわらず、現役の将軍であるはずの義稙のことを「前将軍」と記していることからも、その認識が窺えます。(一方で『祐維記抄』には義稙のことを「公方様」、義晴のことを「京ノ公方様」と記しており、京都と奈良では温度差があったのかもしれません。)
この大永元年(1521)10月から11月にかけて帰洛を試みた義稙の行動については『祐維記抄』が様々な風聞を伝えていますが、それによると、義稙は10月23日に再び堺へ上陸し、翌24日には「カタキ屋」に御所を移しました。畠山義英も仇敵である畠山卜山と再び和睦して大和へと軍を進めたようです。
京都の現状を知って義稙も態度を軟化させたようで「京ノ公方様ト御和談」の話も進められたのですが、条件が合意に至らなかったのでしょうか、畠山義英は兵を引くことなく大和へ侵攻し、大和の国人にもこれに与する者が現れたため、11月には幕府から畠山稙長が差し向けられ、筒井氏や越智氏と協力して大軍をもって総州勢を迎撃、これを撃退するに至りました。
(なお『祐維記抄』は、この時に稙長の父卜山は出陣していなかったことや、卜山に澄元後室への婿入りの話があったことも伝えています。卜山は稙長と対立して稙長派に追い出されたとの解釈もあるようですが、卜山はあくまで個人的な義理を貫くために義稙に追随しただけで、尾州家の更なる分裂抗争を望んだわけではなく、稙長も父の考えを汲んでいたのではないかと考えます。)
また、義稙が堺「カタキ屋」の御所を出て和泉の「カリノヲ」あるいは「マキヲ」に進出したとの風聞もあり、いよいよ京都へ攻め込んで来るかと心配されたものの、「公方様へ引及諸大名一人モ無之」と、味方する大名が一人も現れなかったためか、義稙も諦めて再び淡路へと退去したと伝えています。
高国贔屓の三条西実隆もこの顛末は予想外だったのでしょうか、『実隆公記』10月29日条に「前将軍昨日又去堺給云々、不可説々々々」と記しました。
出奔当初から義稙の帰洛を支援していたはずの晴元や讃州家が何をしていたのかは分かりませんが、おそらく軍を出さなかったのではないでしょうか。
将軍の出奔直後の状況であれば、その帰洛という大義名分によって高国を孤立させ、幕府からの排除を図ることもできましたが、高国によって擁立された義晴が将軍候補として受け入れられている状況ではそれも難しく、だからこそ義稙も和睦の道を探ろうとしたものと考えます。
すでに時代は変わってしまった、そのような空気であったからこそ、義稙の高国打倒の掛け声に応じる勢力は充分に集まらず、讃州家もこの時点での上洛計画を断念せざるを得なかったのではないでしょうか。彼らを頼って出奔した義稙としては、まさに梯子を外されることになってしまったわけです。
そもそも、永正16年から17年にかけての上洛戦敗退からもまだ満足に立ち直れていない状況で、旧領回復のために戦いは避けられない畠山総州家や旧澄元派の国人たち、そして高国打倒が叶わなければ幕府への復帰も望めない晴元の立場では、義稙と共闘することは難しかったとも考えられます。
そしてこれを最後に、義稙の帰洛に向けた活動は見えなくなり、大永元年(1521)12月25日に義晴が正式に征夷大将軍に就任、同時に義稙はこれを解任されることとなったのです。
義晴は将軍就任の前日、大勢の見物人が見守る中で仮御所の岩栖院から三条御所へと移り、高国を加冠役として元服しましたが、これに先立つ12月12日、高国は従四位下に叙されるとともに武蔵守に兼ねて任ぜられています。『菅別記』によると、この高国への叙位は三条西実隆の内奏によって実現したようです。
従四位下・武蔵守は3代将軍・足利義満に管領として仕えた頼之以来の細川家の先例であり、幼少の義満「春王丸」が元服する際に加冠役を務めたのも細川頼之でした。義晴「亀王丸」の元服年齢もほぼ同じであり、一時期ではありますが同じ赤松家に庇護されていたことも思い起こされたでしょう。
高国は義晴の将軍就任に際して、足利将軍家の全盛期を築いた初代「室町殿」義満と、自身の先祖である細川頼之の先例を強く意識していたのではないでしょうか。
長くなりましたが、こうして、高国討伐を謳って京都を出奔した義稙はこれを諦めざるを得なくなり、結果的には高国の完勝に終わってしまったのです。
旧来からの通説ではこの結果をもって、高国は幕政の壟断を目論んで義稙を追放し、幼少の義晴を傀儡将軍として迎えたという解釈がなされています。
しかし、これまで述べてきましたように、当時の史料から高国の「専横」を示す具体的な証拠を挙げることは難しく、そのような見方は結果から推測されたものに過ぎないと感じます。
いわゆる「京兆専制」論が妥当ではないことが明らかにされてきたことを踏まえても、義稙が澄元を受け入れたことで生じた信頼関係の綻びが、高国の保守政治家としての非凡な資質(あるいは人心収攬術と言い換えるべきかもしれませんが)も相まって、このような結果を招いてしまったと捉える方が適切ではないでしょうか。
義稙の遺臣たちが「堺公方」義維を擁立し、義稙の系譜が「阿波公方」家に伝承されたこと
最後に、再び淡路へ退去した義稙の結末とともに、義稙の遺臣たちによって擁立された義澄のもう一人の子息で、通説において義稙の後継者とされている義維と、その子孫が「阿波公方」と呼ばれるに至ったことについて、簡単に紹介します。
大永2年(1522)3月18日、邸主を失った前将軍義稙の三条御所を伏見宮貞敦親王が見物に訪れました。義稙は京都の人々にとってはすでに過去の人となったのでしょう。
将軍義晴が岩栖院から移ったという三条御所は、義稙邸とは別だったのでしょうか?ともあれ、義晴の三条御所も大永5年(1525)には、細川高国の意向により京兆家内衆の邸宅跡を利用して造営された新邸、柳原御所(柳の御所)に移築されることになりますので、その頃には義稙邸も無くなってしまったと思われます。
義稙に最後まで付き添った畠山卜山は翌大永2年(1522)7月17日に淡路で死去したらしく、『経尋記』8月27日条に「畠山尾州入道卜山、去月十七日逝去之由風聞、事実云々、不審也、」とあり、また『祐維記抄』8月27日条には「近般当国へ可被打入旨用意之處、萬歳也、偏神慮云々、」と、再侵攻の計画途中で死去したらしいことも伝えられています。
これがただの噂話だったのか事実なのかは分かりませんが、ともかく「明応の政変」による受難以来、ずっと自分を支え続けてくれた卜山の死には、義稙も気力を失ったのではないでしょうか。
大永元年(1521)11月に卜山とともに淡路へと退いて以後、義稙から帰洛支援を命じた御内書などは残っていないようですが、大永2年(1522)10月28日、丹波の国人・池上与四郎盛宗に対して、義稙方の奉行人(斎藤時基、斎藤基雄)から以下のような充行状が送られています。
去年至淡州被移御座處、馳参忠節、尤以神妙、因茲丹波國瓦屋南荘内成時名地頭職事、為御所御修理料由緒云々、被仰付池上與四郎盛宗訖、早全領知、任先例可被其沙汰由、所被仰下也、仍下知如件、
(『大日本史料』大永2年10月28日1条より)
池上家は将軍家に代々棟梁として仕えた室町幕府御大工の家柄らしく、この地頭職は後に「御大工棟梁」として足利義昭の新御所造営を務めたという池上五郎右衛門(『信長公記』)に継承されているそうで、与四郎盛宗もこの一族と思われます。(参考:池上五郎右衛門(いけがみ ごろうえもん)とは - コトバンク)
すでに将軍を解任された義稙からの充行状が実際に効力を持ったのかどうかは分かりませんが、自分を将軍と慕って淡路まで馳せ参じてくれたことに対して、感謝の気持ちを示したかったのでしょうか。
畠山卜山を見送った義稙はその後、阿波国撫養(現在の徳島県鳴門市)に移り、大永3年(1523)4月9日に死去したと伝えられていますが、晩年をどのように過ごしたかは明確ではありません。
おそらく『足利季世記』の「淡路ノ武島ヘ御渡海アリ」という記述からでしょうか、義稙は撫養に移るまでの数年間、淡路の沼島で過ごしたとも伝えられ、そこには義稙ゆかりと推定された庭園跡もあるようですが、これは室町期ではなく江戸初期のものであるとも言われています。
その頃にはもう義稙の消息が都で噂されることもなくなっていたようで、『公卿補任』において引き続き従二位、奨学淳和両院別当・源氏長者と記録されていた義稙の経歴に訂正が加えられたのは、死後4年を経た大永7年(1527)4月のことでした。
ちょうどその頃、高国に反乱を起こした丹波の波多野元清、柳本賢治兄弟に呼応して、細川晴元を旗頭とする阿波勢が畿内に上陸して戦いを展開していましたが、彼らは讃州家に庇護されていた義晴の弟・義維を「義稙の猶子」として擁立していたようで、この陣営にはかつて義稙とともに京都を出奔した奉行人たちや、あの畠山式部少輔順光の姿もありました。
(『二水記』によると畠山順光は大永6年(1526)12月14日に四国衆と共に堺へ上陸した後、翌大永7年(1527)1月20日に畠山上総介によって殺害されたと伝えられており、それが事実であれば同年2月の桂川合戦で義維方の優勢が決まる前に、すでに死去していたことになりますが……。)
義澄の子で義晴の異母兄弟とされる義維は、当時の史料では「南方武家」「四國若公」あるいは「堺武家」などと称されており、将軍義晴に対抗して堺に御所を構えました。そして、かつて淡路で義稙に仕えていた奉行人たちが義維の元で幕府と同じように奉行人奉書を発給していることから、これを一つの政権と捉えるとともに「堺幕府」と呼ばれることもあります。
『二水記』大永7年(1527)7月13日条は義維について「南方御事、去三月廿四日和泉堺御着岸、未及御上洛、法住院殿御息、江州武家御舎弟也、嶋御所為御猶子分歟」と伝えています。(「法住院殿」とは義澄を、「江州武家」とは大永7年(1527)2月の桂川合戦での敗北により近江へ逃れていた将軍義晴を、「嶋御所」とは説明するまでもないとは思いますが、淡路島に隠棲した義稙を指します。)
また『二水記』には、義維は初名を義賢といい、堺に入って元服するとともに、義晴と同じく東坊城和長の撰によって名を「義維」と改めたともあります。
義稙の遺臣たちを味方に付けた細川晴元は丹波勢と共闘の末、享禄4年(1531)6月4日「大物崩れ」でついに高国打倒に成功したものの、政権の内部対立によって堺の御所は崩壊、天文元年(1532)に義維は阿波への没落を余儀なくされ、更に晴元が義晴方の最有力大名・六角定頼と手を結び将軍義晴と和睦したことによって、その存在意義は全く失われてしまい、讃州家当主・細川持隆の庇護のもと阿波平島に逼塞することになります。
義維はその後も何度か上洛を試みたものの、細川晴元や細川氏綱など当時の京兆家当主、その後に畿内の覇者となった三好長慶も義維を支援することはなく、三好政権は永禄元年(1558)の末に将軍義輝と和睦して以後、幕府との協調路線を歩みました。
30年以上もの長きに渡り無念の日々を送った義維でしたが、長慶の死後に後継者の三好義継が起こした、永録9年(1566)5月19日の将軍義輝殺害事件「永録の変」の成り行きの果てに、思いがけずその大願は成就されます。
三好政権から離反した松永久秀や畠山氏をはじめ、義輝の弟・義昭(初名は義秋)を支持する勢力も畿内周辺には健在でしたが、以前から義維擁立を目論んでいた阿波三好家の宿老・篠原長房は、政変後の畿内制圧に多大な功績を上げたことから一躍、三好政権を主導する立場となり、義維の嫡子・義栄(初名は義親)を新たな将軍候補として擁立したのです。(なお、これに伴って三好宗家の当主・三好義継は松永久秀を頼って義昭方に走ることとなり、彼が起こした「永禄の変」は本末転倒な結果に終わってしまいました。)
そして永録11年(1568)2月8日、義栄は摂津富田の普賢寺で待望の征夷大将軍への就任を果たしました。その傍らに仕えていたのは、畠山式部少輔入道安枕斎守肱。父の木阿弥とともに流浪期の義稙を支え、その側近として権勢を振るった、畠山式部少輔順光の後継者でした。
しかし、義栄の時代はわずか半年で幕を閉じることになります。
永禄11年(1568)9月、織田信長の供奉によって義昭の上洛戦が展開された結果、三好政権の崩壊とともに義栄は上洛も叶わないまま若くして病死し、失意の義維は再び阿波平島へ退去、その子孫は以後も「阿波公方」と称して逼塞することとなったのです。
─── ここからは願望を交えつつ通説に逆らって蛇足を続けていきますので、ご注意ください。 ───
義稙の永正5年の将軍復帰に至るまでの動向から窺えるのは、まさしく激しい「執念」ですが、それに比べると、世間から顧みられることもなく、ひっそりと死去した最期には、あまりに静かな印象を受けます。
はたして晩年の義稙は将軍復帰の意志を持ち続けていたのだろうかと、そんな疑問が浮かんできます。
あるいは、義稙は幼い義晴が高国の元で立派に将軍職を務めていることを知り、将軍家の分裂を終わらせるためにも、これ以上は世間を騒がせるべきではないと考えて、ひっそりと隠棲していたのではないかと……。
阿波公方家が由緒として伝える義稙と義維(阿波公方の史料では「義冬」と名を改めたとされていますが、ここでは引き続き「義維」とします)の下向のいきさつは、一次史料が伝えている時代背景との齟齬が目立つことから、創作が加えられていることは明らかで、義稙と義維の関係についても確かなことは分かりません。
今のところ信頼できる史料で義維の存在が確認できるのは、大永7年3月の堺上陸以降であり、それまでの経緯を伝えているのは、後世の軍記や伝承史料だけです。つまり、淡路あるいは阿波に退いた義稙が義維を養子に迎えたという現在の通説に、確かな根拠はありません。
義稙の死後に遺臣たちが義維を奉じたことは間違いないものの、義稙本人がそれを望んだのかどうかは定かではなく、義稙が将軍復帰への執念を義維に託したという解釈も、推測に過ぎないのです。
父の義視と義政の望まぬ対立によって生まれた不幸を身をもって体感してきた義稙は、将軍家の分裂を次代に持ち越すことを望まなかったのでは……そのような考えに至った今、義稙と義維の親子関係というのは、行き場を失った義稙の遺臣たちを取り込んだ讃州家が、将軍義晴に対抗し得る正当性を喧伝するために言い出した虚言ではないか、との疑念すら抱きつつあります。
たとえば『細川三好合戦記』には「先御所義稙公阿波國ニテ御他界アリ、然シトモ三好方ノ計ヒニテ、人ニカクシケレハ、世ニ披露ハナカリケル、」とあるそうです。(『大日本史料』大永3年4月9日2条より)つまり、義稙の死が世間に知られることは、三好方(讃州家)にとって都合が悪かったのではないでしょうか。
また、これまで述べたように、義稙が義晴を養子に迎えて後継者にするべく働きかけていたことを前提とするなら、たとえ義稙が義維を「猶子」に迎えたことが事実であったとしても、それは義晴に対抗するためではなく、義維を懐柔して後に禍根を残さないためだったと考えます。
(『実隆公記』享禄2年4月8日条には、義維方が義稙の七回忌に際して仏事料を納めたとあり、義維が名実ともに義稙の猶子として振る舞っていたことは確かなようです。)
このシリーズ記事を書き始めた頃はそのタイトル通り、「流れ公方」と呼ばれた義稙の執念が義維に引き継がれた結果、「阿波公方」の伝承を生んだと考えていましたが、ここに至って当初の思惑から大きく外れてしまいました。
しかし、天下静謐に責を負う将軍家の宿命に従いつつも、先例に囚われず、乱世における将軍の在り方を模索し続けた……そんな義稙の生涯を省みると、そこに込められた意志は「執念」と呼ぶに相応しいものではなかったか、とも感じるのです。
そして義稙の遺臣たち、特に義稙の忠実な代行者で最後の側近となった畠山式部少輔順光が義維を擁立したこともまた事実であり、その後継者である畠山安枕斎が義維の上洛や義栄の将軍就任のために奔走したことも踏まえると、やはり義稙の執念が「阿波公方」を生んだと言っても良いのかもしれません。
余談: 畠山式部少輔入道安枕斎守肱について、本文では軽く触れるに留めましたが、安枕斎は義稙と畠山式部少輔順光の関係と同様に義栄の側近取次を務めており、義栄政権における重要人物の一人でした。
フロイス『日本史』第77章には「当時公方様と共に津の国越水の城に在りし、公方様の大執事アンシン」とあり、松永久秀が進めた「大ウス逐払」(『言継卿記』永録8年7月5日条)によって京都の会堂から追放されていたバードレが帰還を望んだ際、キリスト教に好意的であった篠原長房が、安枕斎にバードレを紹介したという話が書かれています。
義栄が越水城に在城していたのは永録9年9月23日の入城から同年12月7日に普門寺に移るまでの間であり、まだ将軍はもとより次期将軍たる従五位下、左馬頭への叙任も果たしていませんでしたが、フロイスは義栄のことを「公方様」と記しています。
「永録の変」で将軍義輝が殺害されて以来、将軍不在の状況が続いていましたが、松永久秀父子と対立した三好三人衆が、義栄擁立を主導する篠原長房の力を借りて摂津から京都を制圧するに及び、実質的に義栄が将軍として扱われていたことが窺えます。
(「永禄の変」については将軍・足利義輝の弑逆「永禄の変」から探る三好政権分裂の実情も合わせて読んでいただけると幸いです。)
なお、安枕斎の素性について確かなことは分かりませんが、畠山式部少輔順光とともに義稙に従って京都を出奔したとして『二条寺主家記抜粋』に挙げられている「畠山七郎」のことで、順光の子息ではないかと考えます。(畠山七郎は永正15年の順光邸への将軍御成にも同席しています。)
また、同様に名前を挙げられている、杉原四郎、下津屋修理については、おそらく「明応の政変」以来、義稙(義材)に扈従し続けた奉公衆四番衆の関係者ではないかと考えます。(参考:羽田聡『足利義材の西国廻りと吉見氏』)
下津屋修理は大永7年5月2日の足利義維奉行人(斉藤基速・斉藤誠基)連署奉書に「下津屋修理進重信」として名前が出ており、畠山順光と同じく義稙没後も義維・晴元方に加わっていたようです。(参考:日本古文書ユニオンカタログ)
義稙終焉の地・撫養にある撫養城跡を巡ってみた
義稙に執心して以来ずっと行きたかった義稙終焉の地・撫養に、ようやく訪れることができました。
以下の写真は、2017年5月の訪問時に撮影したものです。
撫養城跡とされている妙見山。地元では「妙見山公園」として親しまれてきた場所だそうです。
いつも、このお城っぽい展望台(?)が高速道路(神戸淡路鳴門自動車道)の上から見えてて、ずっと気になってたんですが……そこがあの撫養城跡だったとは。
車を止めて同行者に待ってもらってたので、急いで目の前の丘を登ったんですが……。
どこで道を誤ったのか、何だかあらぬところから侵入した感じになってしまい……。
ぐるっと回って正面へ。
元は鳥居記念博物館という施設だった(徳島市内に移転済み)名残なのか、「トリーデなると」っていう名前が付いています。
現在は展望台兼多目的ホールという位置付けの施設のようです。
鳥居記念博物館は昭和40年開館ということで、時代的にも鉄筋コンクリート製の城郭風建築あるいは模擬天守が流行していたのでしょう。
館内(城内?)では「Narustagram」という企画の展示が行われていました。
※この企画は2018年1月現在も実施されているようです。Narustagram(ナルスタグラム)【鳴門で写真動画コンテスト】|渦の国 鳴門|
妙見山のある撫養岡崎から小鳴門海峡を挟んで向かいが、土佐泊になります。撫養と土佐泊はいずれも紀伊水道と播磨灘を繋ぐ要衝であり、四国の玄関口でもありました。
土佐泊は三好氏に仕えた阿波水軍の森一族が拠点としたことでも知られており、森志摩守村春は長宗我部元親の阿波侵攻の際、秀吉の援助を受けながらここで最後まで抵抗しました。
(なお、森村春の子孫は蜂須賀氏に仕えて椿泊に移住し、代々甚五兵衛を名乗って阿波水軍を統括しました。「信長の野望201X」にも「森甚五兵衛」の名で登場していますね。)
こちらは紀伊水道のある東側の眺め。たぶん、右半分の住宅地になってるところも昔は海だったんでしょうね。
小鳴門海峡北西側の眺め。手前の破風のある建物が、史蹟・撫養城址に比定されている妙見神社です。
妙見神社。天御中主神と事代主命を祀る神社で、天保元年(1830)に、旧撫養城主・四宮加賀守の子孫である四宮三郎左衛門と、撫養林崎の豪商・近藤利兵衛氏が再建したものとのこと。
「再建」とはどういうことかというと、撫養で没したとされている義稙や義栄が妙見信仰(北辰信仰)で知られる大内氏に頼っていた過去から、守護神として受けた妙見尊星をここに勧進した、という伝承があるようです。
また、妙見山と峯続きの宝珠寺跡には「宝珠寺裏山古墳」という古代の古墳があり、これを地元では「将軍塚」と呼んでいたらしく、寛政7年に成立した撫養の地誌には以下のような記述があるとのことです。
古城山峯つゝきにして、寶珠寺てふ境内にあり、むかしより将軍塚といひ伝え、恐らくは是足利将軍義稙公の御廟所ならんか、 大永元年三月廿九日、将軍義稙公京都御退出の時、寵士村上山城守雅房・嫡子兵部義忠等、始終供奉したまふ、三年四月九日、行歳五十八歳にして、阿波国撫養において薨御し給ふと云々、
(『大日本史料』大永3年4月9日2条より)
なお、将軍塚については鳴門市の公式見解(?)が以下のブログに掲載されています。
(参考: 鳴門市への質問の返事の抜粋 ( 徳島県 ) - 瑞雲一揆 - Yahoo!ブログ)
「西光寺の墓所は、もと撫養にあったものが後世移転されたものと言われていますが、撫養の墓所自体が現在は特定できなくなっています。」とあるのも興味深い話です。
ちなみに別説として、西条益美『鳴門海峡』によれば、鳴門市鳴門町高島にある八幡神社は大正5年に近在の神社5社から合祀されたもので、その中に足利義稙を祀る社があるらしく、これは元々「武山」と呼ばれる小山にあった義稙の墓所から移されたものとする説もあるようです。
(参考:武島神社について (訂正): うるめしま)
『陰徳太平記』により流布された有名な狂歌「たぞやこの鳴門の沖に御所めくは 泊り定めぬ流れ公方か」から、大永元年11月に堺から退去した義稙の寄寓地を鳴門の「武島」(たけしま)=「高島」とする説は興味深いですね。
淡路へ退去したとされる義稙は最後に撫養で死去していることから、讃州家を頼って阿波へ向かう途中で死去したとの見方がなされることがありますが、元々鳴門の武島に寄寓していたのであれば撫養は目と鼻の先ですし、殊更に政治的な意図を汲む必要は無いのかもしれません。(『公卿補任』が大永元年12月の将軍罷免の件で「于時在四國」とするなど、一次史料でも淡路と阿波を混同しているのか、あまり区別して見てないのか……という感じもありますし。)
寛永15年(1638)に破却され、「社殿後方の城石は当時の面影を残している。」なるほど……?
玉垣に大阪市の庄野さんの名があるのが気になりますね。庄野といえば阿波篠原氏に仕えた一族ですが、撫養城で四宮氏に仕えた人もいたのでしょうか。
いますね庄野さん。こういう、城主の子孫が城跡に建てた系の神社では、奉納者の名前を逐一チェックしてしまいます。(笑)狛犬は備前焼かな?
こちらが社殿です。撫養で死去したという義稙が撫養城に滞在したのかどうかも定かではありませんが、帰路の無事とともに義稙の冥福を祈っておきました。
撫養の墓所はすでに特定できなくなっているようですし、ともかく、これで終焉の地をお参りできたということにしておきましょう。
「社殿後方の城石」というのはこの辺の石垣のことでしょうか?
最後期の撫養城の面影を残しているという、石垣群。
外側にも何かの跡が見受けられますが、よく分かりません。
むむむ……。
公園の方に出てきてしまいました。「天下泰平」「海上安全」妙見神社に事代主命が祀られたのは、港があったからなのかな?
撫養警察署の「紀元二千六百年」記念碑などもあり。
裸婦像よりも義稙像を!といった運動は起きなかったのでしょうか。今のような室町ブームの真っ只中(?)であればと思うと、誠に無念です……。
経緯は分かりませんが、公園内にはステージ観覧席のような物も用意されています。
とりあえず上ってみました。(そして、ここでタイムアップです。)
現在の撫養はこんな立地でした。JR鳴門駅が徒歩圏内にあるようなので一応、鉄道でも来ることはできそうです。(関西からだと瀬戸大橋経由でかなり西に遠回りしますが……。)
なお、記事冒頭に掲載した阿波公方家の菩提寺である西光寺には、以前、阿波公方民俗資料館と併せて訪れていたのですが、その時のことはまた別の機会に取っておきます。
参考書籍、史料、論文、Webサイト等
浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』(思文閣出版)
このシリーズ記事を書くに当たって、最も多くの気付きと学びを得られたのがこちらの論文集です。
今回の記事内容に関しては、永正17年2月17日に細川澄元から畠山式部少輔に宛てた例の書状の紹介から、将軍義稙が澄元の二度目の上洛戦以前から赤松義村を通じて澄元と交渉していたことを知ったのが一番の収穫でした。
(実は、そこからの妄想が止まらなくなってこのシリーズ記事を始めようと思ったわけですが、結果的には当初の妄想は方向性を変えて更に飛躍することになりました……。)
また、猿楽興行や大名邸御成の主客一覧からは、畠山式部少輔や浦上村宗への将軍御成がいかに異例のものであったのかがよく分かりました。これらの儀礼が行われた時期から、背景の政治的な事件との関わりを想像することもでき、とても面白いです。
義澄、義晴、義輝の元服についても京兆家による幕府儀礼の一例として取り上げられていて、元服儀礼の流れや幕政における意義についても学ぶことができ、今回の記事内容にも反映されています。
東坊城和長が義晴の名字選定に際して「晴」の字が上に来るのは不吉だと懸念を示した話もこちらからで、細川晴国、細川晴元、赤松晴政、大内晴持、陶晴賢などのことが一瞬頭を過りましたが、むしろ一生を通して吉な人の方が少数派なのでたぶん気のせい。
そして記事中でも触れましたが、将軍義稙が出奔に至ったのは細川高国との権力闘争に敗れた結果と捉えられ、その原因についてもいくつか根拠を挙げつつ考察されています。
個人的には高国が野心をもって義晴を将軍として擁立するに至ったとは考えていませんが、政元とは対照的な資質を持つ高国が様々な幕府儀礼を通じて人脈を広げ、幕政を主導する立場を獲得したことについては非常に納得するとともに、高国の見方が大きく変わりました。
今のところ、細川高国の真価に触れることができる唯一無二の一冊だと思いますので、特に以前の僕と同じように三好氏からの視点で「大内義興に便乗して権力を握った要領のいいやつ」と捉えている方には、是非ともご一読いただきたいです。
ちなみに、この本を通じて僕の高国のイメージは「調整型リーダーシップに長けた真のコミュニケーション強者」となり、コミュ障としてその資質に妬ましさを感じつつも、もしかして細川高国って理想の上司じゃね?という感想に至っています。
山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』(戎光祥出版)
足利義稙だけではなく、父の木阿弥と共に畠山式部少輔順光の活躍も多く紹介されており、このシリーズ記事を書き上げるに当たって大いに学ばせていただきました。木阿弥・順光父子の興味深い経歴はほぼこちらの内容からです。
戦国期の将軍とはどういった存在なのか、そして中央と地方の有力者の関わりも満遍なく紹介されていて、この時代の入門書にも適した内容なので、このブログで初めて「応仁の乱」からの前期戦国時代に興味を持っていただいた方にもおすすめの一冊です。
この本で「堺公方」足利義維との関係には一切触れず、義稙が後継者を定めた形跡はないと書かれていることがずっと気になっていましたが、この件は記事でも述べた通り、近世の阿波公方側の伝承や軍記など良質とは言えない史料だけが伝えているためと判断しました。
そして、晴元を頼った義稙の遺臣たちが義維を後継者と称しただけなのかも知れない、との疑いを持つに至ったわけですが……どうでしょうか。
今谷明『戦国 三好一族』(洋泉社)
細川氏と三好氏を中心に畿内の情勢を把握する上で、常々参考にしているものです。今回は特に澄元方上洛戦の経緯と三好之長の動向について参考にしました。
義稙後期の幕府を「京兆専制」の枠で捉えられている点など、義稙贔屓となった今では支持できない部分もありますが、この本で「堺公方」の存在を知ったことは今回の記事の原点と言えます。
この本にある「澄元が義維を播磨から阿波へ拉致」という記述がずっと気になっているのですが、今のところその根拠と思われる情報を見つけることができていません。もし心当たりのある方がいらっしゃったら、ご教示いただけると嬉しいです。
清水克行・榎原雅治(編)『室町幕府将軍列伝』(戎光祥出版)
室町幕府の歴代将軍に関して、各担当の研究者がそれぞれ様々な視点で語られていますが、義視や義維といった将軍には就任せずとも政局に影響を与えた兄弟をについても「コラム」という形で書かれており、とても読み応えのある一冊です。
このシリーズ記事に関連する部分の担当者は、義稙・義維…木下昌規、義澄…浜口誠至、義晴…西島太郎、義栄…天野忠幸、となっていますが、各先生方のこれまでの研究分野と被る部分がありつつ、ちょうど将軍家の分裂期で時代が重なっていることもあり、同じ事件でも捉え方の違いが見られて面白いです。
今回の記事に関連するところでは、室町幕府における足利将軍家とはどういう存在なのか、そして義稙が二度将軍に就任した状況や前後の経緯について改めて確認し、義稙が将軍家の分裂問題にどう対処しようとしたのかを考えるヒントを得られたように感じます。
木下先生の義維のコラムは、現時点での研究成果の状況が分かりやすくまとめられていて、参考になりました。(なお、その中でも「堺幕府」の呼称については不適切と断じられていました。)
ただ期待していた、義維が讃州家に庇護された経緯と、義稙との猶子あるいは養子関係の究明については、残念ながら未解決のままとなりました。
渡邊大門『備前 浦上氏』(戎光祥出版)
赤松氏の内情や浦上村宗に関する概略は、この本を参考にしています。
ただし、兵庫県史等でも言及されている赤松氏の動向と畿内政権との関連には触れられておらず、おそらく意図的に避けているような印象を受け、その点は浜口先生の論調とは対照的に感じます。
播磨学研究所・編『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)
- 小林基信『浦上則宗・村宗と守護赤松氏』
- 依藤保『晴政と置塩山城』

- 作者:
- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター
- 発売日: 2011/06/01
- メディア: 単行本
赤松義村と洞松院に関することは、こちらも併せて参照しています。
一般に義村は浦上氏の「下克上」を許したとされ後世の評価は低いのですが、再評価して欲しいと思うきっかけを得た本でもあります。
義村と村宗の関係には、政則・則宗主従とはまた違った面白さを感じるので、もっと世間で流行って欲しいのですが……。
大石泰史編『全国国衆ガイド 戦国の "地元の殿様" たち』(講談社)

全国国衆ガイド 戦国の‘‘地元の殿様’’たち (星海社新書)
- 作者:
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2015/08/26
- メディア: 新書
複数の執筆者で書かれている本ですが、特に畿内の国人については澄元(晴元)派 or 高国(氏綱)派、あるいは一族がそれぞれに分裂していたのか、といった点に触れていることが多いので、「両細川の乱」における京兆家内衆の動向を把握する上で参考になります。
ちなみに、畿内地域の担当は『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』の浜口誠至氏です。
この本では「丹波荻野氏」の紹介で、細川澄元から畠山式部少輔に宛てた件の書状を届けたと思われる「荻野左衛門大夫」は澄元の側近で、澄元派と高国派に分裂していた荻野氏の一族と説明されていました。
その通りだとすると、京兆家麾下の国人の中には摂津や和泉だけではなく丹波でも澄元に味方して阿波まで没落した者がいたわけで、興味深い話です。
若松和三郎『戦国三好氏と篠原長房』(戎光祥出版)
「永禄の変」後の三好政権分裂騒動における篠原長房の活躍および、当時の畠山式部少輔入道安枕斎守肱の活動については、この本から学びました。
現在の篠原長房への評価は『昔阿波物語』などの軍記に引きずられているようで、それすらも一般にはまだまだ知られていない状況ですが、長房が阿波三好家を代表して義栄を擁立するに至った経緯など、今後の研究の進展によってその評価も変わってくるんじゃないでしょうか。
特に昨今「忠臣説」が話題になっている松永久秀との対比という点でも(義輝と久秀、義栄と長房、キリスト教への姿勢など)、ぜひ多くの方に注目していただきたいです。
(長房は背が高いとか、宣教師のマントを褒めたという話もあるので、『昔阿波物語』ベースのTVドラマでもやって、背の高い俳優さんが一般イメージの信長ばりに黒マント着用で長房の最期を演じてくれたら、間違いなく人気出るんじゃないかと思ってるのですが……。)
あと、「秋山家文書」所収の永正18年9月13日付連署奉書で篠原左京進之良と瓦林日向守が連署していることに気付き、これまで高国派とされてきた瓦林日向守が義稙から御内書を受け取っていることとの矛盾に不審を感じるに至ったのは、この本に連署奉書の内容が掲載されていたおかげです。(後述しますが、この件については馬部隆弘先生が解明されています。)
那賀川町史編さん室『平島公方史料集』
阿南市立阿波公方・民俗資料館にて購入したものです。
「平嶋記」などの阿波公方側の伝承史料のほか、義稙および義維(阿波公方側では義冬とされる)の動向を確認できる史料の抜粋が翻刻文で掲載されており、今回の記事でも参考としました。
阿波公方側の伝承史料は、他の史料の内容とは辻褄が合わないところや明確な誤りも多く、鵜呑みには出来ないのですが、積もり積もった蜂須賀家への不満を爆発させて京都へ移住したという阿波公方9代・足利義根が、祖先の事跡をまとめるに当たって誤りを訂正した形跡なども窺え、面白いです。
なお、義稙の死後、大内義隆が三条西実隆に尋ねてその肖像画を制作した件をこの本で知って以来、大内義興が義稙と仲違いして帰国したとか、見捨てたというのは当たらないのではないかと考えるようになりました。
京都府教育委員会『京都府中世城館跡調査報告書 第3冊(山城編1)』『第4冊(山城編2)』
史跡探索の助けになればと、たまたま地元近くの図書館で読んでみたものですが、1107年から1600年台に至るまでの軍記を含む文献史料に登場する城館や邸宅、寺の名前と史料名と年月日、翻刻文の簡潔な引用が掲載されており、思いがけず本記事の役に立ちました。
特に永正17年5月の「等持院合戦」前後の動向に関して、『後法成寺関白記』『実隆公記』『拾芥記』『元長卿記』といった当時の日記の記述内容と、『応仁後記』『続応仁後記』『足利季世記』といった軍記の記述内容を比較して読むことができました。
調査の手は絵画資料の書き込み内容にまで及んでおり、参考資料を広げる索引としても役立ちそうです。
兵庫県史編集専門委員会『兵庫県史 通史編 第三巻』
昭和53年と若干古い本ですが、いわゆる両細川の乱についてまとまった内容があります。本記事に関連する部分の執筆は石田善人先生、Wikipediaによると神戸出身の歴史学者で中世惣村の研究で有名な方のようです。
永正16年秋からの澄元方上洛戦の経緯についても、兵庫県にゆかりの深い赤松氏や瓦林氏が関わった関係から、一般向けの新書などよりもかなり詳細に記されています。
赤松義村は洞松院と高国の和議に反して終始、澄元派であったとして、赤松家中の対立が中央の政権争奪に関わっていたという視点もあり、案外古くからそのような見方をされていたという事実も興味深いです。
亀王丸の上洛に付き従った側近たちが相国寺で切腹した事件への「原因は赤松義村と浦上村宗の対立抗争」という指摘に妄想を掻き立てられたことも、今回の記事内容に大きく影響しました。
西宮市史編集委員会『西宮市史 第一巻』『第四巻 資料編1』
こちらも昭和34年と更に古い本ですが、地元だけあって特に河原林(瓦林)氏に関する貴重な資料や考察がまとまっています。おそらく本記事に関連する部分の執筆は永島福太郎先生です。(現在、呉座勇一先生の新書『応仁の乱』が大人気ですが、そのずっと前に同タイトルの新書を出された方です。僕はまだ入手できていませんが……。)
資料編には当時の史料から河原林(瓦林)氏が登場する部分の引用が多数掲載されており、特に直接読むのは難しい一次史料に関しては今回の記事でも参考にしました。
国書刊行会編『続々群書類従 第三 史伝部2』(続群書類従完成会)
『祐維記抄』を含む『続南行雑録』が収録されています。
この記事の中に『祐維記抄』と多く記載しているように、永正16年から17年にかけての澄元方の上洛戦に関する情報や、将軍義稙の出奔後の動向、また両畠山家の動向については一貫して詳しく記されており、参考になります。
オンデマンド版を発行している八木書店によると、『続南行雑録』は「水戸の儒臣佐々宗淳が元禄年間に奈良で採訪した春日若宮社司家代々の記録と寺社の由緒故事」というもので、おそらく興福寺の情報網によってもたらされた伝聞を多く含んでいるのでしょう。
赤沢朝経(澤蔵軒宗益)・長経父子の後継者と思われる「赤澤新兵衛」がたびたび登場しており、彼らにとって「赤澤」の名は災厄の象徴として記憶に刻まれていたことなども窺えて、興味深いです。
塙保己一編『続群書類従 第二十三輯下 武家部』(続群書類従完成会)
幕府の年中行事や将軍御成の記録、武家故実を主としている武家部ですが、この中に義稙期のものを含む『御内書案』が収録されています。
この記事中に「御内書」と書いている部分は、ここから読み取ったものです。(こんな良い史料が近くの図書館で読めたのに、割と最近まで気付いていませんでした……。)
嬉しいことに「国立国会図書館デジタルコレクション」でも読めます。永正16年はこのページ辺りから。続群書類従. 第23輯ノ下 武家部
塙保己一編『群書類従 第二十一輯 合戦部』(続群書類従完成会)
赤松家に仕えていた得平定阿の筆による『赤松記』が収録されています。
ジャンル的には軍記に分類されていますが、創作というよりも覚書的な要素が強い内容のため、参考史料として扱われることが多いようです。
赤松義村が永正16年末に亀王丸を伴って脱出して以後の動向については、この記事ではほぼこちらの内容に従っています。(得平定阿が仕えていたのは義村の後継者・赤松晴政とその子義祐なので、当事者による情報ではありませんが)
なお『赤松記』は「国立国会図書館デジタルコレクション」でも一応読めますが、活字ではないので僕には厳しかったです……。群書類従. 第453-498冊(巻369-399 合戦部)
高橋遼「戦国期大和国における松永久秀の正当性─ 興福寺との関係を中心に─」
畠山式部少輔順光が獲得しようとした「官府衆徒」とは何ぞや?という疑問から、こちらの論文に学びました。
三好政権における松永久秀と併せて、細川晴元期の木沢長政についても解説されていますので、そちらに興味のある方にも参考になるかと思います。
西原正洋「永正の錯乱以降における細川氏の本庶関係―典厩家を軸として―」
細川京兆家が澄元派と高国派に分裂したことで、細川一門の「同族連合体制」が変質していった過程を、典厩家を中心として庶流家の視点から説いた論文です。
特に一貫して澄元派であった政賢の嫡子・澄賢が、阿波へ逼塞してからも旧来の家格を認められて、幼い晴元を補佐する地位にあったことを学びました。
三好長慶が細川氏綱派に離反して以降は氏綱の弟にあたる藤賢が復権を果たし、織田信長の供奉による足利義昭上洛後は京兆家からも独立して、御供衆の筆頭というべき地位を利用して存続を図っていたという点も、興味深いです。
馬部隆弘『細川晴元の取次と内衆の対立構造』ヒストリア 258号 (2016.10)
細川京兆家、とりわけ高国、晴国、氏綱、国慶といった高国党の希少な研究成果を発表されている点で個人的に注目している、馬部隆弘先生の論文です。
論文の本題は晴元の取次と内衆の世代間対立についての考察ですが、思いがけず瓦林日向守の経歴について知ることができました。
これまで「細川高国在京奉行人連署奉書」として紹介されてきた史料、永正18年9月13日の瓦林日向守、湯浅弾正忠、篠原左京進による連署状が、阿波に在国していた細川六郎(晴元)周辺から出されたものという説明は納得できるものです。
三者の経歴および、こちらの某年6月23日付の瓦林日向守、湯浅弾正忠、古津修理進から秋山幸久に宛てた連署状の内容から明らかにされています。秋山家文書 文化遺産オンライン
これによって、これまで『細川両家記』等の記述から高国派と見られていた瓦林日向守が、将軍義稙から帰洛支援を求める御内書を受け取っていることの矛盾や、明らかに讃州家の被官と思われる篠原左京進之良がなぜ「高国在京奉行人」とされているのかという疑問が一度に氷解するとともに、義稙の最後の出奔は旧澄元派と示し合わせた計画的なものであったと判断するに至りました。
その点、今回の記事を書くに当たって、この論文から得られたものはとても大きかったです。普段はなかなか大学図書館などを利用できる機会がなく、論文についてはWebで公開されている数少ないものだけが頼りなのですが、偶然が重なってこれを読むことができたのは本当に幸運でした。
落ち穂ひろい
赤松・浦上・宇喜多関連で、手元の資料にない情報で気になることがあれば、真っ先に確認させていただいているサイトです。
特に永正16年から18年の赤松義村と浦上村宗の対立について、以下のページを参考にさせていただきました。
また、「御一家衆」と呼ばれる庶流家や「年寄衆」と呼ばれる宿老など赤松家の事情については、こちらの 赤松氏の家臣団構成 からも学ばせていただきました。
やまんなか: 亀王丸と義村
赤松義村のことをWebで調べていて、一番印象に残っている記事です。(初見は旧サイトで3つの記事に分かれていましたが、移転の際に統合されたようです。)
義村というと浦上村宗との対立関係ばかりが採り上げられますが、幼少の亀王丸(義晴)にとっては置塩館で共に過ごした義村との思い出もあるはずで、義村殺害の首謀者たる村宗への将軍御成が高国邸で催された時、義晴は何を思ったのでしょうか。そして「大物崩れ」で村宗や高国が死んだ時は……この記事の視点からは、そのような事に思いを馳せざるを得ませんでした。
二周年です(…のおまけ): Muromachi通り
中編でも参考記事として挙げさせていただきましたが、今回は義稙出奔を巡る畠山尚順の動向やその解釈について多くを学びました。
以前は知識不足のため理解できないところが多かったこちらの記事も、実際に『続南行雑録』の『祐維記抄』を読み進めた後、改めて記事を読み直すと、その解釈には納得できる部分が多かったです。
特に、大永元年10月から11月にかけての帰洛計画を最後に、義稙と尚順はともに淡路で静かに隠棲したという見方については、こちらの記事というか管理人さんから全面的に影響を受けたものと言って良いです。
室町幕府奉行人一覧
中世公家日記研究会を紹介されているサイト『中世史の部屋』内のコンテンツですが、文明元年から天文23年までの幕府関係の引付史料に登場する奉行人を年次でリスト化されています。
前年に奉行人として見えない者、翌年から奉行人として見えなくなる者、前年・翌年ともに奉行人として見えない者を色分けして記載されているため、特に永正5年(1508)の義稙帰洛に伴う政権交代が目に見えて分かるようで興味深いです。
幕府分裂期の明応3年から永正8年、大永元年、大永6年から天文元年には非主流派の奉行人として「足利義稙・義澄右筆方奉行人」や「足利義維右筆方奉行人」が別枠で掲載されており、参考になります。
東京大学史料編纂所データベース
特に『大日本史料』の綱文・書名・本文・索引語から人名や出来事を検索できる「大日本史料総合データベース」が非常に有用です。
素人が直接確認することが難しい史料からの翻刻・引用文も多数収録されています。綱文については今では解釈が誤っている部分も見受けられますし、新出の史料をフォローできていない部分もあるでしょうけど、調査の取っ掛かりとしては十分でしょう。
今回の記事では執筆終盤にこのサービスを知ったため、内容への反映は主に「将軍・足利義稙が旧澄元派を頼って細川高国を討つために京都を脱出したこと」以降で、それ以前は数ヶ所を手直しするに留まっています。(見直し出すとキリが無さそうで……すみません。)
いやはや、こんな便利なサービスの存在を今まで知らなかったとは……たぶん基本レベルですよね、これ。
なお、『塵塚物語』の義稙に関する記事「恵林院殿御事」も、このデータベース経由で知りました。義稙に興味を持った方はぜひご一読ください。
(『大日本史料』では有名人の逝去日付の記事において、関連する花押や系図あるいは様々な伝承が掲載されていて、参考になります。義稙の養子・猶子関連の記述も充実しており興味深いです。)
その他
今回の記事執筆は約1年半と非常に長期間に渡ったのですが、調査と執筆を繰り返す中で閃いたり疑問に感じたことを、Twitterで呟いたりしました。その中で賛意や補足情報などいくつかの反応をいただくことがあり、より考察を深めたり整理することができました。
具体的にどの方のどのツイートと挙げることは難しいですが、Twitterで反応をくださった皆様には感謝いたします。
同シリーズ記事
讃岐香西氏と大内堂の縁起が伝える大内義興の永正17年幻の上洛
今回は京兆家内衆としても知られる讃岐香西氏の名字の地・高松市香西町にあります、「大内堂」(大内義興報恩堂)を紹介します。
この大内堂の興味深い縁起について考察するとともに、讃岐香西氏の略歴をまとめました。
また併せて、香西で訪れた史跡もいくつか紹介します。
なお、前回の記事 『「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(中編)将軍義尹の甲賀出奔事件の背景』 の続きになる大内義興の帰国後の話や、逆に前回取り上げた丹波の内藤氏以前に香西氏が丹波守護代を務めたという話にも触れていますので、合わせて読んでいただけると幸いです。
香西氏が築いた山城・勝賀城跡のある勝賀山。香西氏が平時の本拠地とした、佐料城跡付近から。(高松市鬼無町佐料)
『香西記』が伝える大内堂(大内義興報恩堂)と大内神社
大正15年に改修されたという大内堂は、勝賀山から少し北東にある小さな山、薬師山の麓にあります。(高松市鬼無町是竹)
案内板の説明文には、大内義興の供奉により足利義尹が将軍に復帰して以来、香西元定は大内氏に従って交易の利益を得たため、義興の死後その恩義に報いるために建立したものとあります。
大内堂の裏には「大内神社」と書かれた小祠がありました。それぞれの関係はよく分かりませんが…。
地元の伝承を集めた史料『香西記』は藤尾八幡宮の祠官・新居香流軒直矩が寛政4年(1792)に完成させたといい、その前書きには「嘗流聞香西の昔語書捨たるを拾ひ集て、童蒙の夜話ともなさんと、是を俗編せんと欲す…」とあります。
その『香西記』には大内堂について、以下のように記述されています。
所謂勝賀山の東麓に小山あり。是竹邑に一峰を生す。故是竹山と云。或は常世山と云也。又常山と云。(中略) 香西豊前入道宗玄、是竹山の原に一宇の禅林に建て、常世山宗玄寺と號。今寺迹に小庵有。又此東南の原に三位義興の像を造立して一宇を立、大内堂と云。又號大内寺也。退轉して今はなし。鎮守荒神の小祠有。此邊を大内堂と地名に稱す。大内寺本尊の觀音、今は西光寺内佛に有と云々。此大内堂東隣作山城跡なり。
香西豊前入道宗玄は是竹山、あるいは常世(とこよ)山、また常(じょう)山と呼ばれた山の原に、常世山宗玄寺を建てるとともに、この東南の原に大内義興の像を造立して「大内堂」あるいは「大内寺」と呼ばれる寺を建てた。今は寺はなくなったが鎮守荒神の小祠があり、その辺りの地名は「大内堂」と呼ばれている。
大内寺の本尊であった観音像は、今は西光寺の私房に置かれているという。この大内堂の東隣が作山城跡である。
…大体の意味はこんな感じでしょうか。
是竹山は現在「薬師山」と呼ばれており、その名の由来であろう薬師寺が建っています。天台宗根香寺末寺とのこと。
香西記の記述では大内堂の東隣が作山城跡とありますが、こちらの薬師寺も城っぽい外観ですね。
勝賀山一帯にはみかん畑がとても多いのですが、大内堂の背後に当たる薬師山にもみかん畑があるようで、農業用モノレールの線路らしきものが伸びていました。
『南海通記』が伝える永正17年秋の大内義興上洛と、将軍義稙の動き
さて、『香西記』は香西豊前守元定の項においても、大内堂のことをこのように記しています。
香西豊前守元定、永正五年八月二千五百餘兵を引率して山田郡に責入て、三谷兵庫頭景久と王佐山の城に相戰也。永正十六年大宰大弐政賢と大内義興筑前に對陣の時、大内方として兵士を引率し、長州赤間か關に到る。爰に大友氏和平を乞。故に兵を引て國に歸也。永正十七年大内義興卒去。彼像を造て以一宇を建て、大内堂又大内寺と號也。
香西元定の事跡について淡々と記述していますが(永正十六年「大宰大弐政賢」って誰のことでしょうか?)、「永正十七年大内義興卒去」を機会として大内義興像を造立したと伝えている点に注目です。
つまり、大内義興は永正17年(1520)に死去したというのですが、通説では享禄元年(1528)とされており、実に8年もの開きがあります。
いったいどういう事なんでしょうか?
讃岐香西出身の兵法家・香西成資が、寛文3年(1663)に書き上げた『南海治乱記』を元に増補を重ねた末、享保3年(1719)に完成させたという軍記『南海通記』には、「讃州香西氏建大内堂記」との章立てで大内堂の縁起が紹介され、その中に永正17年とされる大内義興の最期が書かれています。
永正十七年秋大内義興上洛ノ費用ヲ調ヘ、二万餘兵ヲ擧テ泉州堺ノ浦ニ到著ス。大兵海濱ニ上リケレハ廣津モ猶狭迫ナリ。義興ハ翠簾屋ト云町人ノ宅ヲ本陣トシテ夜守厳格ノ備ヲナシ、警衛■モ無リシカ何トカ為タリケン、館中ニ■盗アツテ諸人寝定リテ後義興ヲ害ス何者ノ所行ト云コト知レス翌日大内家ノ老臣密談シ是ヲ露顕セス、義興ハ防州ニ在テ病ニカゝリタル由、到来スト披露シテ兵船ニテ漕還ス。将軍家モ義興上洛ナキニ因テ、洛中ニ止リ玉フコト成玉ハスシテ淡州ニ退キ蟄居シ玉フ、義興卒去ノコト匿スト云ヘトモ世上普ク推量シテ力ヲ落ス者多シ、今天下ニ将軍ナシ管領ナシ天下ヲ得ント欲スル志アラハ即時ニ天下ヲ得ヘキ時ナレトモ其器ニ當ル人ナクシテ過ヌ、近世兵革打ツゝキテ静マルコトナケレハ百姓モ農ノ時ヲ失ヒ國民困窮ス。
(一部、私の拙い漢字力では読み取れなかった箇所を「■」としています…。)
永正17年(1520)秋、上洛の費用を調えて二万余の兵を率いて堺に到着した大内義興は翠簾屋という町人の家に陣を張ったものの、盗賊によって殺害されたというのです。
また、老臣達が義興の死を秘匿し、防州で病に罹ったと称して上洛を中断したため、義興の支援を受けられなくなった将軍義稙は京都から淡路に退いて蟄居したとします。
※ここからかなり妄想入りますので要注意
永正17年といえば、管領細川高国に対抗する細川澄元が阿波勢を率いて前年の秋から上洛戦を展開、摂津方面で高国方を撃破した三好之長が2月に京都へ入り将軍義稙を奉じたものの、5月には六角氏の支援を受けた高国方の反撃を受けて等持院合戦に敗れ、6月には澄元が病死したため上洛戦は失敗、そんな激動の年です。
この時、近江へ脱出する高国が将軍義稙を連れ出そうとするも、義稙は拒否して在京し続けたことから、土壇場の決断で高国を見捨てて澄元との提携を選んだと解されています。
しかし、義稙は以前から赤松義村を仲介して澄元との交渉を継続していたようで(浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』)、そう考えると将軍の判断は唐突なものではなく、計画的に高国の排除が進められていた可能性があります。
いずれにせよ、その目論見は三好之長と肝心の澄元の死去によって崩れてしまったのですが、その後も赤松義村は亀王丸(後の将軍義晴)を奉じつつ、領国播磨・備前・美作において高国に与する浦上村宗との戦闘を繰り返していることや、ちょうどこの頃に国人達の謀反によって領国紀伊を追われた畠山卜山が、翌大永元年(1521)3月の義稙の京都出奔に呼応していることを合わせると、その背後には反高国方の核として将軍義稙と亀王丸の存在があったのかもしれません。
そうすると、この『南海通記』が伝える永正17年秋の大内氏上洛は、すでに2年前に帰国していた大内義興が再び義稙の呼び掛けに応じたものと捉えることができるわけです。
また『南海通記』はこれに続き、大内義興に大恩のある香西氏が義興の死後にその霊像を祀ったものが「大内堂」であると記しています。
讃州ノ諸将細川政元卒去ノ後、大内義興ニ服従シテ國ヲ守リ、地ヲ保テ数年ヲ超タリ、殊ニ将軍ヨリ安富山城守、香西豊前守海上ノ警衛ヲ奉テ廻船ノ非常ヲ制ス、故ニ上京セスシテ兵衆ノ煩勞ナシ、且能島兵部大夫ニ属シテ大内家朝鮮ノ役ニ加シカバ財足民饒ニシテ兵力有餘ス。是義興ノ芳恩ニアリトテ香西氏ノ産神藤尾八幡宮ノ向ノ山ニ堂ヲ立テ義興ノ霊像ヲ安置シテ、是ヲ祭ル是ヲ大内堂ト云フ世ハ變リ行ケトモ其林木ト名バカリハ今ニ存セリ。
ここでは細川政元の死後、讃岐の諸将は大内義興に従って領国を守り、安富山城守と香西豊前守は将軍から海上警護の役目を命じられたため、上京して兵を損ねることはなかったとしています。また、能島兵部大夫に属して大内家の「朝鮮ノ役」に加わったため「財足民饒」ともあります。
このように香西氏が兵を損ねず財産を得られたのも、亡くなった大内義興の恩に依るものだとして、氏神である藤尾八幡宮の向かいの山に堂を建てて義興の霊像を祀り、「大内堂」と呼んだとのことです。
なお「朝鮮ノ役」は日明貿易とする解釈と、いわゆる倭寇とする解釈に分かれるようですが、当時の海賊の実態としてはどちらも大差なしという感じはします。
能島兵部大夫が一般に「海賊大名」として知られる村上三家の一つ能島村上氏だとすると、大内義興が前将軍義尹を奉じて上洛した際、能島村上氏はこれに協力して塩飽島の代官職を与えられたと伝えられており、当時大内氏に従っていたと思われる香西氏も、能島村上氏の麾下で遣明船の警護を担って利益を得たのかもしれません。
一方の安富山城守は「細川四天王」として知られる安富盛長が名乗った官途ですが、京兆家内衆としての安富氏が細川澄之の乱で没落した後、讃岐に残った安富氏が名乗ったものでしょうか?
安富氏は讃岐東守護代として塩飽島に代官を置いていたそうですし、香西氏と同じく麾下に海賊衆を持っていたのかもしれません。
また『南海通記』は、義興の死去は秘匿されたため世間ではこれを知られることなかったとし、子の義隆は幼少ながら父の遺跡を継いで大国を多数領し、富貴かつ安逸であったため天下の政事は山口に移って大勢の者が集まり、外国の商船も博多や山口を訪れて、明国との勘合も政弘以来大内家が独占したため、外国人は義隆を日本の国王と思っていたと、その治世を好意的に記しています。
義興卒去ノコト深ク密シテ世ニ露ハサズ、故ニ世人ソノ所以ヲ知ス其子義隆幼少ニシテ、父ニ後レ其遺跡ヲ繼テ大國數多ヲ領シ、富貴ニシテ安佚ナリシカハ天下ノ政事ハ防州山口ニ移リ、貴賤トナクコゝニ来集シ、西蕃ノ商船モ筑前博多、防州山口ニ来著シテ、和漢ノ勘合モ政弘ヨリ以来ハ大内家ヨリ通達セシカハ異邦人ハ大内殿ヲ以テ日本國王ト思ヘリ、大永元年ヨリ三十年ニ及テ義隆大國ヲ塞テ終ニ上洛シ玉ハス。
さすがに8年も当主の死を秘匿するのは難しいと思いますが、幼少で父の跡を継いだという義隆は実際に永正17年までに元服して周防介を継いでおり、すでに代替わりしていたようです。
大内義興が帰国した後も将軍義稙との繋がりを断っておらず、澄元の反攻に呼応すべく動いていたのだとすると、遣明船の利権を巡って大永3年4月「寧波の乱」で大内方と細川方が武力衝突に至った件、阿波守護家の細川持隆が大内義興の娘を正室に迎えた件、義稙の没後に大内義隆がその肖像画を描かせたという件なども、その延長戦上の動きとして理解できるのではないでしょうか。
香西氏の地元に伝えられてきた大内義興の最期と幻の上洛の話、真偽はさておき、当時の状況と重ねあわせると妄想が膨らみますね。
「讃州藤家」から香西氏を興した香西左近将監資村
『南海通記』や『香西記』所収の「讃州藤家香西氏略系譜」によると、香西氏は源平合戦において源氏方に与して活躍した「讃州藤家」(讃岐藤氏とも)と呼ばれる武士の一族を出自としています。
その始祖は保安元年(1120)に讃岐守として赴任した中御門藤中納言家成と、阿野郡の大領を務めた豪族・綾氏の娘の間に生まれたという藤大夫章隆とされています。
「讃州藤家」は大野氏、羽床氏、新居氏、香西氏、福家氏、西隆寺氏などの諸氏に分かれますが、新居藤大夫資光は源平の争乱において源氏方となって屋島合戦で軍功を立てました。
その新居藤大夫資光の子、新居次郎が香西左近将監資村で、「承久の乱」の際に幕府方に付き、宇治川合戦での戦功によって阿野・香川両郡の地頭に任ぜられ、笠居郷に屋敷を構えて「香西」と称したことが香西氏の始まりと伝えられています。
(当時「讃州藤家」の嫡流は羽床氏でしたが、羽床氏は「承久の乱」で宮方に付いたため凋落し、これに代わって香西氏が台頭することになったようです。)
勝賀山上に詰めの城である勝賀城を、勝賀山麓に平時の居城として佐料城を構えるとともに、笠居郷の発展の礎を築いた香西左近将監資村は、地元香西においては現在も「資村公」と呼ばれて崇敬されています。
佐料城跡とされる、佐料公民館と奥津神社。
佐料は現在の高松市香西よりも内陸寄りの高松市鬼無町にありますが、香西資村の出自である新居(にい)や、同じく新居からの分家という福家(ふけ)は、更に内陸の高松市国分寺町に地名として残っています。
笠居郷の開発とともに瀬戸内海へと進出していった香西氏は、天正年間には長宗我部氏の讃岐侵攻に備えて、香西浦の藤尾城に本拠地を移すことになります。
なお、香西氏は笠居郷に因んで「かさい」と称したとする説がありますが、平安後期に編纂された辞書『和名類聚抄』(和名抄)には香川郡が東・西両条に分割されたこと、また康治2年(1143)の太政官牒案には讃岐国野原荘の四至に「香西坂田郷」と見え、同文書の同年9月13日、10月20日には「幸西」とも見えることから、香西条に因む地名としての「香西」(こうざい/こうさい)は香西氏以前から存在していたようです。
(『角川日本地名大辞典 37 香川県』)
『香西記』には以下のような記述があり、笠居=香西=「かさい」説はここから導かれたものと思われます。
香西地名は前に述る如し。香河の東西を別て云處なり。然れは則香東六郷を都て香東と云、又香西六郷を都て香西と云也。爰に香西氏代々笠居郷に居す。因て笠居を香西とも混せり。然るに葛西と云は非也。葛西氏有故に誤れり。葛西氏は関東の姓也。笠居の海邊を香西浦と云。香西の海濱成故也。又昔香西氏居城藤尾山の邊地を指て、香西浦と云事最可也。
また、人名として確かな史料に現れるのは、財田の南朝方攻略に関する建武4年(1337)6月20日の細川顕氏書下に「香西彦三郎」とあるのが初見とのことで、左近将監資村との関係は分かりませんが、これ以前より存在していた香西氏の一族が細川氏に従って北朝方として活動したのは間違いないようです。
(『角川日本地名大辞典 37 香川県』)
「細川四天王」で唯一、讃岐土着の武士であった香西氏
時代は下って応仁・文明の乱の頃、『南海通記』には細川勝元に仕えた「細川家ノ四天王」の一人として、香西備後守元資が登場します。
享徳元年ヨリ細川右京大夫勝元ハ、畠山徳本に代リテ管領職を勤ルコト十三年ニ至ル、此時香川肥前守元明、香西備後守元資、安富山城守盛長、奈良太郎左衛門尉元安四人ヲ以テ統領ノ臣トス、世人是ヲ細川家ノ四天王ト云フ也。
室町時代の細川家による讃岐支配は、香川氏を西守護代、安富氏を東守護代として、香川氏が多度津に天霧城、香西氏が香西浦に勝賀城、安富氏が津田に雨滝城、奈良氏が宇多津に聖通寺城と、「細川四天王」のそれぞれが瀬戸内海に港を擁する要衝に山城を築き拠点としていました。
『南海通記』は四天王それぞれの讃岐における領地とその由来について、以下のように述べています。
各讃州ニ於テ食邑ヲ賜フ、西讃岐多度、三野、豊田三郡ハ詫間氏カ領也。詫間没シテ嗣ナシ、頼之其遺跡ヲ香川ニ統領セシム、那珂、鵜足ノ二郡ハ藤橘両党ノ所有也。是ヲ細川家馬廻ノ武士トス、近年奈良太郎左衛門尉ヲ以テ二郡ノ旗頭トス、奈良ハ本領畿内ニアリ、其子弟ヲサシ下シテ鵜足津ノ城ニ居住セシム、綾ノ南條、北條、香東、香西四郡ハ、香西氏世々之ヲ領ス、三木郡ハ三木氏没シテ嗣ナシ、安富筑前守ヲ以テ、是ヲ領セシム、香川、安富、奈良ハ東國ノ姓氏也。細川家ニ属シテ當國ニ來リ、恩地ヲ賜フテ居住ス、其來往ノ遅速、何ノ年ト云フコトヲ知ラス、香西氏ハ當國ノ姓氏也。建武二年細川卿律師定禪當國ニ來テ、足利家歸服ノ兵ヲ招キシ時、詫間、香西是ニ属シテ武功ヲ立シヨリ以來、更ニ野心ナキ故ニ、四臣ノ内ニ揚用サラル其嫡子四人ハ香川兵部少輔、香西備中守、奈良備前守、安富民部少輔也。此四人ハ在京シテ管領家ノ事ヲ執行ス、故ニ畿内ニテ食邑ヲ賜フ、其外在國ノ郡司ハ、大内、寒川二郡ハ寒川氏世々之ヲ領ス、山田郡十二郷ハ、三谷、神内、十河ヲ旗頭トシテ、植田氏世々相持テリ、細川管領家諸國ヲ統領スト云ヘトモ、讃州ヲ以テ根ノ國トス、
郡単位ではこのような勢力配置となります。
- 香川氏(天霧城)…多度郡、三野郡、豊田郡
- 奈良氏(聖通寺城)…那珂郡、鵜足郡
- 香西氏(勝賀城)…阿野郡(綾南條郡、綾北條郡)、香川郡(香東郡、香西郡)
- 安富氏(雨滝城)…三木郡
- 寒川氏(昼寝城)…寒川郡、大内郡
- 植田氏(戸田城)…山田郡
このうち、香川氏と安富氏と奈良氏はいずれも主君の細川氏に従って関東から讃岐へと移住した御家人で、香西氏、寒川氏、植田氏(三谷、神内、十河)は讃岐土着の武士です。
ややこしいのですが、香川氏は相模国高座郡香川村を出自とする一族で、讃岐国の香川郡とは関係ないそうです。(僕はずっと勘違いしてました…)
このように讃岐の多くに関東出身の一族が配されたのは、南北朝期に幕府方として西国平定に多大な貢献を果たした細川氏の活躍によるものですが、香西氏は細川の麾下に入った讃岐の国衆の中で、特に戦功を認められたようです。
『蔭涼軒日録』明応2年(1493)6月18日条には「讃岐国者十三郡也、六郡香川領之、七郡者安富領之、国衆大分限者惟多也、雖然香西党為首皆各々三昧不相従安富者惟多也」とあり、讃岐の国衆には富裕な者が多く、好き勝手に事を行って安富氏に従わない者が多くいたようで、とりわけ香西氏はその代表格と見なされていたことが窺えます。
讃岐の国衆達が富裕を誇るに至ったのは、彼らが京都へと繋がる瀬戸内航路の要衝を掌握していたことが大きかったのでしょう。
東大寺領であった兵庫津北関の関税徴収記録『兵庫北関入船納帳』にも「香西」の名が見られるほか、香西氏は備讃瀬戸の要衝で造船・航海技術に優れた「塩飽衆」を擁する塩飽島や直島に一族を配していたと伝えられており、香西氏は有力内衆として政事や軍事に貢献するとともに、物流においても畿内における細川家の活動を支えたのではないでしょうか。
前述した大内堂の縁起が伝えている永正年間の「香西豊前守海上ノ警衛ヲ奉テ廻船ノ非常ヲ制ス」も、そのような経緯によるものと考えられます。
丹波守護代に抜擢された香西常建と、丹波守護代を失った香西元資
讃岐生え抜きの武士であった香西氏が、細川京兆家の内衆として畿内で活動する切っ掛けとなったのが、細川頼之(入道常久)に仕えた香西常建です。
細川頼之は観応の擾乱で西国において南朝方の掃討に活躍しましたが、京都の政争で失脚して南朝方に降り阿波へと逃れた従兄・清氏を討伐し、以後、細川家の嫡流は清氏から頼之へと移りました。
有名な軍記『太平記』の最後は、幼少の将軍義満を補佐する細川頼之の執事(管領)就任をもって天下泰平を祝福して終わっていますが、実際にはその後も斯波氏との政争に敗れて阿波へと下国したり、また復権したりと波瀾万丈の生涯を送っています。
なお、本宗家と阿波守護家に分かれたのは頼之の弟、頼元と詮春からで、頼元が継いだ本宗家は代々「右京大夫」の官途を継承して「京兆家」と呼ばれ、詮春が継いだ阿波守護家は代々「讃岐守」の官途を継承して「讃州家」と呼ばれるようになったのです。
また、京兆家は摂津、丹波、讃岐、土佐の四ヶ国守護を合わせて継承し、庶流家は和泉、淡路、阿波、備中の各国をそれぞれ継承しました。(和泉は上下半国守護制)
いわば、室町期における細川家の繁栄の礎を築いたのが細川頼之ですが、香西常建は頼之の死後も後継者の頼元に仕え、細川氏が明徳3年(1392)に「明徳の乱」の戦功によって山名氏の領国丹波の守護職を獲得するに至り、応永21年(1414)には小笠原成明の跡を継いで丹波守護代に補任されました。
『康富記』応永29年(1422)6月8日条には「細河右京大夫内者香西今日死去云々、丹波国守護代也、六十一云々」とあり、常建は細川京兆家の元で一代で讃岐国衆から京兆家内衆の一員に抜擢され、その晩年に丹波守護代を務めたことが分かります。
この香西常建の次に丹波守護代を継いだのが香西豊前守元資ですが、元資は永享3年(1431)7月には当時の京兆家当主・細川持之によって罷免され、丹波の代表的国衆である内藤氏(備前入道)と交代させられています。
『満済准后日記』永享3年7月24日条には「右京大夫申丹波守護代事、申入処此間守護代香西政道以外無正体間、可切諌由被仰了」「丹波守護代可為内藤備前入道」とあり、細川持之が将軍義教の護持僧であった満済に相談して丹後守護代を内藤備前入道に交替したらよいか将軍に尋ねるよう申し出たところ、その後訪れた将軍は香西は政治のやりかたがでたらめである、厳しく処罰するよう伝えよと言ったようで、どうも罷免の原因は永享元年の丹波国一揆を招いたことにあったようです。
「香西備後守元資」を「細川家ノ四天王」として紹介する『南海通記』には常建の事績が紹介されていないばかりか、元資が丹波守護代であったことも記されていないのですが、常建が傍系の出身であったか、あるいは『南海通記』を記した香西成資が先祖に当たる元資の不名誉に触れたくなかったのではないかと推察されています。
(藤井公明『香西氏研究』)
上香西と下香西に分かれた香西氏
『香西記』の系図によると、香西元資の後継者に当たる元直と元顕の兄弟(?)で、元直が上香西氏、元顕が下香西氏の二流に分かれたとされています。
『蔭凉軒日録』長享3年(1489)8月12日条には「又香西党太多衆也、相傳云、藤家七千人、自余諸侍不及之、牟礼鴨井行吉等、亦皆香西一姓者也、只今亦於京都相集、則三百人許有之乎云々、」とあり、京兆家主催の犬追物のために集まった香西氏の一党(牟礼・鴨井・行吉を含む)は300人に及んだと記されており、中でも細川政元の信頼を得た香西又六、香西五郎左衛門、牟礼次郎兄弟らの活動は史料によく登場しており、政元が主催した犬追物にもたびたび参加しました。
『蔭涼軒日録』には香西又六と香西五郎左衛門の二人が「両香西」とも称されていることから、又六が上香西、五郎左衛門が下香西を代表する人物であったとも考えられます。
香西又六は明応6年(1497)10月に山城守護代に任じられ、やがて細川政元の養子澄之を擁立、政元暗殺の首謀者として知られる、香西元長です。
(香西元長と上香西氏の動向については、また別の機会に書く予定です。)
一方の香西五郎左衛門は、延徳3年(1491)10月に京兆家内衆で備中守護代を務める庄伊豆守元資が備中に下国し、備中守護の細川勝久に対し挙兵した「備中大合戦」において、西備前の松田氏らと共に庄氏に味方して戦いましたが、延徳4年(1492)3月の戦いに敗れて讃岐勢の大半と共に討死してしまいました。
この「備中大合戦」は京兆家が内衆を使って備中守護家へ介入しようとしたものと捉えられていますが、その背景には当時の将軍・足利義材が讃州家や備中守護家の取り込みを図ったため(讃州家出身で備中守護家の養子となっていた細川之勝が将軍から偏諱を授かり「義春」を名乗ったのもこの頃)、対立を深めていたという流れがありました。
これが政元による讃州家の懐柔策を招き、引いては政元の後継者問題を通じて、内衆の派閥抗争を激化させてしまうことになるわけです。
ちなみに庄伊豆守元資は前回の記事 『「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(中編)将軍義尹の甲賀出奔事件の背景』 でも紹介した「細川政元拉致事件」において安富新左衛門尉元家と共に一宮方へ討ち入った人物ですが、その時の感状を巡って安富氏と対立関係にありました。
また、応仁・文明の乱において、西備前一帯を支配する金川城主・松田氏が山名氏と手を組んで赤松氏・浦上氏と戦った際にも、庄元資は松田方に味方したようです。この一連の戦いで嫡子の則景を失った浦上則宗は、後に安富元家の子を養嗣子に迎えることになりました。
更にずっと後のことですが、宇喜多直家に滅ぼされた松田元賢の弟元脩は毛利家に属し、関ヶ原合戦の敗北によってしばらく直島に逃れた後、香西に移り住んだとの伝承があります。
元脩は香西・植松両氏の世話を受けて堀の内に居住し、高松藩の命により塩田開発に従事、その子孫は藤尾山の南東麓に郎党の五輪塔を立てて先祖の松田左近将監元親の木像を祀り、表向きは竈(へっつい)神社=かまどの神様として崇敬していたそうです。
現在、松田左近将監の像は宇佐八幡宮の摂社白峯神社に合祀され、竈神社の跡地にています。
(参考:発見!キラッと☆香西 ヘッツヒ神社)
備前の松田氏は、讃岐の香西氏とは不思議な縁がありますね。
勝賀山と香西の史跡を巡ってみた
今年の正月とお盆、二度に渡って香西に訪問した時の写真です。
勝賀山は時間と装備不足で残念がら山頂の城跡までは見られなかったんですが、中腹までから各城の位置関係や高低差を見ることで、香西氏が天正年間に佐料城から藤尾城へと本拠地を移した理由が何となく感じられました。
標高360mを超え、山城としては結構高い方と思われる勝賀山ですが、山全体にみかん畑が広がっていて、平成に完成した勝賀農免道路が走ってます。この道路を通って登山口付近まで車で近寄れました。
(駐車場はありませんが道幅が広くなっているところがあり、ちょうど山の陰になっていたのでそこに停めました。)
勝賀山と佐料城、薬師山、大内堂などの位置関係はこんな感じ。勝賀山は大きくて、この絵が大げさではないくらいのスケール感です。
こちらは勝賀城登山道からの眺望です。足元に広がるのはみかん畑。
真ん中が神宮寺山、その右側が薬師山、その右奥が峰山、その左奥辺りが高松港、さらに奥にうっすら見える台形が源平合戦で有名な屋島。左側に女木島も見えてます。
香西氏が佐料城から移転したという藤尾城には、宇佐八幡宮が建っています。
藤尾山は今でこそ内陸ですがかつて「磯崎山」と呼ばれ、『香西記』にも「又昔香西氏居城藤尾山の邊地を指て、香西浦と云事最可也」とある通り、当時は香西浦の水辺に面していました。
(藤尾というのは香西資村が勧請した宇佐八幡宮の元の遷座地の名前だそうです。参考:発見!キラッと☆香西 宇佐八幡宮)
香西氏は長宗我部氏の侵攻に備えて、水上交通の要衝として発展してきた香西浦を包摂する海城を新たな主城として、周辺丘陵地の支城による防衛網を敷き、瀬戸内方面からの支援ルートを確保することで、長期戦に耐えうる体制の構築を図ったのではないでしょうか。
八幡宮のすぐ側には香西神社があります。香西小学校の校庭に建立された忠魂社が戦後に名を改めて移転されたそうです。
祭神は香西左近将監資村公を始め十余の先賢と、二百三十余柱の英霊が合祀されているとのこと。
ここからは、香西氏の出城であったという芝山城跡です。
天正年間には直島を本拠地としていた渡辺氏の一族、市之丞と三之丞兄弟が守っていたと伝わります。
芝山の頂上には現在、芝山神社が建っています。祭神は大国主命(大黒様)、事代主命(恵比須様)、市杵島姫命(弁天様)。
神社の裏に立つ宝篋印塔は、香川郡笠居の「紀伊國屋」によって奉納されたもの。
芝山の東側が現在の香西港になります。イオンモール高松やマルナカが建っています。真ん中の奥の方に見える台形のが屋島です。
芝山から見た勝賀山です。佐料の方からだと山頂が削られた跡なのか結構べったりして見えますが、海側から見ると美しく感じました。
(『香西記』に「勝れて高く美しき山也」と評されているのはこちら側からの眺めでしょうか?)
芝山から見て、真ん中の小さい森が藤尾山、その奥が薬師山です。
全体を収めるとこんな感じ。勝賀山の大きさが分かりますよね。香西の人々にとっては常に仰ぎ見る、特別な山なんだろうと思いました。
本文に記載したものの他、参考にさせていただいた書籍、資料、Webサイト等の紹介
今回は香西氏ということで、参考になる書籍が見つからず、かなりWeb上で公開されている情報に頼る結果となりました。
特に瀬戸内の港町や水軍と幕府、あるいは地域権力との関わりについては、知識の不足を痛感させられます…。
「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典 37 香川県』(角川書店)
- 作者:
- 出版社/メーカー: 角川書店
- 発売日: 1985/10
- メディア: 単行本
1985年と少し古い本ですが、地名としての「香西」の起源や香西氏の関わり、塩飽諸島の略歴を学びました。
こういう辞典を初めて読んだのですが、知らない地域の経歴や史跡について調べるのに意外と役立ちますね。
宇田川武久『瀬戸内水軍』(教育社歴史新書)
ずいぶん昔に購入した新書ですが、あまり記憶に残らないまま本棚に眠っていたものです。
「大内義興報恩堂」にちなんで、香西氏と日明貿易の関わりについて少しでも書いてるかもと考えて久しぶりに開いたら、冒頭から香西成資が『南海通記』に記した水軍に関する内容が強く批判されていて、苦笑してしまいました。
香西氏とその麾下の水軍については直接触れられてはいませんが、「警固衆」と呼ばれる大内氏麾下の水軍が遣明船の警固に当たった経緯などを学びました。
国立国会図書館デジタルコレクション
久々にこのサイトに当たりましたが、『香西記』や『南海通記』が丸ごと収録されていて驚きました。
『南海通記』は江戸時代前期の兵法家・香西成資によって記された四国の通史です。
いわゆる軍記物語として扱われていますが、荒唐無稽な内容ではなく、概ね時系列順で例えば「細川高国與細川澄元諍管領職記」「讃州香西氏建大内堂記」「讃州河野氏建不動堂記」「讃州塩木合戦記」「讃州津柳合戦記」のようにエピソード毎に分けて書かれていて読みやすく、郷土史料としても有用な内容です。
まだ通読はしていませんが、四国の戦国史を調べる上では避けては通れない書物のようで、内容も多彩で面白いので、今後も読む機会がありそうです。
『香西記』は藤尾八幡宮の祠官・新居香流軒直矩が、地元の伝承を集めた史料です。
香西周辺の名所旧跡や神社の縁起などが多く、現地を訪ねるに当ってイメージを膨らませるのに役立ちそうです。
「讃州藤家香西氏略系譜」も収録されており、香西氏を知る上でこちらも必読だと思います。
古野貢「室町幕府-守護体制下の分国支配構造-細川京兆家分国丹波国を事例に」
確かな史料に基いて、丹波一国で約200年に及ぶ京兆家と守護代たる内衆、そして国人たちの変遷を解説されています。
香西氏について参考にしたのはごく一部ですが、荻野氏が関わった「丹波国一揆」や波多野氏の地域権力化(守護権からの自立)について多く触れられており、今後も何度か読み返すことになりそうです。
「細川氏守護補任以後の丹波守護と守護代の事跡」として、現存する文書の一覧が掲載されており、丹波に関する史料のインデックスとしても有用だと思います。
(上香西氏と関連して波多野氏の経歴にも触れざるを得ないので、また読むことになるでしょう。)
高松短期大学『研究紀要』
それぞれ昭和56年、昭和58年と古いものですが、Webで読める香西氏の研究としては唯一かもしれません。
- 第十一号 藤井公明「香西資村とその時代」
香西氏の祖とされる資村の経歴のみならず、当時から香西の地がどのように発展していったのかが考察されていて、実際に現地を巡る際にも往時を偲ぶ上で役立ちそうです。
資村が進めた漁業振興政策が水軍の養成に繋がったとの説明も、香西氏の特質を知る上で学ぶところが多かったです。
香西=笠居=「かさい」説に強くこだわっておられるようで、わざわざ「かさい」とふりがなされていたり、「室町時代になると、立身出世の夢を追うて、都あたりの戦争に明けくれたのであった」と、京兆家内衆としての畿内進出については否定的な見方をされているのも特徴的です。
- 第十三号 藤井公明「香西氏研究」
香西氏の経歴について非常に詳しく解説されています。特に畿内進出の先駆けとなった香西常建について学びました。
出家して讃岐宇多津に帰った細川頼之(入道常久)の親衛隊の一人として香西氏から加わったのが、若き日の常建ではなかったかと想像されていて、面白いです。
白峰寺に奉納された「頓証寺法楽百首」に収録されているという、常建と元資が詠んだ和歌についても紹介されています。
飯倉書屋
「香川史学」第17号『細川家内衆香西氏の年譜ー香西又六の山城守護代任命までー』より抜粋、とのことですが、香西氏の初見となる建武4年6月20日から、明応6年10月の香西又六(元長)の山城守護代就任までの、確かな史料に見える香西氏の動きが列挙されていて、参考になります。
細川氏一門の守護支配と京兆家
政元主催の犬追物に参加した香西氏一党について記された、『蔭凉軒日録』長享三年八月十二日条の解説が参考になりました。
香西氏が京兆家のみならず和泉下守護家にも庶流の香西藤井将監を内衆として輩出し、同じ「香西党」として認識されていたことをもって「京兆家と庶流家の紐帯」と説明されていて、こちらも興味深いです。
香川県埋蔵文化財センター研究紀要
たまたま検索で見つけた資料ですが、「野原」=香東郡野原庄は現在の高松城付近のことで、香西と同じ高松平野で共に発展した港町ということで参考になりました。
市村高男先生からは、香西氏の家臣に紀州雑賀出身者がいることや、「香西氏が香西の港を掌握しながら外来の武装商人集団を引っ張ってきている可能性がある」との興味深い指摘もあります。
将軍・足利義輝の弑逆「永禄の変」から探る三好政権分裂の実情
三好長慶死後の三好氏といえば一般には、将軍・足利義輝を「暗殺」した後、松永久秀と三好三人衆が対立して争う間に、「天下布武」を掲げて全国統一を宣言した織田信長が、義輝の弟・義昭を擁立して上洛を開始し、その怒涛の進撃の前に三好方は為す術もなく崩壊したと認識されていると思います。
前回の記事(三好長慶の畿内制覇と本願寺「石山合戦」への道)では、三好長慶が独力の裁許による支配体制を構築するに至りながらも、将軍・足利義輝の権威を必要とした経緯に触れましたが、その三好政権が長慶の死後、なぜ将軍を殺害するに至ったのでしょうか。
また、三好政権はかつての主筋である阿波守護・細川持隆が庇護していた「阿波公方」足利義冬の子・義栄を擁立し、在位期間は短いながらも義栄を将軍とする新たな体制で幕政を運営しました。しかし、その過程で松永久秀父子に続き、三好宗家を継いだ三好義継までもが政権から離反してしまったのです。
従来、松永久秀は三好政権を壟断しようと企んで三人衆と対立した後、信長の上洛に際してその猛勢に恐れをなして降伏したと捉えられてきました。しかし、三好政権における久秀の実像や将軍義輝を殺害した「永禄の変」の背景を知るほどに、そのような解釈に疑問を感じるようになりました。
長慶の死後から「阿波公方」の擁立に至るまでの経緯をまとめつつ、三好長慶と将軍・足利義輝の静かな戦いを振り返るとともに、なぜ松永久秀が三人衆と対立したのかについても、妄想を交えながら考えてみます。
三好政権による将軍・足利義輝の弑逆「永禄の変」の経緯
永禄7年(1564)7月4日、「天下執権」たる地位に上った三好長慶が病に斃れてしまいます。三好宗家の家督を継いだのは養子となっていた孫六郎重存(後の義継)で、長慶の死は遺言に従って秘匿されることとなりました。
重存はまだ15歳にも満たない少年であったため、最長老として三好一族を代表する地位にあった三好日向守長逸、かつての政敵・三好政長の子の三好下野守、長慶に見出されて奉行衆から出世した岩成友通という、三者三様の「三好三人衆」と、大和一国を任されるとともに朝廷との交渉でも重要な役割を果たした松永久秀、その弟で丹波方面を任されていた内藤宗勝(松永長頼)の5人を中心に政権の再興が図られました。
畿内を実力で制した三好長慶はその晩年、22歳の若さで病没した嫡子・義興の死に際して、三好氏の菩提寺である南宗寺の住持・大林宗套に葬礼を行わせ、将軍の葬礼を担当する五山(足利氏が臨済宗の中でも南禅寺を頂点とした5つの寺院を別格と定めた)の禅僧を勤仕させるとともに、関白九条家の血筋を継ぐ重存を後継者に定めるなど、最期まで足利将軍家の権威への挑戦を続けました。
そんな長慶の意志を継いだ重存は、一挙に足利将軍家との関係に決着を付けようとしたものか、ついに実力行使に及びます。
永禄8年(1568)5月1日、三好長逸や松永久通らを率いて義輝の元に出仕した重存は、左京大夫の官途とともに偏諱を授かって名を「義重」と改めますが、5月18日に一万の軍勢を率いて再び上洛した翌日の5月19日の朝、将軍義輝の御所を包囲して討ち入り、将軍を殺害してしまったのです。
この「永禄の変」では、義輝の弟で鹿苑寺の僧であった周嵩、義輝の母の慶寿院、そして義輝の子を身籠っていたという側室の小侍従が殺害され、小侍従の父・進士美作守晴舎を始めとする多くの近臣たちが討死、あるいは自刃しました。
翌日には公卿の久我家や高辻家、近衛家が討たれるという噂も流れ、一時は都が騒然としていたことが窺えますが、21日には三好義重の代理として三好長逸が天皇に参内して酒を下賜され、22日には奉公衆や奉行衆ら幕臣が三好義重や松永久通の元に出仕し、騒ぎは収まることになりました。
なお、塚原卜伝の弟子であったという「剣豪将軍」義輝が将軍家伝来の名刀を次々と取り替えながら敵を切り倒したという逸話が知られていますが、『言継卿記』など当時の記録にはそのような記述は見られません。
この逸話の最初の出所は、室町末期から江戸初期の間に成立したと考えられている軍記『足利季世記』の「公方様御前に利剣をあまた立てられ、度々とりかへ切り崩させ給ふ御勢に恐怖して、近付き申す者なし」(永禄の大逆 足利季世記より)という記述だと思われますが、その元ネタの一つとして知られる『細川両家記』には「乙丑五月十九日に二条武衛陣の御構へ人數押入御生害候上は。御内侍衆討死候也。」と記されているのみです。
(『細川両家記』は上巻が天文19年、下巻が元亀4年に書かれた軍記ですが、内容的には一次史料の隙間を補完するに足る、信憑性の高い書物として扱われています。)
一方、当時の伝聞を記録した書物として(宗教絡みの事柄を除けば)信頼性が高いとされるルイス・フロイスの『日本史』には、自ら武器を取って戦った将軍の奮戦を称える記述があります。
軍記というものの性質上、当然『足利季世記』には創作が加えられているでしょうが、一万もの兵に襲撃されながら二時間以上持ちこたえたことは『言継卿記』にも記されており、確かに将軍とその側近達は最後の意地を見せたのでしょう。
「永禄の変」で実力行使に及んだ三好政権の狙いと松永久秀の動向
三好政権にとって、将軍・足利義輝はそれほど放置できない危険な存在だったのでしょうか。三好長慶の生前に遡ってみます。(ちょっと長くなり、余談も増えます)
永禄元年末の将軍義輝との和睦以来、三好長慶はその権威を利用して、大友氏を動かして讃岐西部への進出で対立する毛利氏を牽制、あるいは旧信濃守護・小笠原長時の旧領回復を支援するよう長尾景虎に働きかけるなど、外交戦略を有利に運びました。
(武田信虎の甲斐追放と「武田入道」の在京奉公でも少し触れましたが、旧領回復を狙って上洛した小笠原長時は、阿波小笠原一族の後裔を称する三好氏の客将となっていました。長時は義興を通じて筑前守(長慶)の病状を知っていたり、細川晴元の嫡子六郎の馬術指南を勤めるなど、三好政権に深く関わっていました。謙信と信玄の「一騎討ち」で知られる永禄4年の第四次川中島の合戦の発端には三好氏の意向が絡んでいた可能性があります。)
また、畠山氏の内紛に介入して河内へと進出、永禄5年3月の久米田の戦いでは弟の三好実休を失う痛手を負ったものの、5月の教興寺の戦いで畠山方を破り、松永久秀はその勢いで反三好方の諸城を落として大和を平定しました。
(なお、この時の多武峰衆徒との戦いでは大和柳生郷の土豪・柳生家厳が松永方として参戦しており、父と共に戦功を立てた柳生新介、後の石舟斎が久秀から感状を受けています。柳生氏は以後も一貫して松永方として行動することになります。)
教興寺の戦いに勝利した三好氏は、畠山氏に呼応して京都を制圧していた六角承禎父子とも和睦、石清水八幡宮に避難していた将軍も帰京しましたが、この時義輝の伯父・大覚寺義俊が逃亡を図ったほか、これまで政所執事として三好政権に協力していた伊勢貞孝父子までもが近江坂本へ退去しており、畠山・六角氏の連携の陰では幕府から三好氏を排除する陰謀が動いていたことが窺えます。
(大覚寺義俊は近衛前久の祖父・近衛尚通の子で、義輝と義昭の生母である慶寿院の兄という関係で、後には義昭を助けて越後上杉氏や越前朝倉氏への使者を務めるなど、その流浪期を支えたキーマンの一人となっています。)
一方で、微妙な立場に追い込まれ挙兵した伊勢貞孝が松永久秀によって討伐されると、将軍義輝はこれまで執事職を世襲してきた伊勢氏を政所から追放、代わって側近の摂津晴門を起用するなど、表面上は長慶に従いながらも将軍親政を強く志向していたことが明らかとなりました。義輝は決して三好氏の傀儡に甘んじるような人物でなかったのです。
将軍義輝との和睦を三好政権の幕府への屈服と捉え、兄弟の相次ぐ死と嫡子・義興の死で心を病んだ長慶の晩年は廃人同然だったなどと評されることがありますが、前述の通り、長慶が足利将軍家の権威に挑戦し続けたことは確かです。しかし、最終的に将軍義輝との関係にどう決着を付けるつもりだったのかは分かりません。
『信長公記』には「三好修理大夫、天下執権たるに依って、内々三好に遺恨思食さるべしと兼て存知、御謀反を企てらるゝの由申掠め」と記されており、当時の世評では、長慶が将軍義輝の「御謀反」を理由として殺害したと見られていたことが窺えますが、実際にはすでに長慶は病没していたため、三好政権はこれまで以上に将軍の動きを警戒していたものと思われます。
フロイス『日本史』には御所を包囲した三好方が進士美作守に突きつけた訴状の内容として、将軍自身の命ではなく、将軍の愛寵を受けて懐妊していたという側室の小侍従と近臣達の殺害を要求していたことが記されている一方、『細川両家記』には将軍の正室である関白・近衛前久の姉は三好長逸によって近衛邸まで送り届けられたことが記されており、三好方には足利将軍家と関白近衛家の関係を断つ狙いがあったことが窺えます。
(そもそも、天文24年の時点で前久は元服の際に将軍義晴から賜った「晴嗣」の名を「前嗣」と改めており、前久は父の稙家以降から親密な関係にあった将軍家と距離を置こうとしていたようです。将軍が側室の小侍従を愛寵したというのも、そのような近衛家との関係の変化が影響したのではないでしょうか。)
また『言継卿記』には「阿州之武家可有御上洛故云々」とあり、三好方が11代将軍・義澄の子で義輝の伯父に当たる「阿波公方」足利義冬の擁立を企んでいることが噂されていたようです。
これらのことから考えると、三好方は当初から将軍の殺害を意図したわけではなく、義晴-義輝と続いた血筋を断絶させる代わりに、関白近衛家の協力を得た上で、阿波公方家を唯一の将軍家として存続させようとしたのではないでしょうか。将軍弑逆という大事件を起こしたにも関わらず、阿波公方の擁立まで1年半もの時間を必要としたのは、当初の計画通りに事が運ばなかったことを示しているように感じます。
なお、この三好政権による将軍義輝の弑逆は、近世以降、松永久秀の悪虐ぶりを示す逸話として語られてきましたが、当時の史料からは久秀の積極的な関与は認められません。
また、これまで久秀は覚慶を「幽閉」したと捉えられてきましたが、覚慶が義輝の死からわずか3日後の5月22日に松永久通に宛てた書状で「進退の儀気遣い候処、霜台(松永久秀)誓紙を以って別儀あるべからず由候間安堵せしめ候、弥疎略なきにおいては、別して祝着たるべく候」と記しているように、当時大和に在国していた久秀は、興福寺一乗院に入寺していた義輝弟の覚慶(後の義昭)に誓紙を提出してその保護を図りました。同じく僧籍にあった兄弟の周嵩が殺害されているにも関わらずです。
「阿波公方」の擁立により始まった二人の将軍候補を旗頭とする争乱
三好政権が「阿波公方」の擁立に至るまでの、両者の関係はどうだったのでしょうか。更に遡ってみます。
(写真は阿波平島の公方館跡)
まだ三好長慶が細川晴元の麾下にいた天文16年(1547)、義冬は証如に援助を依頼して堺へと渡り上洛を窺ったものの果たせず帰国、その後、氏綱方となった三好長慶は天文22年(1553)10月、「四国室町殿」(足利義冬)に上洛を促したものの、義冬はこの要請には応じませんでした。同年6月に、長慶の実弟で阿波三好家の実休が、義冬を庇護していた細川持隆を謀殺したばかりであったため、三好氏を信頼することができなかったのでしょう。
『平島記』によると義冬は阿波守護・細川持隆の庇護のもと、天文3年(1534)以来、足利氏とゆかりの深い天龍寺領・平島庄の西光寺を御所としていましたが、弘治元年(1555)4月に妻の実家である大内氏を頼り、妻子と共に周防山口へと移りました。大内氏といってもすでに義隆は陶隆房の謀叛によって殺害されており、毛利氏とも断交しまさにあの「厳島の合戦」に至る直前のことです。
その後、大内氏領を併呑した毛利氏と義冬父子がどのような関係にあったのかは分かりませんが、義冬は永禄6年(1563)に三好長逸からの説得を受けて再び阿波平島に復帰したと伝えられています。これが事実であれば、三好政権の最盛期である永禄初期には顧みられなかった義冬父子が、長慶の晩年に再び選択肢として浮上していたことになります。
(なお、足利義冬は将軍に就任することはなかったものの、次期将軍に授与される従五位下左馬頭に就任して「堺大樹」と呼ばれた、いわゆる「堺幕府」の将軍・足利義維です。義維と三好氏の関係については、天文の錯乱・山科本願寺焼失と『祇園執行日記』に見える京都周辺の情勢でも概略に触れています。)
さて、義輝弑逆からわずか半年後、永禄8年(1565)11月には早くも三好三人衆と松永父子が対立して交戦を開始しており、12月には三人衆方が飯盛山城を占拠して義継を高屋城に迎えるとともに、篠原長房や三好山城守康長ら阿波三好家と手を結び、対する松永久秀は三人衆方に対抗するため、紀伊へと逃れていた畠山政頼(後の秋高)と結びました。
畠山氏は「永禄の変」に際して、その翌月6月24日には畠山氏の重臣・安見宗房が上杉謙信に挙兵を促すとともに、朝倉義景や織田信長を調略していることを伝えており、7月28日には朝倉義景の支援を受けた覚慶が大和を脱出して奉公衆・和田惟政の居城である甲賀和田城へと逃れています。そして安見宗房は覚慶の脱出を喜ぶとともに、阿波公方の上洛前に家督を継承できるよう協力する旨を伝えています。
また、永禄8年(1565)8月に松永久秀の弟・内藤宗勝が荻野悪右衛門直正(赤井直正)の攻撃で敗死した際、畠山氏の重臣・遊佐信教は宗勝の討死を将軍殺害に結びつけて「上意様御天罰」などと報じています。その僅か3ヶ月後に、敵方であったはずの松永久秀と手を結ぶことになったわけです。
このような動きを見ると、もはや三人衆方と松永方の争いは三好政権の内訌に留まるものではなく、二人の将軍候補を旗頭とする「天下」の争奪戦に発展したと捉えるべきでしょう。
前述したように「永禄の変」に際して覚慶を保護した松永久秀が、実はその擁立を計画していたとすれば…そのことで阿波公方の擁立を進める阿波三好家とそれに与する三人衆との間に深刻な対立が生じ、松永父子は政権内で浮いた存在となってしまったのではないでしょうか。
三人衆方が宗家当主の義継を迎え入れるに当たり、飯盛山城を力づくで占拠した一件は、内藤宗勝の死によって影響力の低下した松永久秀・久通父子を孤立させ政権から排除するために、三人衆の方から先手を打ったとも考えられます。
篠原長房が権勢を握る一方で立場を失った三好義継と、松永久秀の真意(?)
四国衆と結んで有利に立った三人衆方では、永禄9年(1566)6月11日に篠原長房が阿波から大軍を率いて摂津に上陸、6月24日には三好義継が河内真観寺で五山長老の参列のもと葬礼を執り行い、その10日後には南宗寺で三回忌を催したことで、これまで秘匿していた長慶の死を広く公表するとともに三好宗家の後継者としての決意を示しました。
その間にも、阿波勢を主力とする三人衆方は、松永方であった滝山城、越水城、西院城、勝龍寺城、淀城を攻略しており、畿内は平定されたかに見えました。しかし、篠原長房と三人衆が「阿波公方」足利義冬の子・義親を擁立したことで、三好義継の立場は大きく揺らぐことになります。
永禄9年(1566)9月23日に摂津越水城へ入った後、12月に摂津富田庄の普門寺城(かつての宿敵・細川晴元が隠居していた城)へと移った義親は、12月28に朝廷から従五位下左馬頭を約束され、翌永禄10年正月5日には正式に叙任されるとともに名を「義栄」と改めました。
阿波公方の擁立と摂津平定に貢献した長房は、この後も畿内における松永方との戦いで阿波勢を率いて活躍、フロイスが「権勢彼等に勝り、ほとんど彼等を左右するの地位にありしもの」と評したように、三人衆を凌ぐ程の権勢を持つことになります。
その一方で、義栄によって冷遇された義継は翌永禄10年(1567)2月、遂に敵方の松永久秀の元へと走ることとなったのです。
さて、ここからは更に妄想を交えて書き連ねていきます。
その後の歴史を知る立場からすると、将軍としての在位期間、本人の寿命とも短命に終わった足利義栄の存在を過小評価してしまいがちです。しかし、義栄の父・義冬(義維)はかつて三好元長と細川晴元に擁立され堺に御所を構えて「天下將軍御二人候」と言われた人物であり、管領・細川高国との対立から阿波撫養へと流れ「島公方」とも呼ばれた不屈の「流れ公方」足利義稙の養子でもありました。
(「明応の政変」以降、足利将軍家は京都を離れることが多くなりますが、二度の将軍就任を経験したのは歴代足利将軍の中でも義稙ただ一人です。)
それを継いだ義栄には当然、義稙や義冬から受け継いだ家臣達がおり、いつか上洛する日を夢見て畿内各地で雌伏の時を過ごした家臣達がいたことも伝わっています。(中には斎藤基速のように、三好長慶に協力して幕政に参加した者もいましたが)
義栄にそのような支持勢力があった点は、将軍の実弟とは言え最初から僧侶として育ってきた覚慶とは大きく異なるところだと思います。
つまり松永久秀は、阿波公方を擁立してしまえば、三好長慶が志した三好宗家を頂点とする新たな武家政権の確立は成し得ないと考えたのではないでしょうか。そして、実際にその危惧は的中し、宗家を継いだはずの義継は政権から排除されてしまったのです。
義継は関白九条家にも縁を持つ(義継の母は九条稙通の養女で十河一存の正室)、当時の武士としては最高級の貴種であり、長慶が嫡子義興の死に際して、十河家断絶の危険を冒してまでも彼を後継者に指名した理由はまさにその点にあったはずです。家中の人望が厚かったという実弟の安宅冬康を殺害したのも、それが幼い義継が家中を掌握する上で障害になることを恐れたためでしょう。(「松永久秀の」讒言を受けて殺害したという話は『足利季世記』以降の編纂物から登場するものです)
それなのに、九条家のライバルである近衛家を頼り、結局は足利将軍家の血筋を担ぎ出すに至っては、守護代以下の地位から「天下執権」たる地位に上り詰めた三好長慶が、何のために三好家の家格を高めるべく尽力してきたのか…。
戦国時代を代表する「梟雄」とされてきた松永久秀ですが、その悪評のほとんどは、近世以降に成立した編纂物の流布によるもので、少なくとも長慶の生前に三好家の壟断を企んだような形跡はありません。そして、久秀は長慶の死後もその意志を尊重し、三好家の傀儡として御しやすいであろう覚慶の擁立を企んだのではないでしょうか。(結果的にはその覚慶も兄に負けず劣らずの存在感を示し続けることになったわけですが…)
久秀が後世に逆臣との謗りを受けている一方、阿波三好家の宿老であった篠原長房は、三好政権の屋台骨を支え続けた忠臣と高く評価されています。しかし見方を変えると、阿波公方の擁立によって権勢を手にした長房は、同時に三好宗家を蔑ろにする結果を招いたとも言えます。
近年、信長以前の「天下人」として三好長慶の再評価が進んでいますが、その腹心を務めた松永久秀についても、近世以降に作り上げられてきた先入観を取り払って見直す必要があると思うのです。
幕臣として権勢を得た松永久秀と「永禄の変」
以上、天野忠幸先生の研究成果に習い、松永久秀は三好長慶の忠実な側近であったとの評価を基準に妄想を広げてみました。
これに対して、旧来の評価とは異なるものの、松永久秀が永禄3年の御供衆就任以降、対幕府・朝廷交渉において従来の三好政権とは異なる立場を取り、京都政界において幕臣あるいは大和国の大名として独自の権力を築いたと評価する研究者もいます。
田中信司氏の「松永久秀と京都政局」では、松永久秀は幕臣としての活動を通じて、初めは対立していた将軍義輝とも、永禄6年の久秀と多武峰衆徒の和睦を義輝が仲介し、また義輝が娘を人質として預けるほどの信頼関係を築いていたとされています。
永禄4年には、三好長慶が幕府からの「御紋拝領」を辞退したのに対して、久秀は御紋と共に「塗輿御免」も受けていることから、長慶と久秀では幕府との距離感に相違があったという指摘もあります。
また幕府だけでなく、禁裏との関係においても、三好氏が永禄元年以前の三好政権期から引き続き禁裏とは疎遠だったことに比べて、松永久秀は永禄3年の御供衆就任以降、禁裏との交渉件数が格段に増えているそうです。
そして、久秀の京都における活躍が、フロイスによるあの有名な「天下すなわち『都の君主国』においては、彼が絶対命令を下す以外何事も行われぬ」という評価を形成したと見られており、説得力を感じます。
しかし、三好長慶がどんな理由で将軍との和睦を受け入れて、その後も将軍家との関係にどのような決着を目指していたのかという肝心なところが分からない限り、幕臣としての久秀の権勢が増大していったことが、果たして長慶の意向に反するものだったのかは判断できません。
更に妄想をたくましくして、長慶が(従来の評価通り)あくまで将軍の臣下に留まる心づもりだったと仮定した上で、久秀の幕臣としての活動もその意向に従ったものだとすると、義輝との協調関係を維持しようとする長慶・義興・久秀ら宗家側と、三好長逸を筆頭とする重臣層の間に緊張関係があり、義興と長慶の相次ぐ死によってそのバランスが崩れた結果が「永禄の変」を招いたと解釈できるのではないでしょうか。
阿波公方側の伝承では、永禄6年(1563)に足利義冬・義親(義栄)父子を周防から阿波へと呼び戻したのは三好長逸だったとされていますが、それが長慶の意志ではなかったとすると…その翌年に安宅冬康が殺害されたことを「逆心」によるものとする『言継卿記』の風聞も真実味を帯びてきます。
また「永禄の変」には、松永久秀の腹心の一人で当代一流の儒学者だった清原枝賢が従軍しており、その役割についてもよく分かっていません。(天野忠幸先生は、義継が易姓革命思想を背景に将軍殺害の正当化を狙ったものと推測されています)
これまで一般には、将軍義輝の殺害と阿波公方の擁立が、三好政権の総意であったかのように語られてきましたが、その裏では様々な思惑が交錯していたのでしょう。
「永禄の変」にはまだまだ検討の余地が多く残されています。
武衛陣町、将軍義輝の「武家御城」跡を歩く
「武家御城」と呼ばれた将軍義輝の御所は永禄2年(1559)8月、勘解由小路室町の斯波氏邸宅跡に建てられたもので、堀を備えた城郭でした。
現在「旧二条城跡」と呼ばれている足利義昭の御所は義輝の「武家御城」の跡に建てられたものですが、京都市営地下鉄烏丸線の建設に伴う発掘調査で、城跡の南内濠のすぐ南を東西に走る石垣のない堀跡が見つかっており、これが義輝期の堀と考えられるそうです。
これまで何度も京都を追われた義輝は父の義晴と同様、人夫を徴発して北白川城や霊山城といった洛外の山城を精力的に改築しつつ、相国寺などに今出川御所の留守番を命じ、洛中に将軍の御所が存在し続けることに尽力していたそうです。三好長慶との和睦による帰還を果たした後、この武衛陣跡に新たな御所を築城したのは、今度こそ将軍として京都に在り続けようという決意の表れだったのかもしれません。
しかし、フロイスの『日本史』には、三好方の襲撃を受ける前日のこと、身の危険を感じた義輝は近臣とともに密かに御所を脱出し、京都から亡命する決意を打ち明けたところ、反逆の証拠もないのに自ら臣下から逃れるようでは将軍としての威厳を失墜させてしまうと反対され、渋々引き返したと記されています。そして義輝の不安は的中し、油断しきっていた御所の人々は全ての門を開けたままにしていたため、すぐさま鉄砲を持った兵の侵入を許してしまったということです。
(見たんかい!と思わずつっこみたくなる程、ただの伝聞とは思えない詳細な描写ですが…どうなんでしょうね、『日本史』の信憑性って…)
なお、後年に三人衆方が六条本圀寺に将軍義昭を襲撃して逆襲を図った「本圀寺の変」で危機に陥ったことから、織田信長は自ら普請奉行を務め、義昭のためにこの地に新たな御所を築城しました。それがいわゆる「旧二条城跡」で、発掘調査では内郭と外郭の二重構造を持ち、南北が平安京の条坊制の三町分に相当する広さを持っていたことが明らかとなっています。また、安土城や兵庫城でも見られる胴木組を用いており、大量の石仏や石塔が石垣の材料として使用されていたそうです。
現在「武衛陣町」と呼ばれているこの地は、応仁の乱で朝倉孝景が主君の斯波義廉を守って東軍方を何度も撃退した戦跡であり、「永禄の変」で将軍義輝が最期を迎えた「武家御城」の跡であり、信長が義昭のために築いたいわゆる「旧二条城」の跡でもあるわけです。
武衛陣跡に建つ、平安女学院の校舎。
以下、第30回平安京・京都研究集会「室町将軍と居館・山城―権力・器量・武威―」にて「旧二条城」(足利義昭御所)跡見学会に参加させていただいた時の写真です。
京都市文化財保護課の馬瀬智光さんに解説していただきながら見て回りました。
この椹木町通が南内濠、義輝期の「武家御城」外郭に当たるそうです。
御苑の中にある復元石垣。これも地下鉄烏丸線の工事に伴う発掘調査で見つかった物です。
だいぶ読みづらい状態ですが、解説板には「織田信長が室町幕府最後の将軍・足利義昭のために造った強靭華麗な居城の跡と推定」とあります。うーん、強靭…??
配布資料より、武家御城(旧二条城)調査位置図
青い点線の枠が義輝期、赤い実線の枠が義昭期の御所と見られている範囲です。
アルファベットは濠跡が検出されたところですが、Gの部分を見て分かる通り、北西角と思われる濠は室町通よりも東に寄ったラインで見つかっていて、おおむね平安期の条坊に沿っているものの、正確な方形ではなく結構でこぼこしていたようです。
ちなみにGの濠跡の上は現在、110番指令センター等の施設がある京都府警察本部の敷地になっています。(これを建てる際の発掘調査で見つかったそうです)
西側は明治期に拡張された京都御苑がかなり食い込んでいて、遺構が埋もれているのは間違いないと思いますが、掘れる機会はないでしょうとのこと。(まあ、そうですよね…)
参考書籍、参考資料
- 若松和三郎『戦国三好氏と篠原長房』(戎光祥出版)
- 谷口克広『信長と将軍義昭 連携から追放、包囲網へ』(中央公論新社)
第30回平安京・京都研究集会「室町将軍と居館・山城 ―権力・器量・武威―」より
- 山田康弘「戦国時代における足利将軍の城館」配布資料
- 馬瀬智光「考古学から見た戦国期京都の防御施設」配布資料
伊予国・松山城は屏風折の高石垣がすごい!
連休で伊予国は道後に湯築城跡、そして松山城を訪ねてきました。
湯築城跡と河野氏にまつわる話はまた別の機会においといて、今回は松山城のすごい石垣を写真で紹介します。
近世になって建てられた城だし、初代城主は加藤嘉明か…そんなにときめかないなぁ…などと思いつつ、「坂の上の雲ミュージアム」を見るついでくらいのテンションで行ったんですが、これが予想外の感動がありました。
松山城の概略
松山城は勝山の山頂に本丸、中腹に二ノ丸、山麓に三ノ丸が設けられたいわゆる連郭式平山城で、築城したのはいわゆる賤ヶ岳の七本槍に数えられ叩き上げの武将として名高い加藤嘉明です。
伊予正木城10万石の城主だった加藤嘉明は、慶長7年(1602)、関ヶ原合戦の戦功によって10万石の加増を受け、藤堂高虎(仲が悪いことで知られる)とともに伊予半国の領主となります。そして勝山に新たな城を築くこととし、翌年に居を移すとともにこの地を「松山」と名付けました。
しかし、加藤嘉明は松山城の完成間近の寛永4年(1627)、お家騒動により減封となった蒲生忠知(蒲生氏郷の孫)と入れ替わる形で、会津40万石への転封を命じられてしまいました。(この転封は藤堂高虎の推薦によるものだそうですが…嘉明は感謝したのか恨んだのか…)
松山城は築城当時、五層の天守を持っていたそうですが、寛永11年(1634)に蒲生忠知が病没により断絶した後、桑名からの転封で城主となった松平定行によって、寛永16年(1639)から3年がかりで三層の天守に改築されています。
(五層から三層に改築された理由は、天守の安全確保のためだとか、幕府への配慮だとか諸説あるようです。)
しかし、9代松平定国の時に天明4年(1784)の元旦に落雷で天守をはじめ本壇が焼失、11代松平定通が文政3年(1820)に復興工事に着手したものの16年にして頓挫、12代松平勝善が弘化4年(1847)に城郭の復興を再開し、ようやく嘉永5年(1852)に天守をはじめ城郭が完成、安政元年(1854)に落成となりました。
大天守と小天守、隅櫓を連ねた連立式天守を備えた松山城は、このような経緯で幕末に完成されたため、我が国最後の城郭建築とも言われています。
幕末の動乱と松山城
親藩であった松山藩は幕末の動乱では二度の長州征伐で先鋒を務め、慶応3年(1867)に14代藩主となった松平定昭は老中に就任しますが1か月後には大政奉還、鳥羽伏見の戦いで朝敵とされ、新政府軍による追討令を受けました。
抗戦か恭順かで藩論は割れたそうですが、藩主定昭は恭順を決断、財政難の中で15万両を朝廷に献上して、蟄居謹慎の上すべての官位を返上、藩主も元藩主の勝成に交代したことで赦されました。また同年、源姓松平氏と葵紋を返上して菅原姓久松氏に復姓しています。
藩士たちの無念を思うと心苦しいですが、もし徹底抗戦していれば、今の松山城の姿はなく「現存12天守」に数えられることもなかったのではないでしょうか。
余談になりますが、「賊軍」松山藩の下級武士という立場から陸軍大将にまで上り詰めた秋山好古は、明治20年(1887)に騎兵大尉への任官後、旧藩主久松家の当主・久松定謨に伴ってフランスの陸軍士官学校で騎兵戦術を学びました。大正4年(1915)、秋山好古が近衛師団長に就任した際、近衛歩兵第1連隊長を務めていたのが久松定謨で、二人は「これで賊軍の汚名が晴らせた」と喜び合ったとのこと。
(久松定謨のお孫さん、久松定成氏の靖国神社崇敬奉賛会会長就任を祝う会で紹介された話だそうです。【靖国神社崇敬奉賛会会長就任を祝う会を開催】)
松山城本丸の紹介
本丸へは麓からロープウェイに乗って行きました。
ロープウェイから下りて本丸へ向かう途中、いきなり心を鷲掴みにされたのが、この高石垣です。
打込み接ぎの頑丈そうな石垣で、迫力があります。
こちらは太鼓櫓の石垣。
ここもいいですよ!
奥から天守がちらりと顔を覗かせる、中ノ門跡からの眺めもおすすめです。
途中で振り向いて。
石垣に登って、少し高いところから。
この門は筒井門。本丸へと向かう大手を固める最も堅固な門で、築城の際に正木城から移築されたと伝えられているそうです。
こちらは隠門といい、大手から攻め寄せる敵を急襲するための門だそう。
太鼓門。これに加えて太鼓門南続櫓、太鼓門北続櫓、太鼓櫓、巽櫓が石垣上に続けて構築されており、筒井門からの敵に備えているとのこと。
太鼓門を本丸側から見るとこんな感じ。
続櫓を本丸側から。
本丸に入ってすぐのところにある、井戸の跡。
本丸に入ってから天守の建つ本壇まで、結構距離があります。
素晴らしい眺めです…。
本壇に近付くとつい、天守に目を奪われてしまいますが…。
ここから見る石垣も忘れてはいけません。
小天守と南隅櫓。
天守の鬼瓦には葵の御紋。現存12天守の中で唯一の葵紋だそうです。
天守の中には解説パネルのほか、松山城と松山藩にまつわる様々な物が展示されていました。あまりじっくり見る時間はなかったのですが、以下印象深かった二品を紹介します。
(写真は北隅櫓と南隅櫓を連結する渡櫓、十間廊下)
加藤嘉明の物と伝わる甲冑です。嘉明といえば三角形のイカみたいな兜で有名ですが、これもなかなかおしゃれです。
嘉明と不仲だったという藤堂高虎は並外れた巨漢で有名ですが、対する嘉明はけっこう小柄だったようですね。
松山藩が新政府に恭順した際、松平勝成と定昭父子がこの書をしたためたそうです。
(ちなみに勝成は高松藩松平家から、定昭は津藩藤堂家からの養嗣子)
窓から覗いてみるのもよいです。
こちらは大手方面。
大天守の展望台から、道後方面。真ん中辺りに見える森が道後公園、湯築城跡です。
湯築城と比較すると、松山城がいかに巨大な城郭か分かるでしょうか。
大天守から、再び大手方面。
天守を出て、本丸から同じ馬具櫓を。
馬具櫓は松山城で唯一、鉄筋コンクリート製の建物だそうで、現在は管理事務所として利用されています。
馬具櫓から大手寄りの突き出たところから天守方面を見ると、屏風折の素晴らしい高石垣が見られます。
この本丸の壮大な石垣は、加藤嘉明の頃にほぼ完成されていたそうです。同じ加藤で一般によく知られる加藤清正も築城の名手として有名ですが、嘉明も引けを取りませんね。
他にも、松山城では山上の天守と山麓の居館(現在は二之丸史跡庭園になっています)を連結した「登り石垣」という珍しいものがあるそうですが、予習不足と時間不足で見ることができませんでした…。
おまけ
本丸へはロープウェイのほか、リフトでも昇り降りできます。なかなか気持ちいいですよ。
こんなところに鯉のぼりが(笑)
マスコットキャラクターの「よしあきくん」もお忘れなく。
顔出しもあります。
工事の看板も、加藤嘉明リスペクト!
嘉明は三河出身ですが、地元の英雄ではなくても最初に松山城と城下町を築いた領主なので、人気があるんですね。
近くにある松山東雲学園はプロテスタント系の女学校ですが、まるで松山城の一部のようなデザインが面白いです。
参考資料
- 松山城のパンフレット(かなり詳しいです!)
兵庫津遺跡と兵庫城 - 兵庫津遺跡第62次調査 第4回現地説明会の感想と兵庫津の歴史+α
さる3月28日、兵庫津遺跡第62次調査の第4回現地説明会に参加してきました。
前日の神戸市からのプレスリリースで「兵庫城の天守台か」と発表され、一部のニュースサイトには「信長の中国攻め拠点」との見出しで掲載されたものです。
兵庫城築城の経緯
兵庫城は天正8年(1580)7月に荒木村重の乱を鎮圧した戦功によって織田信長から摂津12万石を与えられた池田恒興が、その翌年に兵庫津に築いた城です。
享保17年 (1732)に記された『花熊落城記』には、荒木村重の乱における最後の戦いの舞台となった花隈城を解体し、その材料を転用したことが記録されているそうです。
九年の正月より池田勝入、此城を割給ふ。兵庫に屋舗を被成、此大石を此所へ引給ふ
池田恒興は花隈城の戦いにおいて、兵庫津から須磨一の谷までを焼き払って海上からの輸送路を断った上で、1年以上もの時間を掛けて兵糧攻めを行って、これを落城させました。
岡山大学が所蔵する池田文庫の「摂津国花隈城図」によると、花隈城は西国街道の北側に築かれていたそうで、恒興は自ら城攻めを指揮した戦いを通じてその弱点を熟知していたため、花隈城を破棄して兵庫津を守るための城を築いたのです。
兵庫城は主郭部となる本丸の周りに内堀と二の丸(帯郭)、外堀を巡らせるとともに、町の外郭にも「都賀堤」と呼ばれる堤防を築き、兵庫津全体の城塞化を進めたと伝わっています。
そのような経緯で西国に通じる要衝の軍事拠点として築かれた兵庫城でしたが、豊臣政権期の情勢の変化に伴って城郭としての機能は廃止され、元和3年(1617)には兵庫津が尼崎藩領となったことで、兵庫城跡には兵庫津奉行による支配拠点として陣屋が設けられました。
元禄9年(1696)に描かれた「摂州八部郡福原庄兵庫津絵図」に「御屋敷」と記されている場所が、築城時の兵庫城の主郭部に当たりますが、2012年に行われた第57次調査の際にも、ここで天正年間と推定される四段に積まれた野面積みの石垣が発見されていました。
今回の調査ではそれに続いて、本丸跡で天守台と推定される石垣が発見されたのです。
石垣は横幅1m内外の石で前後二重に構築され、それぞれの裏側には大量の栗石(ぐりいし)が充填されており、石垣の下には建物の不等沈下を防ぐための胴木(どうぎ)組によって築かれた非常に重厚な造りで、3mから5m程度の高石垣が存在したと推定されるそうです。
この胴木組は、織田信長が永禄12年(1569)に将軍・足利義昭のために築いた旧二条城や、天正4年(1576)に築かれた安土城でも発見されており、今回の発見はそれに次ぐ最古級のもので、兵庫城の築城にも信長による最新の築城技術が用いられていたことが明らかになったということです。
兵庫城跡の写真
以下、現地説明会で撮影した写真です。
遺跡の全景はこんな感じ。
列を作っている左側が本丸になります。二重の石垣があり、真ん中辺りの平坦な部分が内堀です。
胴木組の跡。
乾燥による傷みを防ぐため、定期的に霧吹きで水を撒いておられました。
石垣には一石五輪塔や石塔など多くの転用石が見受けられ、まさに乱世の城といった趣があります。
仏様のアップです。右側の石にも仏様が見えます。
さらにアップ。
このような墓石や石仏などからの転用石は、仏罰を恐れない信長の姿勢を表すものと捉えられがちですが、別に信長の城に限ったものではなく、戦国期の城には広く見られるものです。
栗石がたくさん。
転用石もゴロゴロと。
本丸跡には井戸も見つかっていますが、こちらも転用石だらけ。
こういう何気ない杭も、築城当時、あるいはそれ以前の建物の跡かもしれないとのことでした。
今回の石垣も天守台か?という形で発表したものの、当時の建物の記録が残っておらず、石垣の上の建造物についてはおそらく江戸時代に解体されたようで、瓦などはほとんど出土していないため、まだよく分かっていないようです。
説明会の際に専門家らしき方の話を立ち聞きしたんですが、築城当時に瓦葺きの天守なり櫓なりの建物があったとしても、尼崎藩領の時代に尼崎へ運び出されたのではないかと仰ってました。
出土品の写真もいくつか展示してありました。
以前の調査で近世の町屋跡も発見されているので、そこから出た物でしょうか。
奥の壁は明治時代に築かれた新川運河で、この掘削のために本丸跡の大半が破壊されてしまっています。
神戸港の開港によって貿易の中心地が東へと移動するに伴い、兵庫運河は工業地域としての隆盛を支えましたが、現在はウォーターフロントとしての開発が進められています。
ここで発掘調査が行われてきたのもその一環として中央卸売市場が移設されたことによるもので、調査が終われば遺跡の上にはイオンモールが建てられる予定です。
天正8年という戦国末期の築城当初の遺構が、住宅開発による破壊を受けることなくこのような状態で発見されるのは本当に貴重だそうで、担当の方も残念そうでしたが、できるだけ遺構を破壊せずに建ててもらうよう、イオンの方にお願いするほかないようです。
奥の建物が移転した中央卸売市場です。将来はここがイオンモールと接続される計画のようです。
建物の2階には食堂など一般客が利用できる店舗があります。
この看板もいつまで見られるでしょうか…。
新川運河のキャナルプロムナードには、兵庫城跡の石碑が建てられています。
説明板もありますが、かなり字が読みづらくなっている状態です。発掘調査が完了した暁には、その内容を盛り込んだものに新調していただけることを期待しましょう。
三好長慶と松永久秀と兵庫津 - 三好氏とともに成長した正直屋
兵庫津は平清盛が日宋貿易の拠点とした「大輪田泊」で、中世には勘合貿易の発着港として、あるいは畿内と讃岐や阿波を結ぶ短距離航路の要港として、東瀬戸内を支配した細川氏や三好氏にとって重要な拠点でした。
阿波を本拠地とする三好氏の畿内港湾都市との関わりでは、連歌や茶の湯など文化面でも先進的な役割を果たした堺との関係が知られていますが、三好長慶が摂津に勢力を拡げた天文年間は、堺よりも兵庫が重視されていたようです。
天文8年(1539)、長慶(当時は孫次郎利長)は河内十七箇所の代官職を巡る三好政長との対立から主家の細川晴元と交戦しましたが、六角定頼の調停を受けて和睦、晴元の麾下に入った長慶は8月に越水城の城主となり、摂津下郡郡代(事実上の摂津西半国守護代)としての権限の掌握を進めました。
兵庫津においても、天文9年(1540)末、正直屋の屋号を持つ捶井甚左衛門尉に宛てて買得地を安堵する判物を発給しており、その後も捶井氏の保護によって間接支配を進めています。松永久秀の名が史上に現れるのもちょうどこの頃で、『捶井家文書』には「松永弾正忠久秀」と記された副状が残されています。
買得の地所々の事、御知行全うあるべき旨、御折紙の上は、向後相違あるべからず、もし謂われざる族理不尽の催促等、これあるにおいては、相拘え御註進あるべし、御糾明をもって、仰せ付けらるべきの由候也、恐々謹言、
松永弾正忠
十二月廿七日 久秀(花押)
捶井甚左衛門尉殿
当時まだ30代前半と思われる久秀、すでに「松永弾正」を名乗っています。でもまさか将来本当に従四位下の位を受け弾正少弼に任官されるなんて、思いもよらなかったでしょうね。
兵庫津はかつて東大寺が北関、興福寺が南関を支配し、中央権門の管理下にありましたが、応仁の乱では西軍の大内政弘率いる大軍に制圧された後、 山名是豊率いる東軍の攻撃で焼き討ちされ、壊滅的な打撃を受けました。
(『応仁記』には、都の争乱から逃れて家領の福原庄に下向していた一条政房(兼良の孫)が、兵庫津にある福厳寺で東軍勢の乱入によって殺害されたという話も伝えられています。)
しかし、天文年間頃からは在地の商人が主導する港となり、三好氏の御用商人としての地位を得た捶井氏は、後に江戸時代にまで続く岡方・北浜・南浜という三つの自治組織のうち、岡方の名主を独占する程の豪商に成長したのです。
秀吉時代の兵庫津
兵庫城を築いた池田恒興は、賤ヶ岳の合戦後の所領再配置によって、わずか2年程で美濃へ転封となりましたが、その後に兵庫城へ入ったのは三好康長の養子となっていた秀吉の甥・三好孫七郎、後の関白秀次でした。
天正11年(1583)と推定される書状で秀吉は孫七郎に対して、兵庫城と三田城の受け取りに当たって兵庫に残って政道に専念するよう指示しています。
尚以其方事、兵庫ニ残候て政道已下堅可申付候、三田へハ人を可遣候
兵庫城・三田城両城可請取之由、得其意候、塩儀遣候て早々可請取候、猶追而可申越候、恐々謹言
筑前守
五月廿五日 秀吉(花押)
三好孫七郎殿
その秀次も四国平定後の天正13年(1585)に43万石を与えられて近江へ転封となり、兵庫津は秀吉の直轄領となりましたが、下代官として実際の支配を行っていたのはかつて三好氏の御用商人を務めた捶井氏の正直屋宗与で、秀次の時代から引き続き兵庫の諸座公事銭徴収に関わっていたようです。
兵庫津はその後も天正15年(1587)の九州平定、天正18年(1590)の小田原出兵、天正19年(1591)の朝鮮出兵の準備で兵站港として利用されますが、正直屋宗与は文禄3年(1594)10月に「地子役并町役之下代」を召し上げられ、以後は慶長5年(1600)の関ヶ原合戦まで増田長盛が代官を務めました。
その後、片桐貞隆(片桐且元の弟)が代官を務めましたが、江戸幕府が開かれた後の兵庫津は外交拠点へとその役割を変え、慶長12年(1607)、また尼崎藩領となることが決定していた元和3年(1617)にも、片桐貞隆が朝鮮通信使の接待を行った記録が残されているそうです。
近世の兵庫津と岡方惣會所跡
尼崎藩領の時代の兵庫津には町場の中心に西国街道が引き込まれ、陸運と海運の要衝として、城下町尼崎よりも多くの人口を抱える都市に発展しました。
岡方・北浜・南浜の自治組織は「方角」と呼ばれる個別町の連合体で、岡方は宿駅機能(陸運)、北浜・南浜の総称「浜方」が港湾機能(海運)を担当し、藩や幕府から課される諸役を請け負ったそうです。
方角ごとに数名の名主と惣代がおり、名主は家業との兼務で方角内の組頭中の入札によって選出される役人で、一方の惣代は専業で従事し方角から給銀を支給される役人でした。
そして昭和2年、正直屋が名主を独占したという岡方の会所跡に、兵庫商人の社交場として石造りの近代建築が建てられ、この建物は現在「よみがえる兵庫津連絡協議会」の活動拠点「兵庫津歴史館 岡方倶楽部」として利用されています。
岡方倶楽部の展示パネルより、兵庫津への航路を示した地図。
5つ描かれた城は兵庫津の左が明石城、兵庫津の右が尼崎城、尼崎城の下が大坂城、大坂城の左下が岸和田城、大坂城の右が高槻城です。
岡方倶楽部では「神戸・清盛隊」も活動されています。(この写真はちょっと古いですが…)
そういえば元々、大河ドラマ「平清盛」に合わせた観光PR事業「KOBE de 清盛2012」の一環で結成された「神戸・清盛隊」の活動拠点は、今回訪れた兵庫津遺跡の一角に建てられた歴史館でしたね。
岡方倶楽部で展示されているパネルは、当時この歴史館で展示されていたものです。
実は神戸・清盛隊のファンでもあるので、岡方繋がりで最後に無理やりねじ込んでみました。(笑)
参考書籍、参考資料
神戸市教育委員会 兵庫津遺跡第62次調査 現地説明会資料(第1回~第4回)
英賀城跡と本徳寺巡り(前編)『軍師官兵衛』が触れなかった英賀城と三木一族の歴史
英賀城は、夢前川の河口一帯に瀬戸内水運の拠点として発展し、本願寺の播磨における拠点となった本徳寺の寺内町として栄えた城郭都市です。
英賀を発展させた英賀城主・三木一族
戦国期に英賀城主を務めた三木氏は伊予河野氏の一族で、讃岐三木郡を相続したという河野通堯の子・通近を祖としています。しかし、河野氏側の系譜には三木氏との関係が記録されておらず、事実かどうかは定かではありません。
永享2年(1430)に飾東郡恋ノ浜城へと移った通近は三木氏を名乗り、『播州英城日記』は4代目の通武が嘉吉3年(1443)に英賀へ入部、12月から翌文安元年(1444)11月にかけて「芝」の地に居館を築き、同2年正月に移り住んだと伝えています。
三木氏以前の英賀は、鎌倉期に福井荘の地頭であった吉川氏の支配下にあったことや、永享年間に播磨守護赤松満祐の弟・常陸介祐尚が「英城」に居したことが、上郡町の宝林寺や法雲寺といった赤松氏ゆかりの寺院に伝わる文書に記されていますが、確かなことは分かっていません。
三木氏が英賀に進出したのは、嘉吉元年(1441)6月に赤松氏が将軍・足利義教を自邸で殺害するという前代未聞の事件を起こして幕府から討伐を受けた「嘉吉の乱」の終結から間もない頃ですが、三木氏はその間に初代から4代まで立て続けに交代しており、かなりの混乱があったことが窺えます。また、三木通武の母は赤松満祐の娘であったとも伝わっていますが、嘉吉の乱後に播磨を得た山名持豊(宗全)は三木氏の英賀進出を容認したようです。
亀山本徳寺がまとめた『播州真宗年表』によると、永享12年(1440)に関東で勃発した結城合戦に際して、三木通重が軍船40隻を率いて飾磨沖から赤穂の警固にあたったそうで、すでに相当な勢力を持っていたことが窺えます。また「三木氏は武家ではなく、英賀代官の統制下にあった裕福な交易業者であり、後に武士化したと思われる」と推測されています。
あるいは、永享年間に恋ノ浜城を拠点に赤松氏の下で水軍を統括していた三木氏が、嘉吉の乱を通じて山名氏に従い、赤松氏に代わって英賀城を占拠したとも考えられます。(英賀城主・赤松祐尚は嘉吉の乱以前に亡くなっており、後継者の則尚は乱の当時まだ10代でした)
享徳3年(1454)には、将軍・足利義政が赤松満祐の甥・則尚を赦免したばかりか、上意に背いたという理由で山名持豊に対して討伐軍を招集する事件が起きました。『播州真宗年表』によると、この際に山名氏による英賀侵攻の風聞を受けた三木通武は、大規模な築城工事を行い、南側に田井ヶ浜を城内深く引き入れて港とし、北側は十の出入口(広辻口、芝之口、駒芝口、井上口、大木口、河下口、北芝口、岡芝口、野中口、山科口)を土塁で結んで防備を固め、その外側にある沼沢地帯を濠(大木之濠)としました。岩を繋いだような強固な城「岩繋城」と呼ばれた英賀城の城域は、この頃にほぼ確定したようです。
なお、山名持豊の婿であった管領・細川勝元が将軍に従わず逐電したため山名討伐は中止されましたが、梯子を外される形となった赤松則尚は播磨に下向して旧臣達と共に挙兵します。翌享徳4年(1455)4月には山名氏の大軍が播磨に侵攻、赤松方も坂本城や壇特山に篭って抗戦したものの、山名是豊ら備後勢が篭もる室山を落とせず敗走した則尚は備前鹿久居島に逃れて自害、その首は赤松円心開基の法雲寺で晒されました。
(三木通武も赤松方として参戦したとの説もありますが、結局は山名氏によって許されたようで、経緯はよく分かりません。)
その後、長禄元年(1457)には南朝方に奪われていた神璽を奪回した功績により、赤松満祐の弟義雅の孫・政則を当主として再興が認められた赤松氏は、応仁・文明の乱において東軍方として活躍し、播磨の奪還に成功します。三木氏5代目の通安は当初、西軍山名氏に従って大内・河野軍を先導し20隻の軍船を率いて摂津に出向したものの、後に東軍赤松氏の麾下に入って武功を上げ、従四位下宮内少輔に任ぜられました。
その水軍力を武器に山名氏と赤松氏の間で巧みに立ち回り、英賀城を発展させた三木通安は、北方の山崎山に初代通近から四代通武までの頭首とその妻の墓を建てました。そして三木一族は城内に市庭家、井上家、土井家、堀内家の「四本家」と山崎家、薮内家、町之坪家の「三連家」がそれぞれ居館を構え、七家の合議によって英賀の町を運営したと伝えられています。
播磨における本願寺の興隆と「英賀御堂」本徳寺
英賀城を発展させた三木氏は浄土真宗本願寺に帰依し、本願寺一家衆を本徳寺に迎えることで、やがて「英賀門徒」と呼ばれる強力な門徒集団を抱えるに至ります。
西国においては仏光寺系の布教が先行していたようですが、明応年間には「播磨六坊」(円光寺、光善寺、永応寺、万福寺、光源寺、光触寺)に代表される各地の寺院が次々と本願寺の系列に入り、中には天台宗や禅宗から転派する寺院も現れるようになります。
江戸中期に三木知識が編纂したという『姫路船場本徳寺開基略』は、蓮如の命を受けて播磨へ下向した弟子の法専坊空善によって、明応2年(1493)2月28日に道場が開創され、蓮如により英賀東「苅屋道場」に本尊が授けられたと伝えています。
また『播州英城日記』よると、三木氏6代目の通規が英賀城主を務めた永正年間にはますます「専念一向宗」に帰依する者が増えたため、やがて門徒の中で一家衆(宗主の一族)を迎えたいとの声が高まり、永正9年(1512)8月には天満九郎四郎近村が上京して本願寺に参じて一家衆の下向を懇請した結果、実如上人はこれを受け入れました。
『栄玄聞書』には、この頃の播磨では守護赤松氏が怨みにより一向宗を禁止していたところ、実如上人が秘蔵の名馬「ちゞみ栗毛」を赤松氏へ贈ったことにより、禁制が解かれたというエピソードが記されているそうです。
実如上人御代に、御馬五十疋仙飼候、其中にちゞみ栗毛と申御馬、御秘蔵の名馬にて候。然ば播磨の国赤松[是は備前、はりま、みまさか三ヶ国の守護也]このちゞみ栗毛の事を承り及び、上野[蓮秀と云云]まで度々所望の由申入られ候へども、蓮秀御耳にもたてられず候、其故は、御秘蔵の御馬にて候あひだ、中々くだされまじきと存ぜられ、申あげられず候
…中略…
総じて赤松と申ものは、御一宗に怨をなし、播磨一国の門徒の者に、念仏をさへこゝろやすく申させぬ者にて候、播磨一国の尼入に、こゝろやすく念仏をも申させ、仏法をも聴聞させ候はゞ、たとへば御身をうらるゝともおしからずと、思召候と御意候、この仰せを御前の人々承り、数剋落涙のよし候、さて御馬をば京へ引こさせられ、赤松へくだされ候、赤松悦喜申され候事、是非なく候、すなはちこれより、播磨一国の仏法こゝろやすくひろまり申候なり
このような実如上人の意志により、まず永正9年(1512)に五子の実玄が英賀本徳寺に入寺したものの、永正12年(1515)3月に夭逝したため、その後は三河土呂本宗寺の住持であった六子・実円が英賀本徳寺を兼帯することになりました。永正10年(1513)9月2日、芝之館において実円と対面した英賀衆「七家」をはじめ89人が剃髪し、浄土真宗の歓化を受けたと伝えられています。
また『播州英城日記』によると、永正10年(1513)2月には東西一町、南北二十間の地を定めて坊舎の建築が開始され、2年後の永正12年(1515)6月2日には南北九間、東西七間という規模の「英賀御堂」が完成、翌日から七日間の遷仏法要が営まれるとともに、実円より七家以下各分家へ蓮如直筆の六字名号(「南無阿彌陀佛」と記した掛け軸)五十余軸が授与されました。
大永5年(1525)に実如上人が没した後、実円は後継者となった証如の後見役として大坂本願寺にいることが多かったようですが、英賀へも何度か下向しており、天文6年(1537)頃には播磨へ進出した尼子氏の動静を証如に伝えるなど、政治的な面でも本願寺教団の重鎮として活躍しました。
(実円の報告を受けてか証如は尼子詮久に宛てて「御出張の由承り候、ことに早速御本意に属し候条珍重に候」とその進出を祝う書状を送っています。)
また、戦国期の本願寺は各地の門徒を御堂番として上山させていましたが、播磨門徒でも天文7年(1538)以降およそ年2回、万福寺、播磨衆、英賀衆というグループに分かれて御堂番を勤めたほか、証如上人の日記『天文日記』には英賀の俗人門徒である英賀徳正、すみや甚兵衛、英賀市場与三兵衛、英賀丈重新衛門らの死去や年忌に際して、遺族が本願寺へ斎(仏事における食事)の調進を行ったという記録が残されており、信仰活動の中にも英賀衆の経済力が窺えます。
英賀城主・三木氏は自ら門徒となることで「英賀御堂」本徳寺を中核とした阿弥陀信仰を共通の精神基盤とし、地縁的共同体の統率者として強固な関係を築きますが、英賀と本願寺の強い繋がりは、やがて畿内の覇者となった信長との間に勃発する「石山合戦」に強く影響を受けることになります。
『軍師官兵衛』が触れなかった姫路時代の黒田家と英賀の関係
大河ドラマ『軍師官兵衛』では主君・小寺政職を説き伏せて信長方となった官兵衛が、海上から攻め寄せる毛利氏の水軍を撃退したという天正5年(1577)5月の「英賀合戦」において、侍女のうち何人かが本願寺門徒であったため官兵衛の元を離れて英賀本徳寺に駆け込み、敗戦後再び黒田家を頼った末、侍女の1人「お道」が栗山善助の妻になるというストーリーが描かれました。
しかし、実際の黒田家と英賀の関係はもっと深いもので、『寛政重修諸家譜』によると官兵衛の姉妹に当たる黒田職隆の長女が英賀城主・三木氏の元に嫁いでおり、官兵衛が母里一族24人の戦死という犠牲を払いつつ辛勝したと『黒田家譜』が伝える永禄12年(1569)8月「青山合戦」では、三木氏も小寺方として援軍を送っています。
また、英賀本徳寺の後身である亀山本徳寺には、英賀城主・三木通明と見られる「三木宗太夫入道慶栄」が永禄9年(1566)5月に英賀本徳寺へ寄進したという梵鐘が伝えられていますが、この製作者である芥田五郎右衛門尉家久は姫路城近くの野里村に在住して播磨鋳物師を統括した人物で、永禄12年(1569)8月22日には小寺政職から弟の善五郎と共に青山面における戦功を賞する感状を与えられており、同じ小寺氏の被官として、黒田氏とも親しい関係にありました。
芥田五郎右衛門は個人的にも官兵衛と親しかったようで、後に福岡時代の官兵衛から五郎右衛門に宛てて、池田輝政が発展させた姫路城下町の繁栄ぶりを喜ぶ内容の書状が残されています。
姉妹の嫁ぎ先でもありかつて良好な関係を築いていた英賀を攻撃目標とする「英賀合戦」は、主家の小寺氏ともども生き残るため織田方に付いた結果とはいえ、官兵衛にとって辛い戦いだったのではないでしょうか。
ちなみに「ひめじ大河ドラマ館 かわら版」によると、亀山本徳寺では『軍師官兵衛』の英賀合戦に際して、毛利軍の大将・浦宗勝が英賀御堂に本陣を構えるシーンと、本願寺に顕如をはじめ僧侶が念仏を唱えるシーンが撮影されたそうです。
その際、書写山圓教寺のお坊さんが僧侶役のエキストラとして参加したそうですが、旧仏教である天台宗は当時の新興宗教であった本願寺教団を目の敵にしていたため、『播州英城日記』には書写山の僧徒がたびたび英賀に攻め込んで死者が出る争いになったことが記されており、大永5年(1525)には僧徒によって強奪された鐘を英賀衆が山崎辺りで取り戻すという事件も起きています。
カンペを見ながら違う宗派のお経を読んだというお坊さん達は、ご存知だったでしょうか…。
英賀城跡を巡る
英賀城跡の遺構はほとんど残っておらず、十口の城門跡に石碑が建てられているものの、三木通武が築いたという「岩繋城」の姿は現状からはなかなか想像できません。ですが、実際に歩いてみることでその広さを実感することはできました。
山陽電鉄西飾磨駅前にある史跡地図。「付城公園」「清水公園」「矢倉公園」といった公園にも当時を偲ぶ地名が残っています。
付城は織田勢を警戒した三木氏が築いた出城もしくは、秀吉が英賀城攻略の際に築いた付城の跡と考えられます。
清水はおそらく秀吉による英賀城攻略の際に最前線となった「清水構」で、ここには宮部善祥坊が配置されていたと伝わっています。
現在の水尾川。英賀城は東に水尾川、西に夢前川が天然の堀を形成していました。
「城内に 眠り一村 水ぬるむ」
広辻口は英賀城の十口の一つで、水尾川に面した東側に当たります。
本丸跡に建つ石碑と復元図。上が南です。
英賀城は本丸と二ノ丸が随分と東に偏っていますが、この近くには「芝之口」や「駒芝口」があり、おそらく英賀へ入部した三木通武が最初に築き、英賀衆が実円と対面したという「芝之館」が二ノ丸もしくは本丸の原型だったと思われます。
「田井ヶ浜 おぼろがつゝむ 英賀城史」
三木通武が南側に港を引き入れたという田井ヶ浜の跡。落城後荒れ果てていたというこの地を清めた熊谷家が地蔵尊を祀り、英賀神社の辰巳の方角に当たるため「巽地蔵」と呼ばれるようになったそうです。
田井ヶ浜跡の碑文には「天正四年(一五七六) この地は毛利水軍五千人の上陸地」とありますが、この年次は『黒田家譜』による誤伝で、実際には天正5年(1577)5月のことです。
夢前川にかかる山陽電鉄の鉄橋。山陽電鉄の線路辺りが英賀城の南端になりますが、ちょうどこの辺りには英賀津の船溜まりがあったようです。
なお、現在の夢前川は昭和13年の日本製鐵広畑製鐵所の建設に伴う付替工事のため、かつての流路から東に大きくずれています。
夢前川にかかる歌野橋より。夢前川の付替工事によって川底に埋まったという本徳寺跡地は、歌野橋上流約100mの河川敷中央辺りにあったそうです。この辺でしょうか?
歌野橋を渡って夢前川東の堤防を少し北上したところにある「英賀本徳寺(英賀御坊)跡」の案内板と、天正5年の英賀本徳寺建物配置復元図。かつてこの地には「御坊」という字名が残っていたそうです。
本徳寺跡にある英賀城跡区域復元図は、現在の地図の上に土塁や堀が重ねて描かれ、館跡や十口の位置も記入されていて分かりやすいです。
これを見ると、まさしく現在の夢前川の真ん中にかつての本徳寺があったことが分かります。
明蓮寺は永正14年(1527)に三木通規の家臣である神出左衛門の母・妙蓮尼によって建立され、秀吉による寺内町解体後も唯一この地に残った寺院です。ここには石山合戦期に顕如から英賀惣中に宛てた書状が伝えられていますが、それは次回に紹介します。
昭和3年に英賀青年会が建立したという石碑はかつて本徳寺跡にあったもので、夢前川の付替工事に伴って明蓮寺の境内に移設されました。
なお、周りには北条(北條)さん宅が多かったのですが、明蓮寺の斜め向かいには三木さん宅がありました。(三木氏の末裔の方でしょうか…?)
「英賀御坊ハ今ヲ去ル四百三十七年明應元年蓮如上人ノ開基ニシテ播州真宗發祥ノ霊地ナリ」 昭和3年当時はこのように伝承されていたようです。
英賀神社は英賀彦神、英賀姫神を主祭神とし、播磨風土記にも英賀の地名はこの神名に因ることが記されているそうです。英賀城下に本徳寺以下35ヶ寺を数える中、唯一の古い由緒を持つ神社であったようです。
英賀神社には永禄10年(1567)に三木宗太夫慶栄が寄進した英賀本徳寺鬼瓦や、英賀落城の2年後に当たる天正10年に薬師入道道定が撰述したという『播州英城日記』が伝えられています。
奉納された玉垣には「付城」「矢倉東」「清水」「山崎」といった町名が多く見られましたが、あるいは英賀城の戦いに縁ある方々かもしれません。
英賀神社は絵馬堂もなかなか見応えがあります。
中には東塚嬉楽と門人らによる「算術自問答」なる奉納額も。算額というやつですね。ずいぶん新しく見えますが、復元されたものでしょうか。附城村の三木さん三名も名を連ねています。
英賀神社の本殿裏には英賀城の土塁跡が残されています。
英賀城跡公園には復元された石垣(?)があります。『播磨灘物語』の文学碑が英賀神社境内に建立され司馬遼太郎が訪れた際、地元で英賀城を見直そうという運動が盛り上がったそうですが、その際に整備されたものでしょうか。
「花万朶 三木十代の 城の址」
英賀城跡公園には十口の一つ、野中口の石碑も。復元図によると付近には「北野中館」があったようです。
十口の一つ、山科口の石碑。ここは北西の角に当たり、現在「矢倉公園」の敷地になっています。この辺りには英賀城の櫓が建っていたのでしょうか。
十口の一つ、岡芝口の石碑。
十口の一つ、河下口の石碑と、北側土塁の外に当たる沼沢地帯を濠としたという「大木之濠」の石碑。大きな交差点の歩道にあります。
「水田にビルが立ち野が枯てゆく」という歌が物哀しさを漂わせていますが、これより北の沼沢地帯は後に水田として利用されていたのでしょうか。復元図を見たところ、この石碑自体も建物の建設により移動されているようです。
英賀薬師(法寿寺)の跡。法寿寺は延宝9年(1681)に三木氏の後裔古今によって中興創建された寺院で、浄土宗知恩院幡念寺の末寺だったそうです。浄土真宗に帰依したはずの三木氏がなぜ浄土宗に?
英賀薬師跡には英賀城主・三木氏一族の墓所があります。延宝9年(1681)山崎山に亀山本徳寺西山御廟が建立されることになったため、同所にあった一族の墓所をこの地に移転したそうですが、当時の亀山本徳寺と三木氏の間で何かあったのでしょうか?
東本願寺派である船場本徳寺の視点による本徳寺の由緒記『船場本徳寺開基略記』をまとめたのが「三木通識」というのも気になります。三木一族も本願寺東西分裂の影響を受けたのでしょうか…? (疑問は尽きませんが、「石山合戦」での英賀城の動向と後の本徳寺分裂については次回に紹介します)
「俗名越智姓三木右馬頭通近」とある通り、こちらは初代三木氏となった通近の墓のようです。河野氏の本姓は越智のためそれに習っているのでしょう。
最後の城主となった三木通秋は秀吉による英賀落城時に船で脱出し、2年後に許されて英賀へ戻ったと伝えられていますが、河野に姓を改めて帰農した人もいるそうです。この方はその末裔でしょうか。
英賀薬師跡の北側には僅かながら土塁跡が残されています。
英賀薬師跡のすぐ傍には赤松義村が定めたという「播磨十水」の一つ、「大木之清水」の石碑と井戸の跡が残っています。この井戸は通称薬師の湯と呼ばれ、昔から「薬の井戸」として親しまれてきたそうです。
十口の一つ、井上口の石碑。復元図によると付近には七家の一つ井上家の館があったようです。
英賀薬師北側の土塁跡に沿って東西に小さな溝が残っており、水尾川まで延びていますが、地図を見たところどうやらこれも堀跡のようです。
参考
播磨佐用郡の山城・利神城の歴史と伝説
利神城跡は佐用郡佐用町平福にあり、標高373.3mの山頂に総石垣作りの威容を誇り「雲突城」とも呼ばれたという山城の遺跡です。
利神城を築いた佐用別所氏
一般に別所氏といえば、赤松政則を支えて東播磨八郡の守護代を任された三木城主・別所則治と、その後裔である別所長治の三木別所氏が知られていますが、別所氏の諸系図では河西郡別所村から三木郡に移った赤松季則の二男頼清を別所氏の始祖とし、赤松圓心の弟「別所五郎入道」圓光がその名跡を継いだとしており、圓光から則治までの系譜は諸説あって定かではありません。
佐用郡歴史研究会が『佐用の史跡と伝説』にまとめた「別所氏略系図」には、貞和5年(1349)に別所五郎左衛門敦範が佐用郡豊福を賜って豊福構および利神城を築城した後、持則、則康、祐則と続き、祐則の五男・小二郎則治が三木城主となって別所家を再興、祐則の二男・五郎蔵人光則が利神城主を継いだものの、子の小太郎治光とともに嘉吉の乱で伊勢にて討死、その子日向守治定が応仁元年(1467)に利神城を再興したとされており、これが佐用別所氏の流れになります。
また『佐用の史跡と伝説』には、日向守治定の後、日向守静治、太郎左衛門定道の代に至り、天正5年(1577)に秀吉による侵攻を受けた際、定道は人質を出して和を乞うたものの、病弱の定道に代わって城主となった日向守林治は秀吉に反抗したため、天正6年(1578)正月に上月城に入っていた山中鹿介幸盛に攻められ落城したと記されているそうです。
秀吉の佐用侵攻については長浜城歴史博物館が所蔵する下村文書に秀吉自身が詳細を綴った書状が残されており、その中で秀吉に敵対する3つの城として福原城、「七条と申す城」上月城、そして「別所中務と申者之城」利神城(あるいは麓にある居館の別所構)が挙げられ、別所中務が降伏を願い出てきたため人質を3人召し取った上で翌年2月まで城を預けたと記していますが、佐用別所氏のその後の動向は明らかではありません。
(秀吉による上月城落城の悲惨な戦いについては 上月城の戦い第一幕・秀吉の播磨侵攻 で記事にしています。)
通説では、天正8年(1580)には赤穂郡・佐用郡を領した宇喜多秀家が家老の服部勘介を利神城主として両郡を支配させたものの、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦で宇喜多氏が西軍に与して敗れたため、服部勘介も城を退去したとされていますが、『浮田家分限帳』に記された宇喜多氏家臣団の中には服部勘介に相当する人物が見当たらないようです。
利神城を改修した築城の名人・池田由之
関ヶ原合戦の後、佐用郡は姫路城主となった池田輝政の領するところとなり、輝政の甥である池田由之(小牧・長久手の戦いで父とともに討死した輝政の兄・之助の子)が利神城主となりました。
由之は慶長5年、遺構を打ち崩して石垣を積み上げた城郭を造り始め、慶長10年にこれを完成させます。三層の天守に二の丸、三の丸、鵜の丸、大阪丸といった曲輪に回廊を巡らせた壮大な城で、山上にそびえ立つその姿は「雲突城」とも呼ばれたと伝えられています。
『佐用郡誌』には以下のようなエピソードが記されています。
池田出羽守利神城主となり大いに加修造營三重の天守を築き城山の西方に諸士の屋敷を設け、又口長谷構の別荘を美にし大いに奢る。 偶々輝政此地に來らんとせしに釜須坂を越えし時其城郭を遠望し其美なるに驚き異圖あるものとし入城せずして釜須坂より直ちに姫路に引返す。 而して慶長十年の頃天守の破壊を命じ、且慶長十二年出羽守を退去せしめ輝政弟池田河内守長政をして代らしむ。
由之が自身の居館を華美に装飾した上、三層天守という大城郭を建ててしまったため、これを見た輝政は由之が良からぬことを企んでいると考えて姫路に引き返し、天守の破却を命じた後、城主を交代させたというのです。
これらの話は安永8年(1779)に記された『播州佐用郡平福古城由来』という記録が元だそうで、このような伝説や通説の類が示す通り、現存する利神城の遺構は全て池田由之によって普請されたものと考えられてきました。(『日本城郭大系』でも同様の記述が見られます)
しかし、城郭談話会の精査によって1993年にまとめられた『播磨利神城』では、遺構の築城法から織豊期のものと推定されており、石垣の角石や角脇石の使われ方も天正年間の普請と見られるほか、城跡に残っている瓦片に天正11年以前の製造法によるものが多数含まれているそうで、池田氏以前に瓦葺きの建物が存在していたことは間違いないようです。
また『佐用郡誌』が記す「又口長谷構の別荘」=別所構の発掘調査によると、出土遺物の大半が15世紀後半から16世紀後半のものであり、由之が城主の頃に「美にし大いに奢る」様子を示す物は発見されませんでした。
由之が輝政の一家臣であることに不満を抱いていたという伝承も誤りで、池田家の記録によると由之の地位は高く、備前下津井城や伯耆米子城など領内の重要拠点の普請に携わっただけでなく、駿府城、篠山城、名古屋城の普請にも派遣されているそうで、なかなかの築城名人であったようです。
元和4年(1618)に江戸から米子へと帰る途中、大小姓の神戸平兵衛の逆恨みによって刺殺されるという不幸な最期を迎えましたが、3人の子は岡山藩、鳥取藩、徳島藩で家老を務めています。(徳島藩については由之の正室・即心院が蜂須賀家政の娘であったため)
姫路から訪ねてきた輝政おじさんが遠く峠からこの城の威容を見て驚いて引き返したという伝説も、どこからつっこめば…という感じで面白いのですが、由之の名誉のために補足しておきます。
2010年3月に利神城跡へ登った時の回想
以下の写真は、2010年3月に利神城跡を訪れた際に撮影したものです。
当時は登城口への案内看板があり、ここから石垣を確認することができました。
「利神城跡」の看板に誘われつつ、線路の脇から目の前の山に登っていきます…。
※「利神城跡は、城郭の一部が破損し、大変危険な状態になっていますので、登山はご遠慮ください。 佐用町」との立て看板がありましたが、遠慮しませんでした…とにかく状況を自分の目で確かめて、本当に危険そうならそこで引き返そうと…。
尾根沿いの登山道からは佐用川と旧宿場町・平福の町並みがよく見えます。川屋敷と土蔵群の景観は有名ですが、この当時はまだ前年の台風9号と洪水の被害を受けて、復興の最中でした。
かつてハイキングコースだったという名残りが、そこかしこに見られました。
木々の間を抜けきると、山頂の石垣が目の前に見えてきました!
平福の町並みも段々小さく…。
尾根を登り切ったところで、二重に積まれた石垣群がはっきりと見えてきました。
大手口となる三の丸からの眺め。頂上にある曲輪が三層天守があったという「天守丸」で、その一段下が天守丸の虎口がある「本丸」です。
五角形の天守丸と本丸の石垣が格好良い! たまりません…。
三の丸から二の丸にかけて、足元にはかなり大きな石が散乱しています。城郭の破損というのはこのような状態のことだったのでしょうか? しかし天候も問題なく、ここで引き返そうとは思いませんでした。
登ってきた三の丸方面を振り返ります。
天守丸の真下から。
利神城の石垣と眺望の雄大さは、人気の竹田城にも決して引けを取らないものだと感じました。
ここで、道の駅ひらふくで購入していた「佐用特産 じねんじょまんじゅう」を取り出します。
このロケーションで食べる、おまんじゅう…最高でした!!!
更に石垣を見て回ります。
木が切り倒された様子もありますし、整備には来られていたのでしょうか。
鵜の丸側の景色も素晴らしいです。この時から4年を経た今でも、思い出すと当時の感動が蘇ってきます。
本丸の様子。
登山道自体はそれほど険しいものではないので、地元では良いハイキングコースだったんでしょうね…。
まだまだじっくり堪能したいところでしたが、この後は上月城に向かう予定がありました。本数が少ない智頭急行に乗り遅れると大変なので、別れを惜しみつつ下山しました。
少しだけ佐用川沿いを歩いてみましたが、まだ洪水の痛々しい爪痕が残っていました。
佐用川から仰ぎ見る利神城。
2014年12月現在、山上の城跡がどのような状態なのかは分かりませんが、佐用町からは登城を遠慮するよう案内しているのは変わっていないようです。その後も台風や大雨がありましたし、更に石垣の崩壊が進んでいることと思います。
史跡の中でも特に高地にある山城の遺跡は、遺構の現状を維持するだけでも大変でしょう。まして訪問者の安全に配慮した整備が求められるとなれば、とても困難なのだろうと思います。
しかし、これほどの素晴らしい石垣がただ朽ちていくのはあまりに惜しいです。何とか保存の道を探っていただきたいものです。
参考
- 朽木史郎、橘川真一編著『ひょうごの城紀行 上』(神戸新聞総合出版センター)

- 作者:
- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター
- 発売日: 1998/04
- メディア: 単行本
尼子詮久の東征(上洛戦?)から郡山城攻めに至るまで
天文年間の尼子氏による上洛戦とも思われる東征については、侵攻を受けた赤松氏や浦上氏の側から触れてきましたが、今回は尼子氏の側から見た流れをまとめてみます。
畿内の混乱と西国の情勢
この頃の畿内では、天文元年から5年にかけて、細川晴元政権の内訌に端を発した本願寺門徒と法華一揆による大混乱の真っ最中で、一時は晴元も本願寺門徒の一揆勢に敗れて淡路へと逃れるほどでした。
また晴元政権では、晴元と本願寺の和睦を仲介したという三好千熊丸(後の長慶)ら阿波三好一族や、その後ろ盾となっていた讃岐および阿波守護・細川持隆との勢力争い、河内および紀伊守護・尾州家(政長流)の畠山稙長と総州家(義就流)の被官で細川晴元の寵臣として権勢を振るった木沢長政の争いなど、たびたび内部抗争を繰り返しており、将軍義晴も元々は細川高国政権において近江守護・六角定頼の協力により擁立されたこともあってか、細川氏を頼みとせず近江へと逃れることがありました。
畿内情勢の混乱を見た豊後の大友義鑑は、将軍義晴の京都帰還を名目とする上洛を計画しており、天文元年には将軍入洛への馳走を大内義隆の悪行によって妨げられているとして、尼子氏および安芸武田氏、熊谷氏、伊予河野氏、宇都宮氏、能島村上氏らに大内氏包囲網の形成を呼びかけました。
大友義鑑書状(切紙、熊谷家文書)
就江州 公方様御入洛之儀、度々被成 御下知候之条、相応之忠儀、無余儀存候之處、依大内造意、干今相滞候、近日猶以悪行令顕然之条、近々豊筑発向之覚悟候、然者、連々如申談候、其堺之儀、無油断御調儀、併可為御忠節候、武田光和・尼子経久別而申合候、海上之事、河野通直・宇都宮・村上宮内大輔申合候、猶小笠原刑部少輔方可被達候、恐々謹言
七月廿日 義鑑 (花押)
熊谷民部少輔殿
(川岡勉先生の講演『尼子氏の勢力拡大と中央政界』配布資料より)
しかし、尼子氏はこれに応じず、独力で東征を開始します。
その背景には、尼子氏では享禄3年以来続いた尼子経久の三男・塩冶興久の反乱によって出雲国内を二分する内乱状態に陥っており、一方の大内義隆も北九州で大友・少弐氏と戦っていたため、相互不可侵協定を結んだことがあったと見られています。
(これに伴い、享禄4年7月10日付で経久嫡孫の三郎四郎(詮久)と元就が兄弟として協力するとの契約を結んでいます。)
尼子詮久の備中・美作への侵攻
天文元年(1532)5月、備中新見荘の代官・新見国経が領主である東寺へ送った書状によると、尼子氏は美作高田城を本拠とする三浦氏への攻撃を進めており、かねてより尼子方であった新見氏にも協力が要請されています。
この時すでに齢七十を越えていた尼子経久に代わって軍を率いたのは、嫡孫の詮久でした。
永正13年(1516)10月19日付の新見国経の書状によると、新見氏は備中守護・細川氏や備中の国人三村氏、多治部氏らの圧迫に対して、伯州、雲州衆と提携して対抗しており、この頃には尼子勢が美作への進出経路となる備中北部へと勢力を拡げていたと見られます。
尼子勢は天文元年からの侵攻で三浦氏の居城勝山城を攻略したものの、天文2年(1533)6月23日付の新見国経の書状に「伯州東半国と作州一国申し合わせ、尼子方に敵となり候」とあり、応仁・文明期の伯耆守護山名家分裂による内乱以来、美作の国人と結び尼子方に付いていた東伯耆の南条氏や小鴨氏が敵対したことで苦戦を強いられました。
天文2年(1533)12月には詮久が美作二宮(高野社)の社人注連大夫に安堵状を出しており、同年中には美作中央部まで進出していたことが窺えますが、天文5年末に亀井安綱から近江の小谷城主・浅井亮政に宛てた書状で、備中・美作が「両国悉く落去」したと報じており、美作の平定には足掛け5年が費やされたようです。
また、この時すでに「明春は早々播州えその働きいたすべく候」と伝えていることから、早くから播磨への侵攻を予定していたことが窺えます。
「尼子十勇士」の一人として名を知られる秋上庵介の本家で、神魂神社の神主を務めたという秋上家に、天文5年10月10日付、詮久自筆の和歌が残されています。
あきあけは とみとたからに あひかして おもふことなく なかいきをせむ
備中・美作両国の平定を終えた状況で、その心境を詠ったものでしょうか。
尼子詮久の播磨進出と竹生島奉加
尼子詮久は天文6年11月に播磨へ侵攻、証如が詮久に送った書状には「御出張の由承り候、ことに早速御本意に属し候条珍重に候」とありますが、「本国にて越年すべき由」と記しており、この時は年末までには帰国したようです。
天文7年(1538)に経久の隠居により家督を継いだ詮久は、再び本格的に播磨侵攻を開始します。
実際に尼子勢が攻め込んだのは同年9月下旬のことですが、7月にはすでに播磨守護・赤松政村が高砂に没落したという噂が京都で流れており、詮久が上洛するかどうかが取り沙汰されています。播磨国内は「正体なき式」となり、赤松政村は淡路に没落、11月には別所村治が三木城に包囲を受けましたが、攻略には至りませんでした。
また天文8年10月には、尼子勢は赤松政村の要請を受けて備中に渡海した阿波守護・細川持隆の軍勢を撃破しています。
(天文8年に浦上政宗が室津で尼子勢を迎え撃ったというのも、この頃のことでしょうか。)
播磨國美嚢郡の法光寺には、対外交渉の窓口を担当したという湯原幸清の天文8年(1539)12月25日付の禁制が残されており、すでに尼子氏の勢力が播磨東部に及んでいたことが窺えます。
尼子氏の快進撃の背景には、畿内における旧高国党や畠山稙長、紀伊湯河氏などと連携の動きもあったようです。
本願寺宗主・証如上人の日記『天文日記』天文七年八月十四日条には、以下のような内容が記されています。(尾州=政長流畠山氏、畠山稙長)
従湯河宮内少輔以書状、就尼子出張尾州被出候間、彼人も可上洛候、然者得指南候ハんよし申候
(川岡勉先生の講演『尼子氏の勢力拡大と中央政界』配布資料より)
また、尼子氏の主家に当たる京極氏を擁立していた江北の雄・浅井亮政からも、竹生島の造営経費に対する奉加の要請を受けていますが(天文9年8月19日付、竹生島造営奉加人数書上)、これ以前の天文7年(1538)9月に国友河原の合戦に敗れるなど、浅井氏は六角定頼との戦いに苦戦しており、上洛を目指す尼子氏との連携を目論んでいたものと思われます。
播磨国内に滞在していた尼子勢は天文10年初頭には撤退することになりますが、同年に京極高延が亮政に反旗を翻し、浅井亮政は天文11年正月に死去、その後継者となった久政が六角氏への臣従を選択したことも、何か象徴的に感じます。(尼子贔屓の引き倒しでしょうか?)
余談:安芸宍戸氏と結んで石見高橋氏を討滅し、勢力を拡大した毛利元就
塩冶興久の乱が勃発する以前の享禄2年(1529)5月、石見に勢力を持つ高橋氏が大内方から離反して尼子氏と結んだため、大内氏は重臣の弘中氏と毛利氏に命じて高橋氏の討伐を開始しました。
かつて「三歳子牛の毛数ほど人数持ちたり」と強勢を唄われたという高橋大九郎久光は、元就の兄・興元の死後に家督を継いだ幸松丸の外祖父として強い発言力を持っており、元就も高橋氏に長女を嫁がせて姻戚を結んでいました。しかし、夭逝した幸松丸に代わって元就が家督を継ぐことになり、更に大九郎久光とその嫡子・元光が共に三吉氏との戦いで戦死したことから、次第に高橋氏と毛利氏との関係も微妙なものになっていったようです。
そして、元就は高橋氏が大内方から離反したことを好機としてこれを一挙に討滅し、享禄3年(1530)7月には大内義隆から高橋氏の旧領を与えられることになりました。
興久の乱に際して劣勢の経久方を支援するよう大内義隆を説得したのも元就でしたが、さすがの経久も興久方への対応で手一杯な状況では、毛利氏による高橋氏討滅を黙認せざるを得なかったようです。
また元就は高橋氏攻めに際して、かつて親細川・反大内方として毛利氏と敵対関係にあった五龍城主・宍戸元源と手を結んでおり、高橋氏の本拠地である阿須那藤根城の攻略には宍戸氏も協力しています。天文3年正月に元就は娘を元源の嫡孫・隆家に嫁がせて姻戚を結び、宍戸氏は後の毛利氏の飛躍に伴って、毛利一門六家の筆頭として厚遇されることになりました。
(なお石見高橋氏の庶流からは、後に尼子方として石見銀山の防衛拠点である山吹城主を務めた須佐高櫓城主・本城常光が出ています。)
阿須那の賀茂神社には、元就によって滅ぼされた高橋大九郎興光を祀る「剣神社」があります。
狩野秀頼筆「神馬図額」は、永禄12年(1569)に「大宅朝臣就光」(高橋就光)によって奉納されたものです。
高橋興光の敗死後、高橋氏の名跡は元就によって掌握されたのでしょう。
大内氏が大友氏と和睦、そして郡山城攻めへ
塩冶興久の乱を通じて協定を結んだ大内氏と尼子氏の間では一時的な小康状態が続いていましたが、天文4年(1535)から大内氏と大友氏の和睦交渉開始に伴って北九州の戦乱が沈静化すると、尼子詮久は石見・安芸・備後方面への圧力を強化し、再び両者の緊張が高まっていきます。
天文5年に尼子氏は塩冶興久の乱で背いた備後甲山城の山内直通を降伏させて家督に介入し、安芸・備後・石見では大内方毛利氏との衝突も起き始めていました。
安芸では頭崎城の平賀興禎が父の弘保と対立して尼子方に通じたため、大内氏は東西条代官・弘中隆兼を送り込みましたが、尼子方の支援を受けた城は容易には落とせず、天文9年6月に至ってようやく、毛利氏を主力とする大内方が造賀において平賀興禎勢と交戦して勝利しました。
また、すでに天文7年(1538)には大内氏と大友氏が和睦を結んだことで大内氏包囲網は崩壊しており、天文9年4月には尼子方に付いていた沼田小早川氏が大内方に転じ、6月には同じく尼子方であった安芸守護・武田光和が死去するなど、備後・安芸方面において尼子氏の不利が続いていました。
こうした情勢の変化を受け、ついに詮久は播磨に遠征していた軍勢を安芸方面に転進させることにしました。天文9年8月から翌年正月にかけて尼子氏が行った毛利氏の本拠地・吉田郡山城に対する攻撃は、このような状況で開始されたのです。
なお、軍記物では血気に逸る若き当主・詮久と叔父の刑部少輔国久ら新宮党に対して、ただ一人慎重策を唱えてこれを諌めようとした大叔父の下野守久幸が「臆病野州」と罵られ、郡山城攻めからの撤退戦で戦死する様が描かれていますが、多くは虚構と見られています。また、系図の記述や竹生島奉加帳の記名順や受領官途などから考えて、そもそも久幸は経久の弟ではなく弟の子であるとの指摘もあります。(系図と軍記物 尼子久幸について)
尼子下野守義勝のものと伝えられる墓。
広瀬町富田の尼子氏史跡
尼子清定・経久を祀る洞光寺。
尼子清定・経久父子のものと伝えられる宝篋印塔。
洞光寺から月山富田城跡を望む。
以前の記事 三日月公園に立つ尼子経久公銅像 にもたくさん載せています。
月山富田城跡の麓、「小守口」にある塩冶興久の墓。
月山富田城跡より
「花ノ壇」にはこんな顔出しも…!!
参考
室津海駅館 特別展『播磨を生きた官兵衛 ~乱世の中の室津~』の感想
10月26日、たつの市御津町室津にあります、室津海駅館の特別展『播磨を生きた官兵衛 ~乱世の中の室津~』を観てきました。
もうそろそろ終盤に入ろうとする大河ドラマ『軍師官兵衛』ですが、そこで描かれた官兵衛の播磨時代では、信長との関係(というか一方的な憧れ)ばかりが強調されて、小寺氏が擁立していた赤松宗家の存在は無かったことにされるわ、織田と毛利の間で揺れる播磨や備前の情勢を描く上で重要な役割となるはずの浦上宗景は名前すら出てこないわ、序盤の強敵として登場したはずの龍野赤松氏の赤松政秀も、ナレーションすらなくいつの間にか代替わりしている始末…。
渡邊大門先生の『戦国誕生』を読んで戦国時代の前期に興味を持って以来、赤松氏を入口として播磨戦国史を学んできた自分としては、せっかく播磨が大河ドラマの舞台となったというのに、あれでは織田と毛利の間で苦渋の選択を迫られた中小勢力の悲哀が全く視聴者に伝わらないし、何より福岡で大名として大成してからも播磨時代の地縁を大事にしたことは官兵衛の人柄を描く上で重要な要素だろうに、それが黒田家臣団の結束という形でしか描かれなかったことは実に勿体ないと感じます。
ドラマももうすぐ終わろうというこの時期に『播磨を生きた官兵衛』と題した展示が催されたのも、そういう消化不良な気持ちを汲み取ってのことかなと、勝手に想像した次第です。
前置きが長くなりましたが、今回の展示では官兵衛に限らず播磨の戦国時代の背景を知る史料と、室津と官兵衛の関わりとして今も残る「八朔のひな祭り」、黒田家の研究で知られる本山一城先生のコレクションなどが見られたほか、この日はその本山先生による「黒田官兵衛とたつの」と題した講演が開かれました。
会場内は撮影は禁止ですが、幸いなことに図録を購入できましたので、これを頼りに感想を書きます。
浦上村宗禁制札(備前市吉永美術館蔵)
永正十八年(1521)九月、播磨・備前・美作の国境にあるという天台宗の寺院、八塔寺に宛てて出された禁制です。
定 八塔寺
一、可被再興本堂造立仏像事
一、可被専勤行事
一、座方之輩不可背衆徒下知事
一、四方一里之内山留事
一、守護使不入事
右条々、任先規掟之旨、可有其沙汰、若於 違反之族者、 就交名注進、可被処罪科也、 仍所定如件
永正十八年九月 日
掃部助 (花押)
永正18年(1521)といえば、浦上村宗にとっては非常に重要な年になります。
村宗は先代赤松政則の夫人・洞松院の後見のもと宗家を継いだ赤松義村を主家としてきましたが、永正16年に自立を図ろうとした義村によって出仕を停止させられて以来、2年近くに渡って派遣された討伐軍を撃退し、永正17年11月にはすでに義村を出家させるとともに、義村嫡子の政村と義母の洞松院、義村正室の3人を室津に迎え入れており、守護としての実権をも掌握しようという状況にありました。
この永正18年に義村は再び挙兵するも一族の裏切りにより失敗、和睦という形で両者の対立は終結し、村宗は同年5月、細川高国の要請を受け、赤松宗家の置塩館で養育されていた前将軍・足利義澄の遺児亀王丸(後の義晴)を上洛させた後、室津の見性寺に幽閉していた義村を殺害したのです。
畿内では、将軍家を巡って義稙(義材)派と義澄派に分かれていた有力守護家同士の争いに加え、畿内随一の勢力を誇る細川家が政元亡き後の管領の座を巡り讃州家出身の澄元派と野州家出身の高国派に分裂、永正17年(1520)には澄元方の有力者であった三好之長が敗死、間もなく澄元も病死したことで弱体化していた澄元派に対して、京都を制圧した高国派の方でも、大永元年(1521)3月に将軍義稙が淡路へと出奔し、幕府は肝心の将軍を欠くという事態に陥っていました。
そんな状況の中、これまで澄元派であった赤松氏の実権を握った村宗が、義澄の遺児を将軍として擁立するという離れ業によって高国派に多大な貢献を果たし、これから飛躍しようという頃に出されたのが、この禁制というわけです。
この時期に村宗が八塔寺の辺りまで勢力を広げていたことが分かる史料で、内容的には仏事に専念することを奨励しているものですが、これまで定めてきた条々を引き継ぐもののようで、ここから60年以上も経た天正10年(1582)8月6日付にも、「仍所定如件」を「仍下知如件」に変えただけのほぼ同じ禁制が「八郎」(宇喜多秀家)の記名で出されています。
なおWikipediaによると、この4年前に当たる永正14年(1517)に置塩城主・赤松義村と三石城主・浦上村宗との間で八塔寺合戦が行われ、本堂・伽藍等が焼失したとのこと。八塔寺はかつて「西の高野山」と称された大きな寺院だったようですが、三ヶ国の国境に当たるため度々兵火に遭ったようです。
禁制に記された「可被再興本堂造立仏像事」の背景にはそういう経緯があったのですね。
浦上政宗感状(高橋秀知蔵)
こちらは天文9年(1540)と見られる、浦上村宗の子・政宗から家臣の高橋平左衛門に宛てて出された感状です。
去年於室構、日夜 粉骨無比類、殊於和泉 堺、被相届候条神妙也、 必恩賞可申沙汰候也、恐々謹言
四月十一日 政宗 (花押)
高橋平左衛門尉殿
享禄4年(1531)6月、摂津天王寺の戦いで赤松政村が細川六郎(澄元の子、後の晴元)を擁する堺方に寝返った「大物崩れ」の敗戦によって高国政権は一挙に崩壊、浦上村宗も乱戦の中で討死しましたが、同年10月には村宗の嫡子・虎満丸を叔父の国秀が後見する体制で立て直した浦上方が蜂起、今度は政村が敗退して明石城へと逃れる事態になり、播磨では天文5年(1536)頃に至るまで、再び赤松方と浦上方に分かれた内戦が続きました。
そのような状況で、すでに美作・備中・備前へと進出していた山陰の雄・尼子氏は、祖父経久から家督を継いだばかりの詮久が大軍を起こし、天文6年(1537)末頃から播磨への侵攻を開始しました。
浦上氏は政村と和睦して共に尼子氏に抗戦する道を選んだようで、政村の偏諱を受けた浦上政宗はまだ元服して間もない年頃と思われますが、天文8年(1539)に「室の構」で尼子勢を迎え撃つことになりました。
皮肉なことに、これまで浦上氏との対立で赤松宗家を支えてきた重臣の小寺則職や明石修理亮などはすでに尼子方に降伏しており、天文7年(1538)11月に赤松政村は本拠地の置塩城を捨て、淡路へと逃れる事態に陥っていました。
天文8年(1539)4月、政村は阿波守護・細川持隆の援助を受けて播磨へ帰国し、三木城の別所氏を頼ったものの、別所氏も尼子方に通じたと疑われたため、再び播磨を離れて堺へと逃れています。
現在の室津港から見た室山城跡
赤松晴政感状(中村文書)
浦上政宗は前述の高橋平左衛門尉に宛てたものと同じ日付で、ほぼ同じ内容の感状を中村三郎左衛門に宛てて出しているのですが、足利義晴の偏諱を授かって名を改めた赤松晴政からも、その3日前に当たる四月八日に感状が出されています。
これは今回の展示品ではないのですが、2004年に開催された特別展『室山の城 -語りつがれた謎の歴史-』の図録に掲載されているものです。
去年室要害、浦上 与四郎相践之処、無別儀 楯籠、殊今度、至和泉堺、 馳来之条神妙候、弥忠義 肝要候、必可褒美、恐々謹言
四月八日 晴政 (花押)
中村三郎左衛門殿
室津での戦いの詳細は分かりませんが、ここでも「室要害」において浦上与四郎(政宗)と共に戦ったことが記されており、政宗は赤松方として室津で防戦したものの敵わず、政村と共に堺へと落ち延びていたと察せられます。(政宗は踏みとどまって戦ったとする説もあって、よく分かりませんが…。)
晴政の播磨帰国が叶ったのはそれから1年以上を経た天文10年(1541)3月のことですが、それも自力ではなく、尼子氏が天文9年9月から天文10年1月にかけて行った安芸侵攻で、大内方の毛利氏が篭もる郡山城の攻略に失敗するという結果を受けてのことでした。
なお、後の天文21年(1552)以降、備前・美作を含む八ヶ国の守護職に補任された尼子晴久が再び侵攻した際、浦上政宗は尼子方に付きますが、政宗の弟・宗景は兄と袂を分かって毛利氏の支援のもと反尼子の戦いを繰り広げ、一方で将軍義晴によって備前・美作守護職を奪われた赤松晴政は、晴元政権を打倒して畿内の覇者となっていた三好長慶を頼ることになります。
(岡山県立博物館企画展『岡山の城と戦国武将』の感想(前編)をご参照ください。)
播磨国古城所在図(姫路市立城内図書館蔵)
近世に描かれたと思われる地図で、この図録の表紙にもなっている史料です。
東は三木郡・明石郡から西は佐用郡・赤穂郡までの播磨国内の各城と街道が描かれており、時代にばらつきがありますが、城には城主の来歴なども記されています。
室津には多くの舟らしき絵とともに町並みや城らしき建物が描かれ「置塩二代将 赤松兵部少輔政村住」と記されています。
御着城らしき城に「小寺相模守頼秀住 天河元祖」、妻鹿城に「小寺藤兵衛尉政職住」と記されているなど、興味深い箇所もあります。(後者については、芥田文書には天文17年に小寺則職が別所家臣の妻鹿氏を討った記録があるそうで、その時のことでしょうか?)
また、宍粟郡安志には「別所安治住」と記されていて、別所氏が足利義昭を擁する信長の上洛に伴い幕府方となった永禄11年から元亀年間にかけてのことと思われますが、別所氏の勢力が相当西まで食い込んで来ていることが察せられます。
個人的には「後尼子助四郎勝久」と記された赤穂郡「尼子山高野山城」も気になるところです。尼子山といえば尼子将監のものと伝えられる墓なども現存していて、尼子氏による播磨侵攻の数少ない痕跡には興味が湧きます。
なお、前回紹介した感状山城には「初赤松則祐住」とだけ記されており、やはり戦国時代の動向は伝わっていないようです。
村田出羽伝(村田家文書)
井口(いのくち)兵助こと村田出羽守吉次の外曾孫、吉田定俊の著作で、講談本「夢幻物語」の原本だそうで、有名な広峯神社に関わる黒田家の目薬伝説が記された内容とのこと。
村田出羽は「黒田二十四騎」に数えられ、朝鮮における虎退治で名高い菅六之助正利と並んで朱具足の着用を許された勇将とのことです。
(以下、本山一城先生の講演配布資料による)
井口氏は古くから赤松氏に仕え、印南郡井口城主となった井口家全は嘉吉の乱で戦死、揖西郡栄城に移った家繁は天文3年(1534)に浦上方と戦った朝日山合戦で戦死しています。
黒田家とは天文年間に栄にいた頃から関係を持っていたようで、黒田重隆の三男(官兵衛の叔父)で井手氏を継いだ勘右衛門友氏は、天文7年(1538)に井口家で生まれたとのこと。(青山合戦で討死)
吉次と共に官兵衛に仕えた三人の兄は皆討死しており、吉次は筑前入国後に官兵衛の命で鍋島直茂重臣の村田姓を名乗ったそうです。
なお「夢幻物語」は黒田家の目薬伝説がフィクションであると示す時によく名前を挙げられますが、本山一城先生曰く、実は読みやすく翻刻された本が存在しないそうで、今その作業を行っているとのことでした。直接子孫の方を訪ね回っておられることといい、フィクションだからと読みもせずに切り捨てるのではなく、そこから丹念に玉を探し出そうとする本山先生の姿勢には敬服しました。
本山一城先生の講演「黒田官兵衛とたつの」より、青山合戦のこと
官兵衛と黒田家を中心とした本山先生の講演も面白かったです。
多伎に渡る内容で詳細はあまり覚えていないのですが、永禄12年(1569)の青山合戦がスケールの大きい戦いであったことを強く仰っていたのが特に印象に残っています。
おそらく前述の別所安治が播磨北西部にかけて広く勢力を拡大したのもこの時のことで、別所氏は織田軍とともに幕府方の先陣として龍野の赤松政秀と連携し、これに対して置塩城の赤松義祐を擁する小寺・黒田氏が抗戦したのが8月の青山合戦で、母里一族24名が戦死という大きな犠牲を払いつつ何とか撃退したとされています。
しかし、戦いはこれで終わったわけではなく、更に翌9月には備前の浦上宗景が置塩方に加勢して室津を攻撃、10月に織田軍が室津を奪取、11月に赤松政秀が再び青山へと進軍した隙を突いて浦上宗景が龍野城を攻撃して政秀を降伏させ、12月には織田軍を撤退させたとのこと。
元亀元年には海路加古郡から上陸した浦上宗景は、別所氏の三木城にまで進出して城下を焼いており、一連の戦いで浦上宗景の果たした役割は非常に大きかったようです。英賀城の三木氏も小寺の与党ですし、室津を確保したことで制海権を掌握できたのが大きかったのでしょう。
青山合戦のことは、当時幕府方であった織田と毛利の間で使僧を務めた朝山日乗の書状にも書かれているそうです。(日乗は青山合戦の際に軍監を務めており、敗戦により失脚したとのこと)
室津の史跡
室山城跡は現在、その一部が「室津二ノ丸公園」として整備されています。
二ノ丸に当たる場所は平成9年から14年にかけて5回の発掘調査が行われ、5つに分かれた曲輪から備前焼の鉢、白磁や青磁などの貿易磁器、更に安土桃山時代と思われる瀬戸・美濃焼の椀や皿に加えて、江戸時代初期の唐津焼も出土しているそうです。
なお、17世紀中頃からは遺物の見られない空白期を経て、「室津千軒」と称された18世紀中頃の繁栄期後再び生活道具が現れているため、廃城の時期は17世紀初頭から中頃と考えられるそうです。
発掘調査で見つかった土塁や竪堀の跡も、今は何も残っていません。
室津の観光案内板。室津城跡からも程近い中央部には、赤松義村が最期を迎えたと伝わる見性寺も見えます。
現在の見性寺。
解説板には戦国時代のことは何も触れられていませんでしたが…。
現在でも浦上氏の子孫の方が関わりを持っているようです。
治承4年(1180)3月、厳島参詣の途中に室津で一泊した平清盛が旅の安全を祈願したという、賀茂神社。
文政9年(1826)にはシーボルトも立ち寄ったとか。
大きな社殿は江戸時代の繁栄ぶりを彷彿とさせてくれます。
賀茂神社には狩野元信の「神馬図額」2面も伝わっていたそうですが、現在は東京国立博物館に保管されているとのこと。
狩野元信といえば、甲冑姿の細川澄元像や道服姿の細川高国像が有名ですね。(自分の中では!)
室津海駅館特別展「播磨を生きた官兵衛~乱世の中の室津~」は11月24日まで開催中です!
なお、11月16日には展示説明会も行われるようです。
参考

- 作者:
- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター
- 発売日: 2011/06/01
- メディア: 単行本
赤松氏ゆかりの山城・感状山城
感状山城跡は相生市矢野町瓜生および森にまたがる感状山の尾根にあり、多段に渡る石垣造りの曲輪が特徴的な中世山城の遺跡です。
謎に包まれた感状山城の歴史
近世に成立した地誌『播磨鑑』には、建武3年(1336)、赤松円心が赤松氏の本拠地である白旗城に籠もって新田義貞率いる追討軍を50日以上に渡り足止めした際、円心の三男・則祐が出城として築いたのがこの城で、ここで勇戦した戦功によって足利尊氏から感状を授かったことから「感状山城」と呼ばれたという伝承が記されています。
『ひょうごの城』の感状山城の項(橘川真一氏)によると、『播備作城記』には「岡豊前守居城也元亀年中落城也」とあり、地元の史料『岡城記』には嘉吉元年(1441)に「感状山城等の城郭悉く没落す」、文正元年(1466)に「竹内祐太夫義昌 当時守護代なり」とあるそうです。
そして、地域の支配者は赤松氏→浦上氏→龍野赤松氏→浦上氏→宇喜多氏と変わっていますが、地元の豪族であった岡氏が引き続き矢野庄を領有していたと推測されています。
また、『日本城郭大系12巻』(昭和56年)では天正5年に秀吉の上月城攻めに際して落城したと推測され、兵庫県教育委員会『兵庫県の中世城館・荘園遺跡』(昭和57年)でも赤松則房の代に至って天正5年、秀吉の攻略に遭って落城したと書かれおり、地元でもその時のこととする落城伝説が伝えられているようです。
しかし、同時代の史料やその他の文献に感状山城の名は現れておらず、実際の築城、廃城の時期や城主の名前など具体的なことは分かっていません。
昭和60年から63年にかけて実施された発掘調査では3つの曲輪と大手門跡が発見されたほか、15世紀から16世紀と見られる備前焼の大鼇、中国産の白磁や青磁、青花磁器などの破片が数多く出土しました。
兵庫県立考古博物館の岡田章一氏によると、その中には備前焼の耳付小壺や筒型容器など茶器として利用されたと思われるものや高級品の貿易陶磁など、播磨の中世遺跡では御着城や姫路の城下町でしか出土例のない物が含まれていることから、城主は唐物趣味の茶の湯を嗜んだ有力者で、西播磨地域に勢力を拡げた龍野赤松氏、あるいは備前を本拠として瀬戸内航路の要衝である室津に拠点を築いていた浦上氏が考えられるそうです。
感状山城跡を歩く…登山道から物見台まで
感状山への登山道の入口は 羅漢の里 という自然体験施設の中にあります。
自動車の場合は施設の駐車場が2ヶ所あるので、どちらかに停めると良いです。(無料でした)
石造りのモニュメントと、現代の刀工「桔梗隼光」(ききょうはやみつ)鍛刀場の水車小屋が目印になります。
この側を通って奥の方へと進みます。
ここは古くから十六羅漢の石仏が有名で、かつては「羅漢渓」と呼ばれた名勝だったようです。
入口付近には、大正時代に建てられた石碑や歌碑が散見されました。
それら石碑の中に「感状山光専寺貫主 赤松性真」と記された物がありました。「性○」は赤松家の戒名なので気になりますね…。(政則=性雲、義村=性因、晴政=性煕)
物見台まで続く登山道は結構歩きやすく整備されています。
途中から少しずつ岩が増えてきますが、運動靴さえ履いていれば、軽装でも問題ないレベルです。
登山道からの眺め。朝8時頃ですが、霧が出ていてとても綺麗でした。
物見台に近付くとともに段々と山城感が出てきて、テンション上がります!
しかし、肝心の物見台はあまり展望はよくありませんでした…。
感状山城跡を歩く…Ⅲ曲輪群から大手門跡周辺へ
倉庫跡を経て、Ⅲ曲輪(近世城郭で言う三の丸)辺りはかなり広くなっています。
大手門跡方面にはこの辺から下りられます。
六段の石段で構成され、鶴翼状に配列された総石垣づくりの大手門とのことですが、かなり崩壊が進んでいます。
石積み技術の未熟さによるものか、あるいは廃城の際に中途半端に破壊したまま放置されたのでしょうか。
大手門の登り口を上から見るとこんな感じで、登山道と比べると荒れてます。
ここから下りてみたい気持ちもありましたが、地図を見ると結構離れた場所に出るようで時間の都合もあり諦めました。
大手門のすぐ内側には井戸があって、今でも水が湧き出ているようでした。(真夏でも涸れることがないそうです)
感状山城跡を歩く…Ⅲ曲輪群から腰曲輪群、北曲輪群を経てⅠ曲輪へ
建物の遺構も見つかったというⅢ曲輪群は複雑な段差を持つ構造だったようで、側面を見ると広範囲に渡って石垣が残っています。
こんな細い道が続いていたので、つい奥まで見に行ってしまいましたが…このルートはちょっと失敗でした。
一番の見どころの南曲輪群を避けて、裏から攻める形になってしまったので…。
腰曲輪群には、少しだけ石垣が残っていました。
北曲輪群はよく分かりませんでした…。
あっさりと、山頂のⅠ曲輪まで到達してしまいました。
感状山城跡を歩く…Ⅰ曲輪から南北Ⅱ曲輪群を経て圧巻の南曲輪群へ
城山の北端に当たるⅠ曲輪には建物の礎石が残っていて、敷地いっぱいに御殿が建てられていたと推定されているとのこと。
この写真から見ると、確かにもうギリギリのような…。
北Ⅱ曲輪との間から見たⅠ曲輪の側面。見ての通り山頂付近まで岩が結構ごろごろしている山なので、未熟ながら結構早くから自然石に石積みを組み合わせた城だったように思えます。
Ⅰ曲輪から北Ⅱ曲輪へ。
南北Ⅱ曲輪の西側面には広範囲に渡って石垣が残っており、「犬走り」と呼ばれる帯曲輪が配置されていたようです。
しかし、時間の経過もあるかもしれませんが、結構スカスカな状態です。そのうち大雨で自然崩壊してしまいそうで、ちょっと心配してしまいます。
南Ⅱ曲輪でも大規模な建築と見られる礎石群が発見されているそうで、Ⅰ曲輪の本丸御殿に対して、常の御殿(日常生活の場所)であった可能性があるとのこと。
これも何かの跡でしょうか。
正直なところ、大規模な遺跡とはいえ現状はいまいち迫力に欠けると思っていたら…ここから先の南曲輪群は、素晴らしかったです。
ここは眺望も良いです。
この二段目の腰曲輪の石垣は全長21m、高さ4.5mで、感状山城の中では最大の物だそうです。
ゆるい曲線状で粗さが残る石積みではありますが、尾根を利用して六段に渡り削平された曲輪群は、非常に見応えがあります。
下から登ってきたところでこの曲輪群に出会っていたら、もっと興奮しただろうなと、少し後悔しました。
ちょっと離れたところから、側面も眺めてみたいですね。
初めて訪れる方にはぜひ、まずはⅢ曲輪群からこの南曲輪群を経て、山頂へと向かうルートをおすすめします。
ここが南曲輪群に向かって登ってくるメインルート。
下から見るとこんな感じ。崩落があったのか、ロープが張ってありました。
土の城から石垣の城へと発展したように言われることがありますが、この感状山城跡を見て、そう単純なものではないと感じました。石積み技術の発達具合に関わらず、石があればそれを活用しようとするのは自然なことでしょう。
感状山城と光専寺と赤松氏
「羅漢渓」入口の石碑に記された「感状山光専寺貫主 赤松性真」が気になったので調べてみました。
光専寺は感状山城の大手門側に現存する真宗本願寺派の寺院で、相生市矢野町の公式Webサイトに以下のような記述がありました。
本尊 阿弥陀仏。開基は赤松義村の孫小林義光、その頃蓮如上人の御代で六字名号を拝領、その後第六代教誓に至り実如上人より寺号・木仏を賜わる。経堂 天保12年建立。鐘楼 宝暦10年。昭和17年、福田眉仙画伯が襖絵を描いたことから、別名、眉仙寺という。
赤松宗家以外の人物で将軍家由来の「義」を名乗っているというのは不可解ですし、義村の孫の世代であれば蓮如(明応8年没)のはずはないと思いますが…。
亀山本徳寺から発行されている『播州真宗年表 (第2版)』を確認したところ、以下のような記述がありました。
1509年(永正6年)といえば義村はまだ元服したばかりで、洞松院尼が後見していた頃です。
ちょうどこの年に英賀城主・三木通規が実如上人の御連枝の下向を願い出ていることからも察せられますが、すでに英賀では在地の長衆(富裕な商人などの有力者)や寺の坊主によって門徒集団が組織されていたようです。
播磨国内では公的には守護赤松氏が先代政則以来、真宗の布教を禁じていましたが、永正9年(1512)に実如の第四子・実円が下向するとともに三木氏一族が一向宗に帰依、翌年には実如上人から赤松義村へ名馬が寄贈されたことで真宗禁制が解かれ、布教の一大拠点となる本徳寺「英賀御堂」の建立に繋がりました。
義村は後に浦上村宗によって弑逆されますが、その村宗も義村の子・政村(晴政)によって討たれ、息つく暇もなく浦上国秀の後見を受けた浦上政宗が蜂起して赤松氏と再び争い、更に但馬の山名氏、そして山陰の雄・尼子氏による侵攻を受けました。
その間の感状山城の動向は明らかではありませんが、後に光専寺が再興されるに当たり、赤松氏ゆかりとされる感状山の麓で、本願寺との関係改善を果たした赤松義村との繋がりを強調する縁起を後世に伝えようとしたものかもしれません。
感状山城の落城伝説
時期は明らかではありませんが、地元では落城時に井戸の中へと身を投じた姫の伝説が残されているようです。
(1)感状山城が落城した日、城には何人かの姫がいました。
押し寄せる大軍に逃げ迷った姫の1人は、人手にかかって恥をさらすよりはと、日頃、可愛がっていた金色の羽を持つ鶏を抱いて、城内にあった井戸に身を投じました。
それ以来、毎年、元旦がくると、その井戸の中から鶏の鳴く声がきこえるといいます。
(2)もう1人の姫は、城を逃れて、城下の藤堂(とうどう)村にたどりつきました。藤堂村の人々は、姫を大事にかくまい、その後も大切にもてなしました。姫は死ぬ直前に、「お世話になったお礼に、この村では、美人ばかりが生まれるようにお祈りします」と言ったそうです。
それ以来、藤堂村では、代々、美人が生れるといいます。
(3)感状山城には、非常に備えて、ぬけ穴を作っていました。それは、森の光専寺(こうせんじ)の北山手から流れる水を通す大溝(みぞ)が、寺屋敷の地底を抜け、鐘楼(しょうろう)の横手を通って、南側の溝と合流するというものでした。
感状山城が落城した日、ぬけ穴をたどって逃れようとした1人の武士がいました。しかし、思うようにぬけ出られず、死んでしまったのです。
その後、武士の亡霊(ぼうれい)がこの溝に出て、毎夜、通行人に墨つけをするというのです。
ここにも光専寺が登場していますが、城からの抜け穴が通っていたということは、それだけ親しい関係だったのでしょうか。
瓜生の八柱神社
「羅漢の里」の手前には八柱神社がありますが、ここがなかなか素敵な神社だったので、写真を掲載しておきます。
奉納絵馬がずらり。
中でも、明治42年に奉納されたという赤穂四十七義士の数々は壮観です。
天保十三年(1842)…古いですね、これは。意外と色が残っています。
郷土の歴史が刻まれた、絵馬たち。
境内に向かって右手には「バクの道」と呼ばれる感状山への登山道があるようで、再訪の機会があればこちらから登るか、あるいは光専寺から大手側を登ってみたいです。
追記:感状山城と光専寺の縁起について推測
『播磨鑑』を再度確認したところ、光専寺については項がありませんでしたが、感状山城の項では「城主ハ赤松彌太郎義村 字道松丸後號政村 父ハ刑部介政資」「又赤松義村居住ス(後改政村)初メ竹内助太夫義昌ノ養子タリ 後政則ノ養子トナル 政則コレヲ婿トシ置鹽山ニヲク 後義村鞍掛ヘ移ル」と記されていました。
道松丸は道祖松丸の誤記として、どうも地元では感状山城の城主が義村であったと伝わっているようで、光専寺の縁起にはその辺りの事情が関わっていると思います。
神戸新聞文化部編『杜を訪ねて ひょうごの神社とお寺[下]』の光専寺の項によると、現住職の赤松誠真さんが語られた寺の縁起には、赤松円心が創建したという円応寺が前身で、正和年間に矢野庄が東寺領となったため真言宗に転じ、その後赤松義村の孫・小林義光(のちに釈正西)が実如上人の感化を受けて真宗に転じ、六代教誓に至って寺谷から現在地へ移転したとあるそうです。
また住職は、寺谷以前の経緯は全く不明だそうですが、付近には「改宗」という地名があって住民のほとんどが門徒なので、真宗に転じた頃の光専寺はそこにあったのではと推察されています。
亀山本徳寺『播州真宗年表 (第2版)』の記述「1509 正西、赤穂郡矢野森村に光専寺を開基す」を合わせて考えると、実如上人の感化を受けた正西=小林義光が1509年に開基あるいは真宗へと転派した後、六代の教誓に至って、長らく廃城となっていた感状山城跡の麓へ寺院を移転する際、山号を「感状山」と改めるとともに、赤松円心ゆかりの円応寺との繋がりと、城主として地元に伝えられていた「赤松義村」の末裔を称したのではないでしょうか。
地元の史料『岡城記』が伝える、嘉吉の乱後の文正元年(1466)に守護代となったという竹内義昌に、赤松七条家出身で道祖松丸(赤松宗家の幼名)と名付けられていた義村が養子入りしたという話は色々とおかしいのですが、近世に至ってから光専寺がこの地元の伝承を元に正西=小林義光は「赤松義村」の孫であったと称したとすると、大幅な年代の差異も辻褄が合ってしまうことになります。
おそらくその頃には地元でも、赤松氏と感状山城の関係について確かなことは分かっていなかったのでしょう。今後の感状山城跡の調査研究に要注目です。
参考
- 神戸新聞文化部編『杜を訪ねて ひょうごの神社とお寺 [下]』

- 作者:
- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター
- 発売日: 1990/12
- メディア: 単行本
- 朽木史郎、橘川真一編著『ひょうごの城紀行 上』(神戸新聞総合出版センター)

- 作者:
- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター
- 発売日: 1998/04
- メディア: 単行本








































































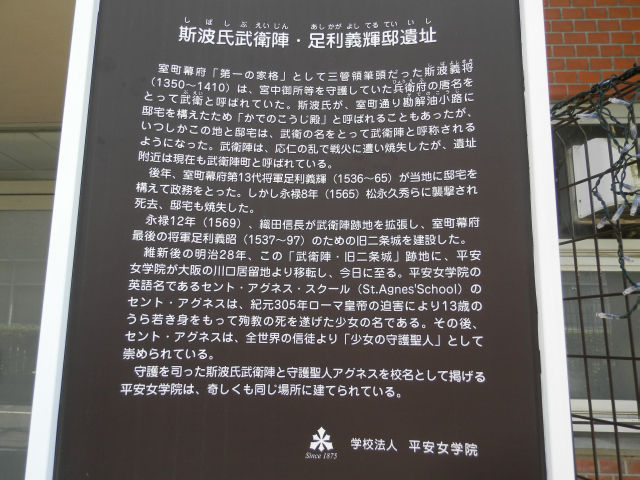












![群書類従 第20輯 合戦部 [1] 群書類従 第20輯 合戦部 [1]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41tgn44n9DL._SL160_.jpg)